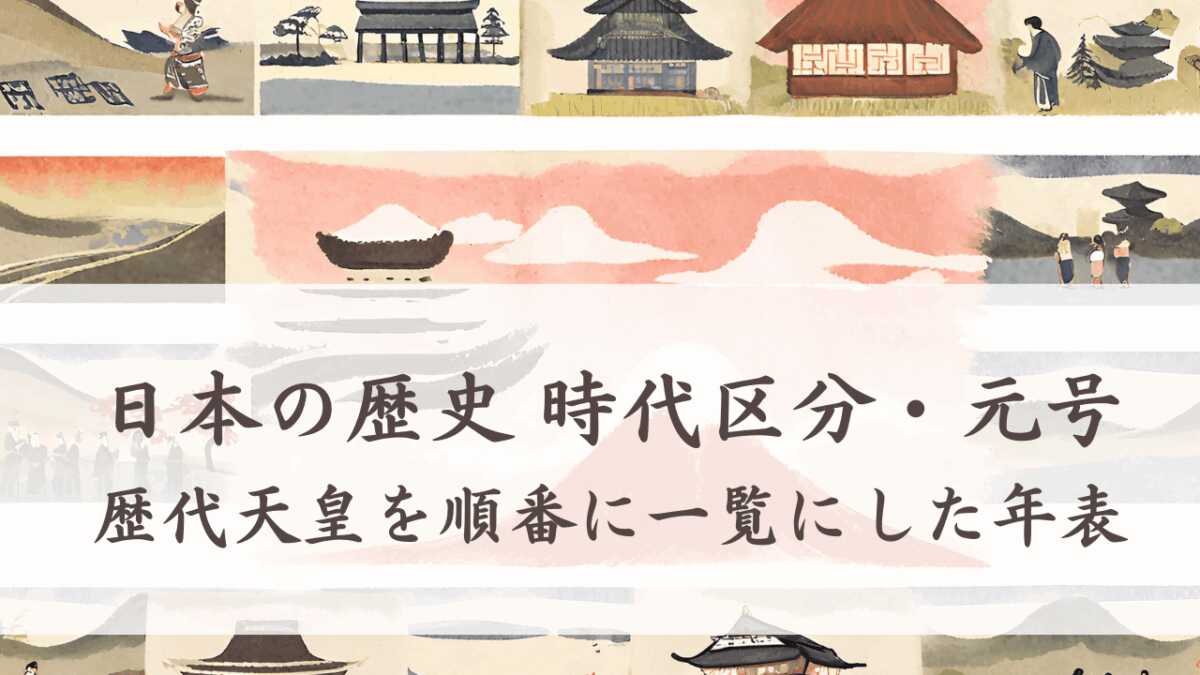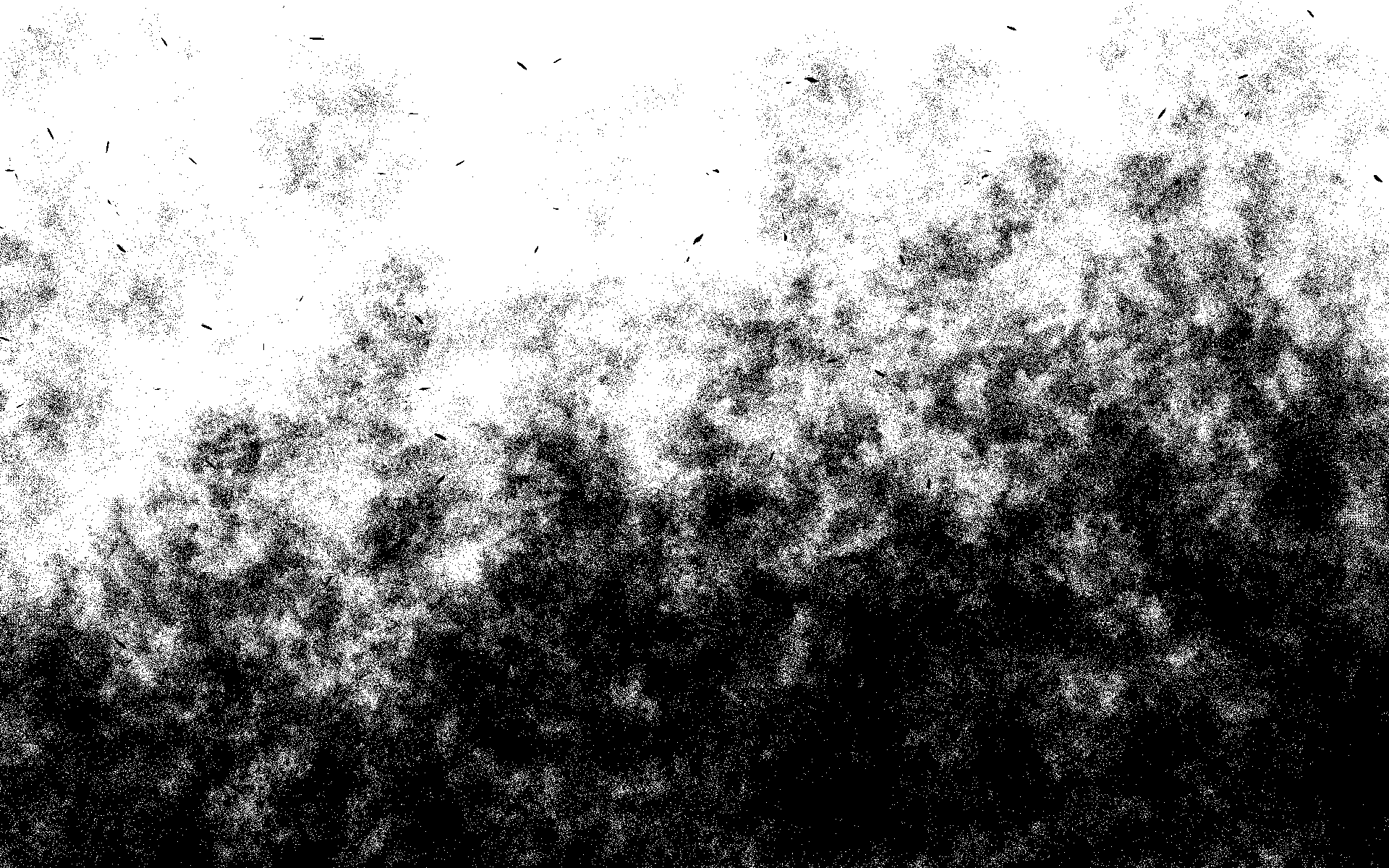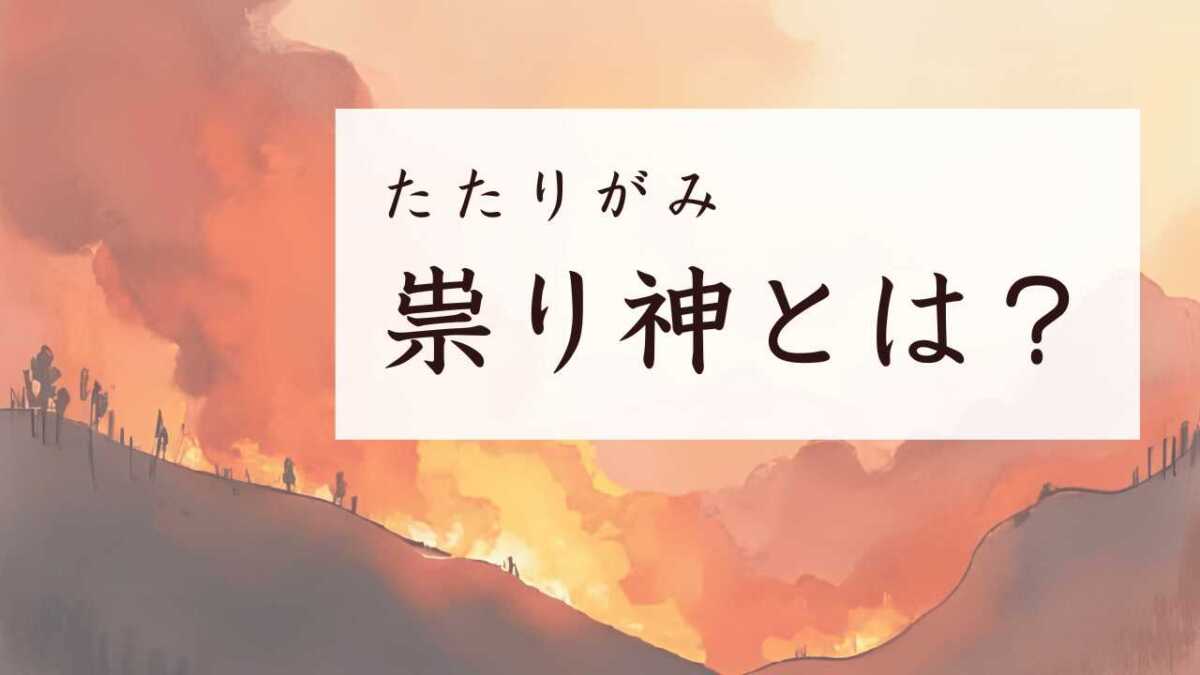第75代・崇徳天皇は、院政期の権力抗争のさなかに即位・譲位を経て上皇となり、保元の乱の敗北により讃岐へ配流されました。やがて「日本三大怨霊」の一として語られますが、その生涯は政治史と宗教文化の交差点に位置します。
この記事では、系譜と即位から配流までの歩み、在位号「崇徳天皇」と院号「崇徳院」の関係、百人一首の名歌の背景、怨霊像が形成された過程を整理します。あわせて、白峯神宮の御廟所(スポーツ守護の信仰)と香川・白峯陵の意味を、史料に基づいてわかりやすく解説します。
広告
第75代崇徳天皇とは?
崇徳天皇(第75代、1123〜1142在位)は鳥羽天皇の皇子です。読み方は「すとくてんのう」です。譲位して上皇となったのち保元の乱(1156)で後白河方に敗れ、讃岐へ配流されて1164年に崩御しました。不遇の最期から怨霊視が広まり、日本三大怨霊の一とされます。小倉百人一首に恋歌を残し、京都・白峯神宮や香川・白峯陵で今も顕彰されています。
広告
崇徳天皇の系譜
崇徳天皇は第七十五代の天皇で、伝統的系譜では父が鳥羽天皇、母が待賢門院藤原璋子とされます。異母弟に近衛天皇と後白河天皇がいます。中世以来、上皇政治と院政の力学のなかで血統をめぐる風説が政治対立の素材となりましたが、史料学的には宮廷派閥の思惑が反映された言説として扱われます。皇子女には重仁親王をはじめとする親王が知られ、継承をめぐる駆け引きの焦点にもなりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 諱 | 伝統的に顕仁親王とされます |
| 父母 | 鳥羽天皇/待賢門院藤原璋子 |
| 異母弟 | 近衛天皇、後白河天皇 |
| 皇子 | 重仁親王ほか |
| 在位 | 1123年から1142年までとされます |
広告
崇徳天皇の歴史 天皇から上皇、そして流離へ
崇徳天皇は幼くして即位し、のちに近衛天皇へ譲位して上皇となります。院政の主導権は鳥羽院から近衛天皇側へ移り、近衛崩御後の継承では後白河天皇が即位しました。こうして崇徳上皇は院政の主導から遠ざかり、支持基盤の再建に努めます。1156年、崇徳方と後白河方が衝突した保元の乱では、崇徳院は源為義らの武力を背景に復権を図りますが、平清盛・源義朝らを擁する後白河方に敗北しました。敗戦ののち、崇徳院は讃岐国(現・香川県)に配流され、都への復帰は叶わないまま1164年に崩じます。この配流と最期の境遇が、のちの怨霊譚の土壌となりました。
| 年代 | 出来事 | 意味 |
|---|---|---|
| 1123 | 即位 | 幼帝として政務は院政に委ねられます |
| 1142 | 近衛天皇に譲位 | 上皇として院政復権を模索します |
| 1156 | 保元の乱 | 後白河方に敗れ政治的失脚が決定します |
| 1156以後 | 讃岐配流 | 都から隔絶され、宗教的修行と祈誦に専念します |
| 1164 | 配所で崩御 | のちの怨霊伝承の淵源となります |
広告
崇徳天皇と崇徳院の関係
「崇徳天皇」は在位中の尊号で、「崇徳院」は譲位後の院号です。
保元の乱以前、崇徳院は院庁を通じて人事や財政の影響力を保持しようとしましたが、近衛天皇期の摂関家や後白河天皇の即位でその余地は狭まりました。政治的挫折と配流を経て、宗教的権威に依拠する「祈りの君」へと姿を変えたことが、後世の文学や説話に濃い陰影を与えます。すなわち「天皇=政治権力」「院=祈りと文化」という二つの位相が、一人の生涯の中で対照的に現れたのです。
広告
崇徳院としての百人一首の和歌
小倉百人一首には崇徳院名義の一首が採られています。
「瀬をはやみ 岩にせかるる滝川の われても末に 逢はむとぞ思ふ」
急流が岩で二つに分かれても、下流で再び合流するように、今は隔てられていても、やがてまた逢えるはずだという恋の歌です。配流以前の作と伝えられ、政治・家族関係の離合集散に翻弄された院自身の境遇と響き合うように読まれてきました。技巧面では比喩の鮮やかさと結句の意志が印象的で、王朝和歌の成熟を示す名歌と評価されています。
広告
崇徳天皇の怨霊像はどのように生まれたか
崇徳院は配所で写経や法会に励んだと伝承されます。中世説話の一部は、血で経文を書いたが受納を拒まれた怨みが都に災いをもたらしたと語り、戦乱や天災を崇徳院の祟りに結びつけました。こうした語りは政治的正統の動揺と災厄の連鎖を「怨霊」を通じて説明する中世的世界観の産物であり、同時に御霊信仰の広がりの中で、荒ぶる霊を神として祀り鎮めるための宗教的・社会的装置でもありました。後白河院政下の権力構造と平氏政権の台頭という歴史過程が、崇徳怨霊譚の定着を後押ししたことは見逃せません。
日本三大怨霊(にほんさんだいおんりょう)とは
「日本三大怨霊(にほんさんだいおんりょう)」とは、平将門・菅原道真・崇徳天皇の三名を指す呼び名です。
いずれも政争や配流の末に非業の死を遂げ、そののち都や地方で起きた災いが彼らのたたりと語られました。怒れる霊を祀って慰め、鎮めることで災厄を避けようとする「御霊信仰」の中で、三人はやがて神社に祀られ、守護神としての側面を獲得していきます。
広告
白峯神宮と崇徳天皇御廟所 スポーツの守護神としての信仰
京都市上京区の白峯神宮は、明治期に創建され、主祭神として崇徳天皇と淳仁天皇をお祀りします。境内には「精大明神」が祀られ、古来の蹴鞠信仰と結びついて、現代ではサッカーをはじめ球技全般の守護神として広く崇敬されています。奉納球や必勝祈願が盛んで、祟りの相から守護の相へと転ずる日本的鎮魂の形が、スポーツ文化の中で生き続けていることがわかります。白峯神宮の「崇徳天皇御廟所」は、都の鎮護を願う場であると同時に、文化・芸能・スポーツの加護を祈る現代的な神域でもあります。
広告
崇徳天皇 白峯陵 配所に眠る天皇
讃岐国の配所の近く、香川県坂出市の白峯陵(しらみねのみささぎ)は、宮内庁治定の崇徳天皇陵です。五岳の一つ白峰の麓に位置し、周辺には白峰寺など崇徳院縁の寺社が点在します。京の白峯神宮と讃岐の白峯陵は、都と地方、祟りと鎮魂、記憶と巡礼という二つの回路で崇徳院の物語をつないでいます。参拝は玉垣外からの遥拝となり、供花と合掌が静かな時間を形づくります。
崇徳院の歴史的評価
崇徳院の生涯は、院政期の権力構造、摂関家と院庁のせめぎ合い、武士の台頭という共振点に位置します。政治の主導権争いに敗れ、宗教的実践に活路を求めた上皇像は、中世文学や説話に濃い陰影を与えました。怨霊という語りは恐怖の物語であると同時に、御霊を神として祀ることで共同体の秩序を回復する手順を可視化する機能を持ちます。白峯神宮での顕彰と白峯陵での追慕は、その転換の歴史を今日に伝える装置と言えるでしょう。
まとめ
崇徳天皇は、幼帝として即位し、上皇として院政の復権を目指しながら、保元の乱に敗れて讃岐で生涯を閉じました。配流と最期の境遇は怨霊譚を生みましたが、のちに神としての顕彰を通じて、守護と文化の神へと姿を変えます。百人一首の名歌は、その感性と意志を時代を越えて伝え、白峯神宮と白峯陵は、記憶と鎮魂をつなぐ二つの聖地として崇徳院の物語を今に語り継いでいます。