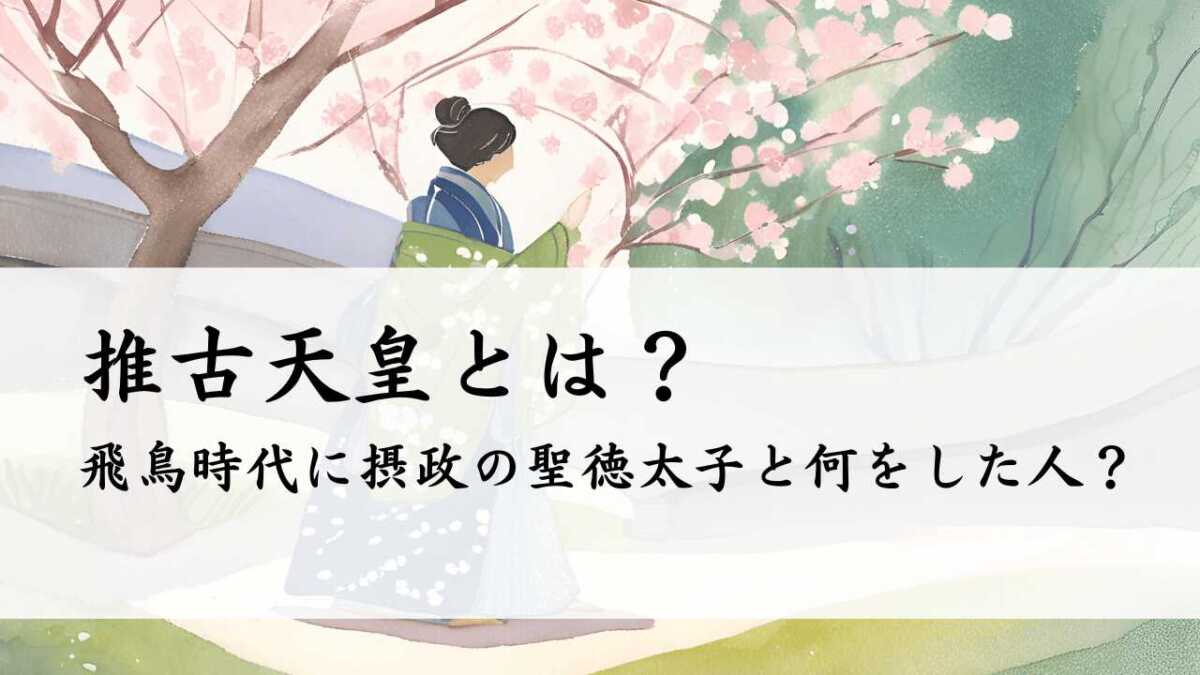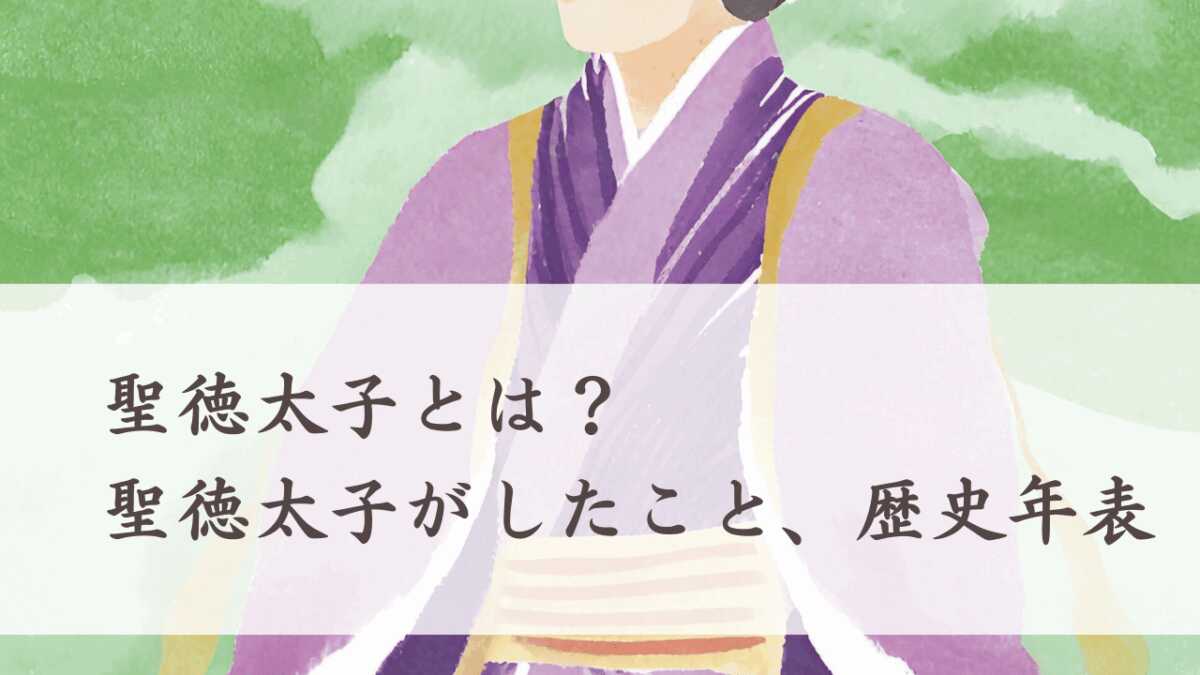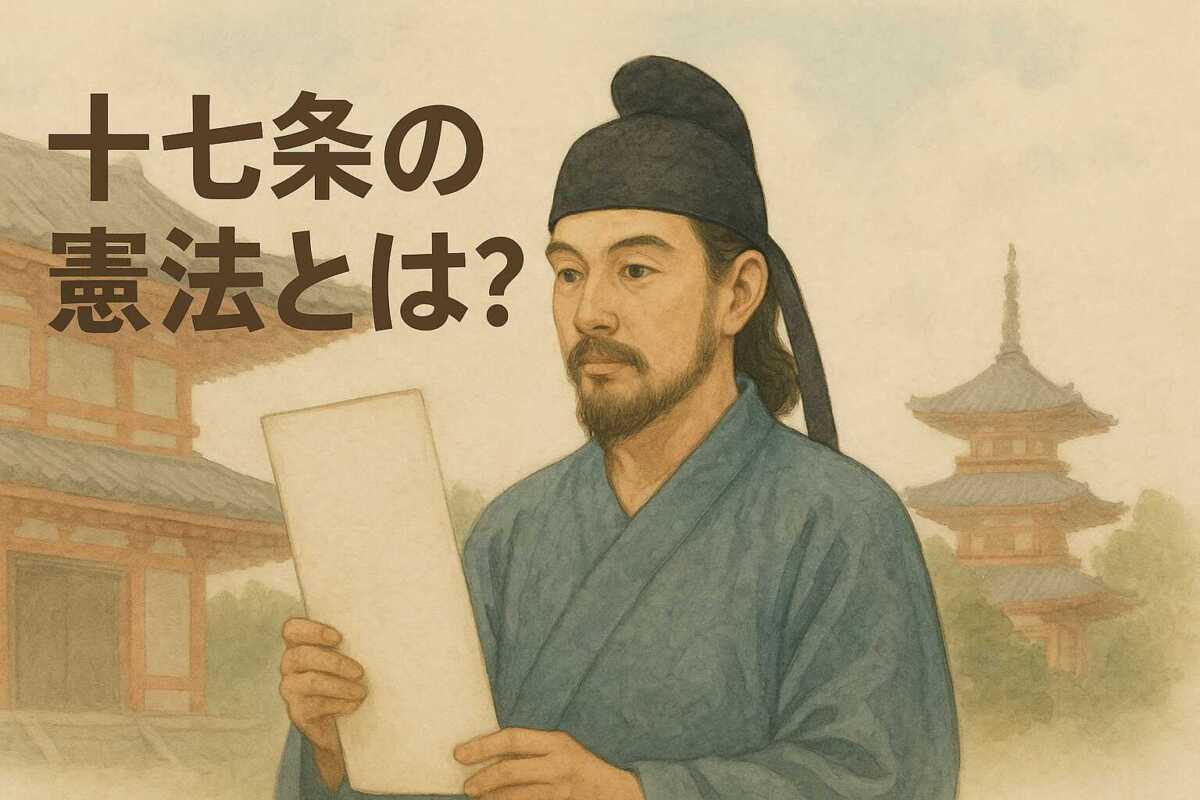
十七条の憲法は、日本の歴史においてもっとも古く、かつ精神的基盤を築いた法制度の一つとされています。制定されたのは飛鳥時代、律令制が整備される以前のことであり、現代の「憲法」とは異なるものの、国家運営や役人の心得を示した倫理的・道徳的な「憲法」として知られています。現代の法律のように罰則や細則を持つものではありませんが、国家を安定させるための道徳的基盤として、和を重んじる精神や、官人としての心得、仏教的・儒教的価値観が凝縮されています。
この記事では、十七条の憲法が誰によって、何のために、いつ定められたのかを整理しつつ、条文の原文とその現代語訳を一条ずつ紹介していきます。現代に生きる私たちが改めて読むことで、日本社会の精神的な礎がどこにあったのかを再確認する機会となるはずです。
広告
十七条の憲法は、誰が、いつ、何の目的で定めたのか?
十七条の憲法は、推古天皇10年(西暦604年)に、聖徳太子(厩戸皇子・うまやどのおうじ)によって制定されました。この時代、日本は飛鳥時代の初期にあたり、天皇を中心とする中央集権体制の確立が課題となっていました。
聖徳太子は、仏教の思想を取り入れつつ、中国の儒教的な政治理念や法制度を学び、国家の運営と官人の行動規範としてこの「十七条の憲法」をまとめたとされています。法というよりは、役人や臣下が守るべき道徳的な規範、つまり「公務員倫理」とも言うべき内容であり、秩序ある国家の形成を目的としていました。
広告
十七条の憲法の原文と現代語訳
ここからは、聖徳太子によって記された原文(「日本書紀」所収)と、その意味を現代人にも理解しやすいよう現代語訳を対比して紹介していきます。
第一条 和を以て貴しと為し、忤ふること無きを宗とせよ
原文
一に曰く、和を以て貴しとなし、忤ふること無きを宗とせよ。人皆党あり、亦達れる者は少し。是をもって、あるいは君父に順わず、上に逆らい下を悩ます。しかれども、上和ぎ下睦びて事を論ずれば、事理自ずから通ずべし。
現代語訳
第一条では、人々が仲良くすることを最も大切にし、争わないことを基本にしなさいと述べています。人は誰でも偏った考えを持ち、十分に理解している者は少ないので、互いに争いがちです。しかし、上に立つ者も下にいる者も心を合わせて話し合えば、物事は自然とうまく運ぶはずです。
第二条 篤く三宝を敬え
原文
二に曰く、篤く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり。すなわち四生の終帰、万国の極宗なり。
現代語訳
第二条では、仏・法・僧の「三宝」を深く敬いなさいと述べています。三宝は人々が安心して生きるための拠り所であり、すべての国の根本的な教えでもあるのです。
第三条 詔を承りては必ず謹め
原文
三に曰く、詔を承りては必ず謹め。君を天とす。臣を地とす。天は覆い、地は載す。
現代語訳
第三条では、天皇の命令を受けたら必ず謹んで従いなさいと説いています。天皇は天のように国を覆い、臣下は地のように民を支える存在であり、両者の調和が国を支えるのです。
第四条 群卿百寮、礼を以て本と為せ
原文
四に曰く、群卿百寮、礼を以て本と為せ。礼なきは則ち無きに同じ。
現代語訳
第四条では、官僚たちは礼儀を最も大切にしなさいと述べています。礼がなければ、人間社会の秩序は失われてしまいます。
第五条 罰を懲らし、徳を明らかにせよ
原文
五に曰く、臣を治むるの道は、明に罰を懲らし、正に徳を明らかにするに在り。
現代語訳
第五条では、統治においては罪を犯した者には罰を与え、善を行った者にはその徳を明らかにして称えなさいと述べています。
第六 悪を懲らし善を勧むるは、古の良典なり
原文
六に曰く、悪を懲らし、善を勧むるは、古の良典なり。
現代語訳
第六条は、悪を罰し善を励ますことが、古来より理想とされた良い政治の在り方であることを示しています。
第七条 人各その職を執り、専らに務めよ
原文
七に曰く、人各その職を執り、専らに務めよ。
現代語訳
第七条では、人それぞれが自分の職務に集中し、責任を持って取り組むことの大切さを説いています。
第八条 群卿百寮、早く朝し、晏く退くべし
原文
八に曰く、群卿百寮、早く朝し、晏く退くべし。
現代語訳
第八条は、役人たちは朝早く出勤し、遅くまで働くべきであるという、勤勉の精神を説いています。
第九条 信を以て本と為せ
原文
九に曰く、信を以て本と為せ。人に信なきは、事成ることなし。
現代語訳
第九条では、信頼を大切にしなさいと説いています。人と人との関係に信がなければ、物事は決してうまくいきません。
第十条 忿(いか)りを絶ち、瞋(いか)ること無かれ
原文
十に曰く、忿りを絶ち、瞋ること無かれ。
現代語訳
第十条は、怒りの感情を抑え、冷静でいることの重要性を説いています。怒りにまかせた行動は誤りを生みます。
第十一条 功を論ぜずして、過を責むること無かれ
原文
十一に曰く、功を論ぜずして、過を責むること無かれ。
現代語訳
第十一条では、人の過失を責める前に、その人のこれまでの功績にも目を向けるべきであると教えています。
第十二条 国司国造は百姓を愛し、殺さざるを本とせよ
原文
十二に曰く、国司国造は百姓を愛し、殺さざるを本とせよ。
現代語訳
第十二条は、地方官は民を大切にし、過度な取り立てなどで苦しめることがあってはならないとしています。
第十三条 諸の悪を棄てて善に従うことは、これ聖の道なり
原文
十三に曰く、諸の悪を棄てて善に従うことは、これ聖の道なり。
現代語訳
第十三条では、悪を捨て善に従う生き方こそ、賢人や聖人の道であり、社会にとって望ましい姿であると説いています。
第十四条 官人は禄を食む者なれば、必ず忠を致せ
原文
十四に曰く、官人は禄を食む者なれば、必ず忠を致せ。
現代語訳
第十四条は、公の給料を受け取る立場にある者は、私欲を離れて忠義を尽くすべきであるという考え方を示しています。
第十五条 私を棄てて公を務めよ
原文
十五に曰く、私を棄てて公を務めよ。
現代語訳
第十五条は、個人の利益よりも公共のために働くことが、役人の基本的な姿勢であると説いています。
第十六条 民を使うには時を以てすべし
原文
十六に曰く、民を使うには時を以てすべし。
現代語訳
第十六条は、人民を労働に使うときには農繁期を避けるなど、適切な時期を選んで配慮せよという教えです。
第十七条 物事は独り断むべからず
原文
十七に曰く、物事は独り断むべからず。必ず衆と論え。
現代語訳
第十七条は、すべてのことを一人で決めるのではなく、関係者で相談し、合意の上で決定せよという合議の精神を説いています。
広告
十七条の憲法で日本の理念の出発点を見つめ直す
十七条の憲法は、法としての強制力よりも、心のあり方、礼節、信義、そして公のために尽くす姿勢を説いた規範でした。聖徳太子が示したこれらの条文は、日本人の精神性や政治思想に深く根付き、後の律令制度や儒教的官僚体制の土台ともなっていきます。
現代の社会においてもなお、人間関係や組織運営において通用する価値が詰まった内容といえるでしょう。