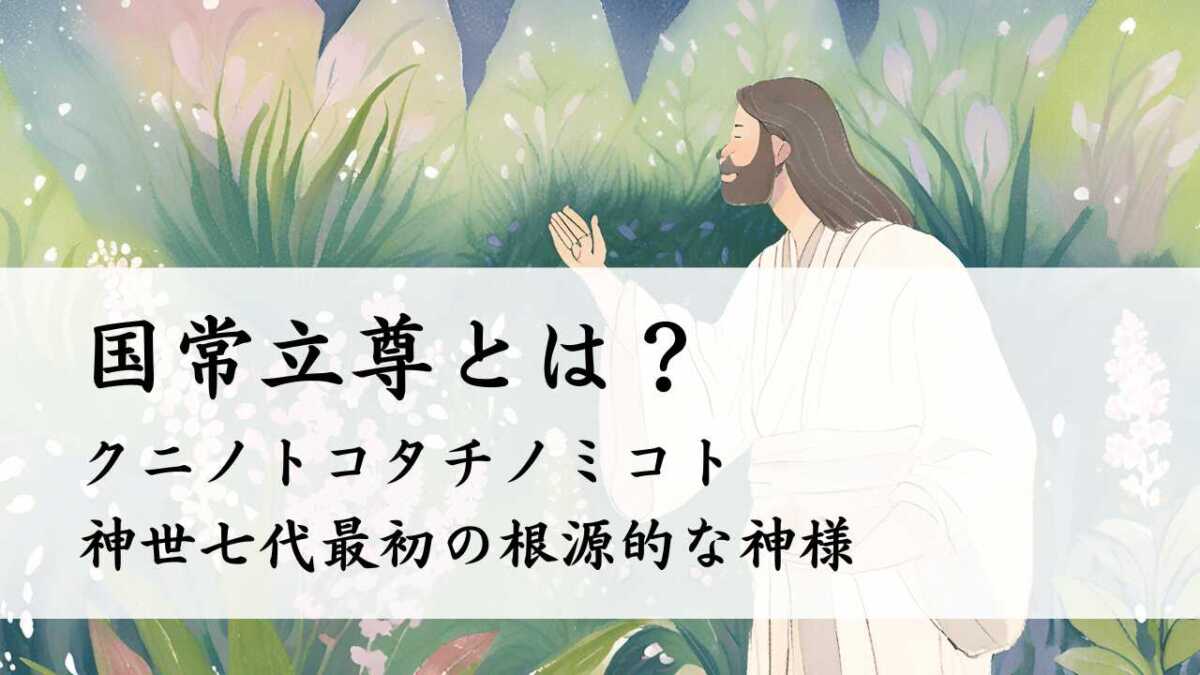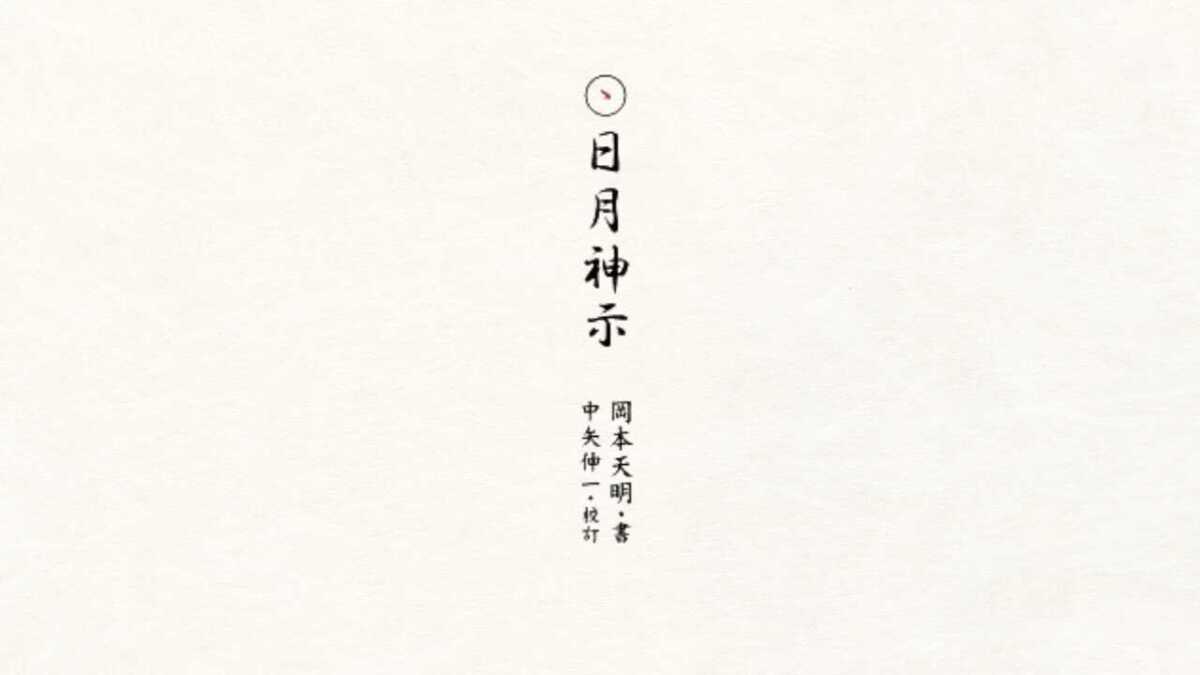
昭和19年、画家・岡本天明が突如受け取ったとされる神の啓示「日月神示」。神道の根源神・国常立尊をはじめとした神々の言葉が、漢字仮名交じりの独特な文体で綴られています。戦争、天変地異、そして人類の大転換を予告するような内容は、戦後の精神世界に多大な影響を与えました。本記事では、「日月神示」の成り立ち、巻ごとの特徴、有名な一節「一厘の仕組み」、評価や批判などを丁寧に解説します。
広告
日月神示(ひつきしんじ)とは?
日月神示(ひつきしんじ)とは、昭和19年(1944年)6月10日に画家・岡本天明氏が受け取ったとされる「自動書記」による神示(しんじ:神からの言葉)をもとにした文書群です。戦時中の日本において、神道的・古神道的な世界観に基づいて未来の大変革や人類の目覚め、人の在り方などを予言的に記しており、戦後以降も精神世界や宗教に関心のある方々から大きな注目を集め続けています。
ただし、日月神示はあくまでも岡本天明氏が自動書記で書き記したというものであり、それが本当に神からの言葉であるのかは分かりません。日月神示は神道的な観点や日本神話に基づくような記載も多く、予言的な要素も含み興味を掻き立てる内容ではありますが、1つの考え方や説として捉える方が良いでしょう。
|
|
広告
岡本天明の自動書記
岡本天明氏はもともと宗教とは無縁の画家でしたが、ある日、突然手が勝手に動き出し、筆を使って神の言葉を書き綴るようになったとされています。この現象は「自動書記(オートライティング)」と呼ばれており、彼が書いた文書には、国常立尊(くにのとこたちのみこと)という神格をはじめとした、数々の神々が登場します。特に「大建て替え」「大立て直し」など、人類社会の大転換を予告するような内容が多く含まれており、一部の読者には終末論や予言書としても受け止められています。
広告
日月神示の構成
日月神示は全38巻(または40巻とも)から構成されており、それぞれに異なるタイトルが付けられています。たとえば、最初に示された「上つ巻」は「日の出の巻」とも呼ばれ、続いて「磐戸の巻」「夜明けの巻」「黄金の巻」「天つ巻」などが編まれています。これらは、戦争や大災害、人々の価値観の崩壊と再構築など、壮大な人類史の転換点を象徴的に描いた内容となっています。各巻ごとに文体やテーマが異なり、簡潔な口調で教訓的に語るものもあれば、難解な言い回しで深い洞察を促す巻もあります。
広告
有名な一節として、「一厘の仕組み」
とりわけ有名な一節として、「一厘の仕組み」という言葉があります。この言葉は「磐戸の巻」(第19巻)など複数の巻に登場し、とくに有名な一節としては以下のような原文があります。
原文(『磐戸の巻』より)
九分九厘までは、神でも仏でも分かるが、残る一厘は神にも仏にも分からぬ仕組みぞ。
この一厘の仕組みが成就する時、世は立て替えられるぞ。
現代語訳・解説
「九分九厘(くぶくりん)」、すなわち99.9%の仕組みは神仏であっても把握できるが、最後の0.1%である一厘は、あらゆる存在を超えた神の中の神のみが知る究極の仕掛けである、という意味です。
この一厘が発動することで、世界は根本的に立て替えられ、新たな秩序が始まるとされています。
ここで語られている「一厘の仕組み」は、すべての人間の知恵、予言、予測、さらには高次の霊的存在すらも把握しえない神の最終手段であり、それが明かされる時には、「まさか」「ありえない」と思っていた形で、世の中が大きく転換するというメッセージが込められています。
『磐戸の巻』全体は、古事記や日本神話の「天岩戸神話」に通じる文脈を持ち、「神が再びこの世に現れ、人々が目覚める時が来る」と繰り返し語られています。
この中で「一厘の仕組み」は、世の立て替えの鍵であり、人々の目覚めの引き金とも言える存在として象徴的に置かれています。
また、神示では「九分九厘までは悪の仕組みで進められる」という表現もあるため、「一厘」は光の側、すなわち真の神の側の反転・逆転の仕組みとも理解されています。
広告
日月神示全38巻(全40巻)のタイトルと内容
日月神示は、一般に全38巻あるとされますが、補巻や関連資料も含めて全40巻とする場合もあります。それぞれの巻には個別のタイトルがあり、独自の内容やテーマが込められています。以下に、巻名(別名含む)・順番・主な内容の要約を一覧表にまとめました。
| 巻数 | 巻名(別名) | 主な内容の要約 |
|---|---|---|
| 第1巻 | 上つ巻(日の出の巻) | 最初に示された神示。国常立尊による神の言葉が記され、神世の立て直しの必要性を説く。人心の乱れへの警告。 |
| 第2巻 | 下つ巻 | 神の仕組みの一部が語られる。神の働きと人間の在り方、誠の重要性について述べられる。 |
| 第3巻 | 富士の巻 | 富士山が重要な神の座であることが示され、霊的中心としての日本と富士の役割に触れる。 |
| 第4巻 | 月光の巻 | 月の象徴性や陰の働き、神の計らいの微細さ、天と地の調和について語られる。 |
| 第5巻 | 黒鉄の巻 | 物質文明の行き詰まりを示唆し、霊的再生の必要性を強調。物と心の調和が主題。 |
| 第6巻 | 白銀の巻 | 善と悪の転換、陰陽の統一。清く正しく生きることの大切さを説く。 |
| 第7巻 | 黄金の巻 | 黄金とは霊性を意味し、金銭の象徴ではない。霊的価値の転換を呼びかける。 |
| 第8巻 | 天つ巻 | 天上の神の意志と、その地上への反映について説く。神の法則を学ぶべきとされる。 |
| 第9巻 | 地つ巻 | 地の働き、人間生活の基礎、自然との調和について述べられる。 |
| 第10巻 | 日の出の巻(再掲) | 神の世の幕開けの比喩。新たな時代の到来と人類の目覚めを促す。 |
| 第11巻 | 春の巻 | 春は復活と再生の象徴。大建て替えの始まりとしての春の精神性を表す。 |
| 第12巻 | 夏の巻 | 夏は浄化と成長の時期。情熱や行動の方向性が試されることが語られる。 |
| 第13巻 | 秋の巻 | 実りと収穫の時期。人々の行動や信仰の成果が試される。反省と収束の象徴。 |
| 第14巻 | 冬の巻 | 冬は忍耐と試練の象徴。混乱の中でも信仰と行動を保つことの重要性を示す。 |
| 第15巻 | 光の巻 | 神の光とは何か、霊的覚醒、神の意識との一体化をめざす道を説く。 |
| 第16巻 | 火の巻 | 浄化と変革の象徴である火。災いや怒りではなく、魂の浄化手段として語られる。 |
| 第17巻 | 水の巻 | 柔軟さ、受容、流動性といった水の精神を通じて生きる術が示される。 |
| 第18巻 | 風の巻 | 風は目に見えぬ力の象徴。見えぬ神の働き、変化への対応を説く。 |
| 第19巻 | 磐戸の巻 | 天岩戸神話との関連をもち、神の再臨と人々の目覚めの時を象徴する。 |
| 第20巻 | 夜明けの巻 | 闇の時代の終わりと、新しい世界の到来を予告。夜明けは神世の夜明けでもある。 |
| 第21巻 | 雨の巻 | 雨は浄化、癒やし、恵みの象徴。人々の心の潤い、情けの精神を表現。 |
| 第22巻 | 雷の巻 | 天からの警告、目覚めの雷。恐怖でなく、方向転換の合図としての雷を語る。 |
| 第23巻 | 白光の巻 | すべてを包み込む神の光の象徴。大調和と霊性の到達点を意味する巻。 |
| 第24巻 | 八咫の巻 | 八咫鏡など三種の神器との関係を含意。真理を映す鏡のごとき生き方を促す。 |
| 第25巻 | 真中の巻 | すべての中心、「まこと」の心を保ち、極端に走らぬように戒める。 |
| 第26巻 | 海の巻 | 海のように包み込む神の心。境界を越えてすべてを受け入れる包容の精神を説く。 |
| 第27巻 | 山の巻 | 山は不動の信仰、根本の教えの象徴。霊的中心地としての山の意味も。 |
| 第28巻 | 星の巻 | 星は神の導き。見えない世界の秩序と運命、宇宙的視点からの神の言葉。 |
| 第29巻 | 龍の巻 | 龍は神の使い。力強さと変化の象徴。霊的覚醒の背後にある原動力を示す。 |
| 第30巻 | 鳳の巻 | 鳳凰は霊的再生と調和の象徴。火を超えて再生する魂の象徴的存在。 |
| 第31巻 | 鳴門の巻 | 渦巻く混乱と秩序。善悪混在の中で中心を見失わぬことの大切さを語る。 |
| 第32巻 | 鏡の巻 | 自らを映し、自らを省みること。神の鏡としての心の在り方を説く。 |
| 第33巻 | 神の巻 | 神の本質や姿、神と人の関係について深く掘り下げる巻。 |
| 第34巻 | 人の巻 | 人間の使命、自由意思、業と報い、神の子としての役割を強調する。 |
| 第35巻 | 根の巻 | 根源の神・国常立尊の働き。宇宙創造と地球再生の根本的な視点が語られる。 |
| 第36巻 | 枝の巻 | 根から枝へ。神の教えが人々の行いとなって広がる様子を示す。 |
| 第37巻 | 花の巻 | 神の意志が花開く時代。信仰と実践が人間社会に実を結ぶことを象徴。 |
| 第38巻 | 実の巻 | 教えの成果としての「実り」。人々の行動と信仰の結晶として語られる。 |
| 第39巻 | 補巻①(未定稿含む) | 一部未完または口伝とされる内容。神示の補足的教えや実践編的要素。 |
| 第40巻 | 補巻②(随時追加) | 岡本天明の手記や、後に判明した断片的神示をまとめた補遺的資料。 |
これらの巻はすべて一貫した「神の国づくり」「霊的再生」「大建て替え」を軸に展開されており、各巻がまるで一つのストーリーのように補い合う構造を持っています。
広告
日月神示と信仰・宗教
日月神示と関係の深い信仰団体としては、「大本(おおもと)」の流れを汲むグループや、岡本天明氏が関わった「日の出の会」などが挙げられます。また、出口王仁三郎や中矢伸一氏といった人物を介して、日月神示はスピリチュアルやニューエイジ運動にも影響を与えてきました。一方で、戦後の宗教ブームのなかで、終末思想や予言を過度に信じる姿勢に対しては、学術的・社会的観点からの批判もあります。たとえば、科学的根拠のない未来予測や、人々の不安を煽る言説については慎重な取り扱いが求められてきました。
研究者の間でも日月神示への評価は分かれています。一部の宗教学者は、近代日本における新宗教や神秘主義運動の一例としてその文化的・歴史的意義を認めており、また、戦時中という極限状態で生まれた宗教的表現としての価値を指摘する声もあります。しかし一方で、テキストそのものが断定的で象徴的な表現に満ちており、検証可能性に乏しいことから、学問的には扱いづらい文書と見なされることも少なくありません。
広告
まとめ
日月神示は、一見難解でとっつきにくい文章ですが、読み進めるうちに、現代社会の価値観や生き方への問いかけ、精神の浄化を促すような力を持っていると感じる方も多いようです。信仰や解釈には慎重さが求められますが、昭和から令和にかけてなお読み継がれているという事実そのものが、日月神示という存在の大きさを物語っているのかもしれません。
国常立尊という神様は日本神話にも登場しますが、宇宙の根源、創造神として謎に包まれた神様です。神社でも国常立尊をお祀りしている神社もたくさんあります。そのような背景もあり、新興宗教や神道から派生した信仰などでは、国常立尊からの神示や言葉をおろして信者に伝えるという形式がたびたび行われてきました。人間に神がかりして、神様の言葉を伝える時には、審神者(さにわ)という真偽を確かめたり解釈したりする人がついて慎重に判定していましたが、神道の知識をもってしても、抽象的な創造神なので、真偽を確認しにくい神様でもあります。
日月神示に記された内容が全て正しく正確であるとは考えず、一つの考え方や一説としてとらえ、自分で考えていきましょう。
|
|