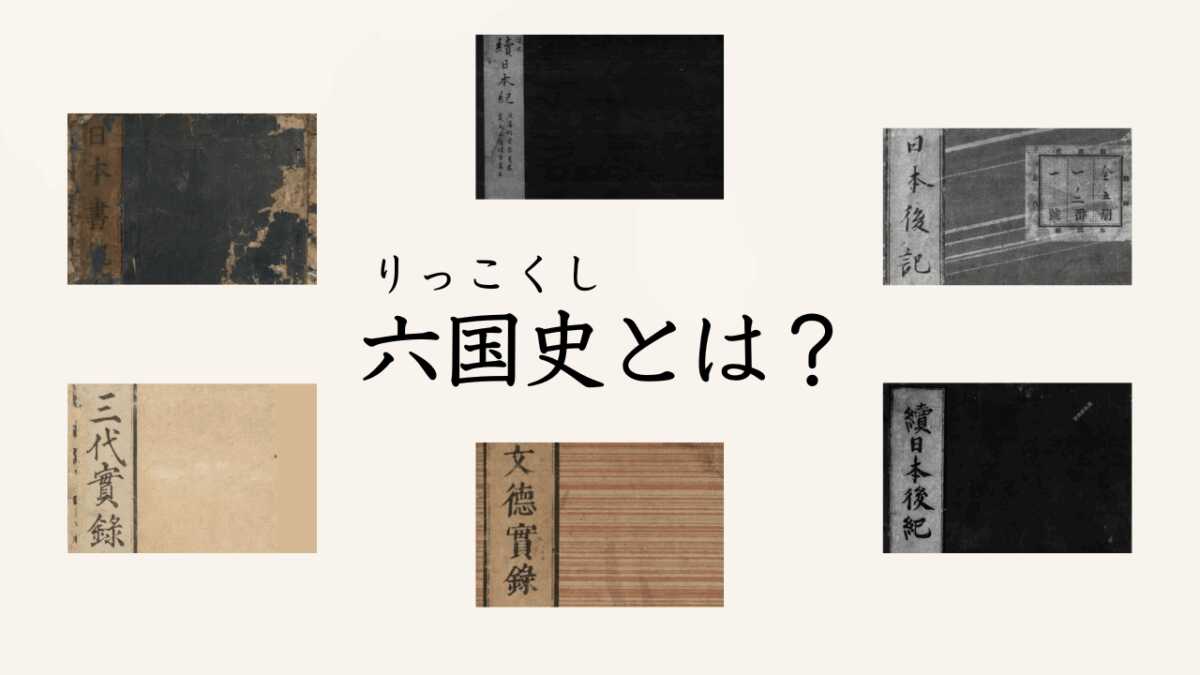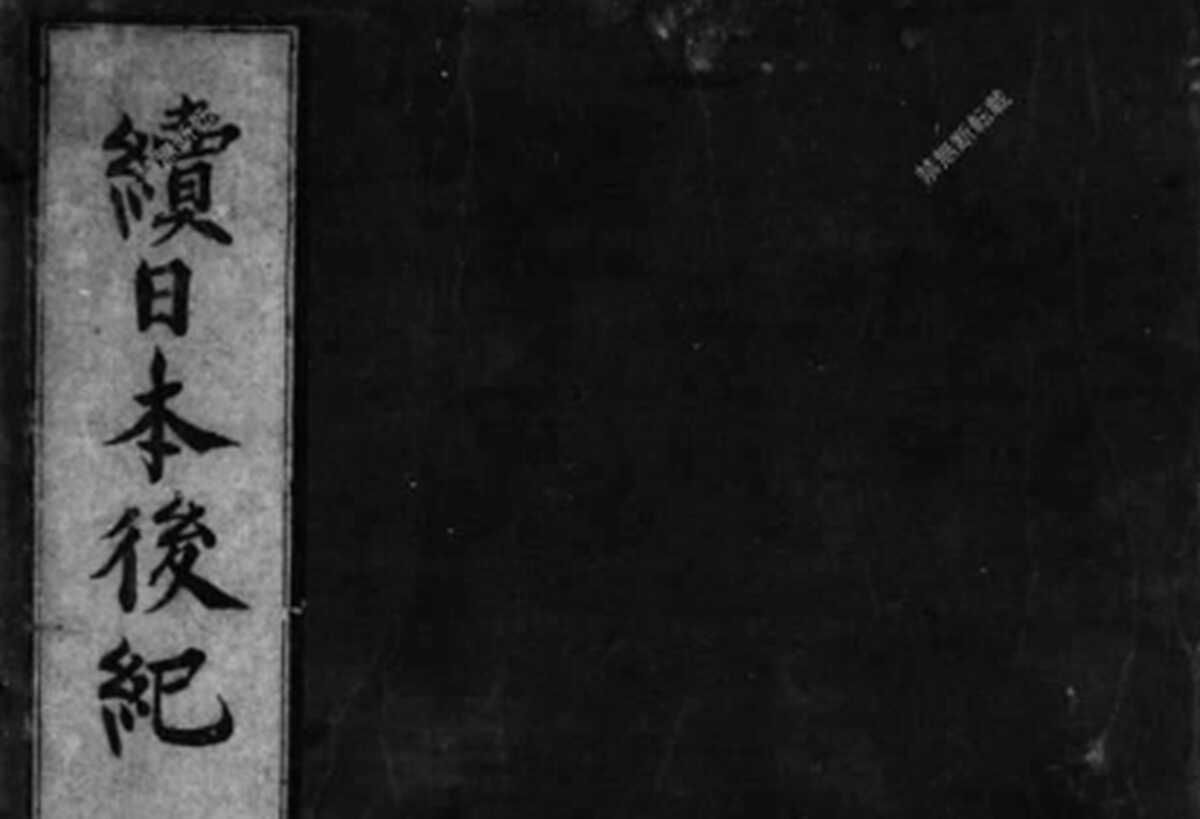
『続日本後紀(しょくにほんこうき)』は、六国史の第四にあたる勅撰国史で、仁明天皇の即位(833年)から文徳天皇の治世末(850年)まで、およそ17年間を記録した歴史書です。全20巻からなり、平安時代前期の政治や社会を知る上で重要な史料とされています。本記事では、『続日本後紀』の編纂背景や記録されている内容、具体的な原文と現代語訳を示しながら、その特徴をわかりやすく解説します。
広告
続日本後紀の編纂と背景
『続日本後紀』は、869年に完成しました。編纂にあたったのは藤原良相や藤原基経をはじめとする藤原北家の人々で、文体は中国の史書に倣った漢文体です。六国史の流れの中でも、藤原氏が大きな政治力を発揮し始めた時期に編纂されたため、その影響が反映されていると考えられています。
また、この時期は律令国家の制度疲労が見え始め、財政難や地方の混乱が深刻化していました。『続日本後紀』は、そうした中で中央貴族の権力構造や政争の動向を色濃く描き出す歴史書となっています。
六国史(りっこくし)とは?
六国史(りっこくし)とは、奈良時代から平安時代にかけて編纂された日本の正史(勅撰国史書)の総称です。『日本書紀』から『日本三代実録』までの6つの歴史書を指し、天皇の命によって国家事業として編まれました。中国の正史を手本にしながら、日本独自の歴史叙述を確立した六国史は、当時の政治・社会・文化を知るうえで欠かせない史料となっています。
六国史は以下の6つで構成されており、それぞれ扱う時代が異なります。
| 国史名 | 編纂年代 | 内容の対象時期 | 時代区分 |
|---|---|---|---|
| 日本書紀 | 720年 | 神代~持統天皇(697年) | 奈良時代初期に編纂、神話から律令国家成立まで |
| 続日本紀 | 797年 | 文武天皇(697年)~桓武天皇(791年) | 奈良時代全般 |
| 日本後紀 | 840年 | 桓武天皇(781年)~淳和天皇(833年) | 奈良後期~平安初期 |
| 続日本後紀 | 869年 | 仁明天皇(833年)~文徳天皇(850年) | 平安時代前期 |
| 日本文徳天皇実録 (日本文徳天皇實録) |
879年 | 文徳天皇(850年~858年) | 平安時代前期 |
| 日本三代実録 (日本三代實録) |
901年 | 清和天皇(858年)~光孝・宇多・醍醐天皇(887年) | 平安時代前期 |
広告
記録されている時代の流れ
『続日本後紀』が対象とする時代は、嵯峨・淳和天皇の時代を経て、仁明・文徳両天皇の治世にあたります。律令制の運営に限界が見え、政治が貴族社会の内部抗争に大きく左右されたことが特徴です。
| 天皇 | 在位期間 | 主な出来事 |
|---|---|---|
| 仁明天皇 | 833~850年 | 承和の変(842年)、藤原良房の台頭 |
| 文徳天皇 | 850~858年(本書は850年まで) | 藤原良房の摂関体制への布石、藤原氏勢力拡大 |
広告
続日本後紀に見える出来事
承和の変
『続日本後紀』で最も注目される記録の一つが、842年の承和の変です。嵯峨上皇・仁明天皇の後継をめぐる政争の中で、藤原良房が橘逸勢や伴健岑らを失脚させ、皇太子恒貞親王を退けて文徳天皇の皇子道康親王(のちの清和天皇)を皇太子に立てました。これは藤原北家による摂関政治の基盤を築く重要な転機となりました。
災異や社会状況
この時代も天災や疫病が相次ぎ、『続日本後紀』には飢饉や地震、疫病の流行に関する記録が散見されます。政治と自然現象の関係を強調することで、天皇の統治が天の意思に左右されるという古代的な世界観が読み取れます。
広告
原文・書き下し・現代語訳の例
原文(漢文)
「承和九年六月、廃皇太子恒貞親王。」
書き下し文
「承和九年六月、皇太子恒貞親王を廃す。」
現代語訳
「承和9年(842年)6月、皇太子の恒貞親王が廃された。」
この簡潔な記述は、承和の変を示す核心部分です。実際には前後の記録に詳細な経緯が記されており、藤原良房の権力拡大が如実にうかがえます。
広告
続日本後紀の特徴
『続日本後紀』は、国家の正史であると同時に、藤原氏の台頭を背景にした政治的意図が強く反映されている史書です。客観性に限界がある一方で、当時の政争や権力構造を理解する上で欠かせない資料でもあります。加えて、災害や疫病の記録、律令制の運営状況を示す記事も含まれており、政治史だけでなく社会史・文化史の研究にとっても重要な意味を持っています。
広告
まとめ
『続日本後紀』は、平安時代前期の仁明天皇から文徳天皇に至る時代を記録した六国史の第四の正史です。承和の変をはじめとする政争の記録、災異や社会不安の描写を通じて、律令国家の転換期を理解する上で不可欠な史料といえます。原文に触れることで、当時の政治的緊張と社会の不安が生々しく伝わってきます。