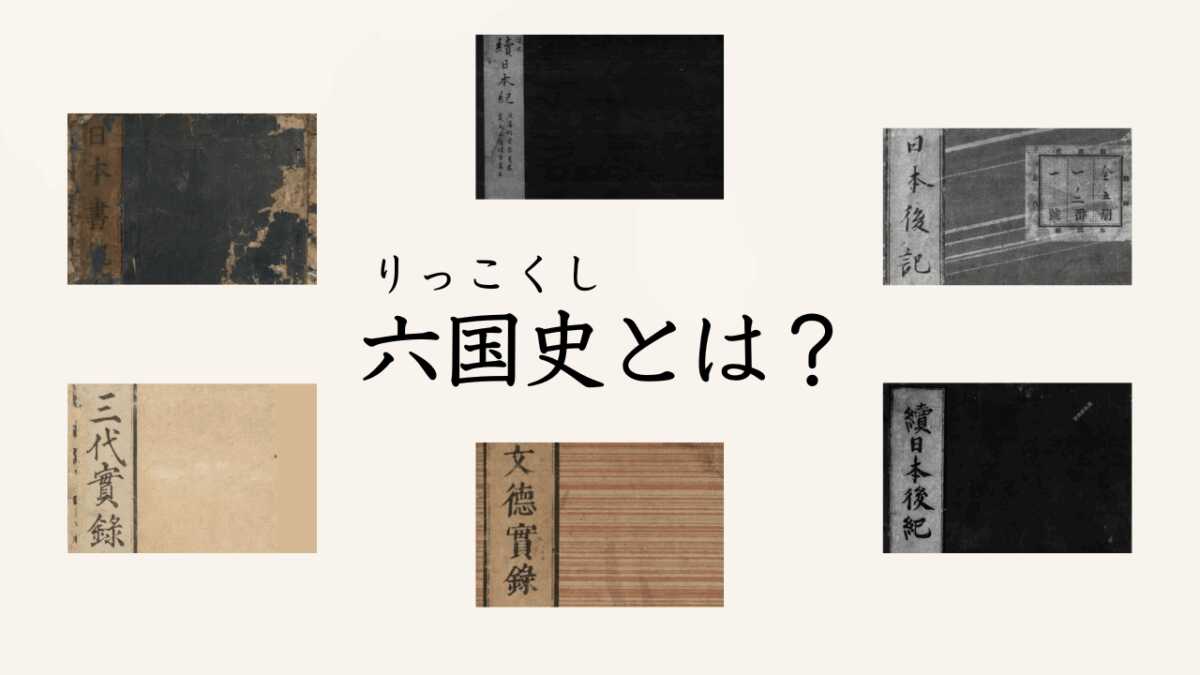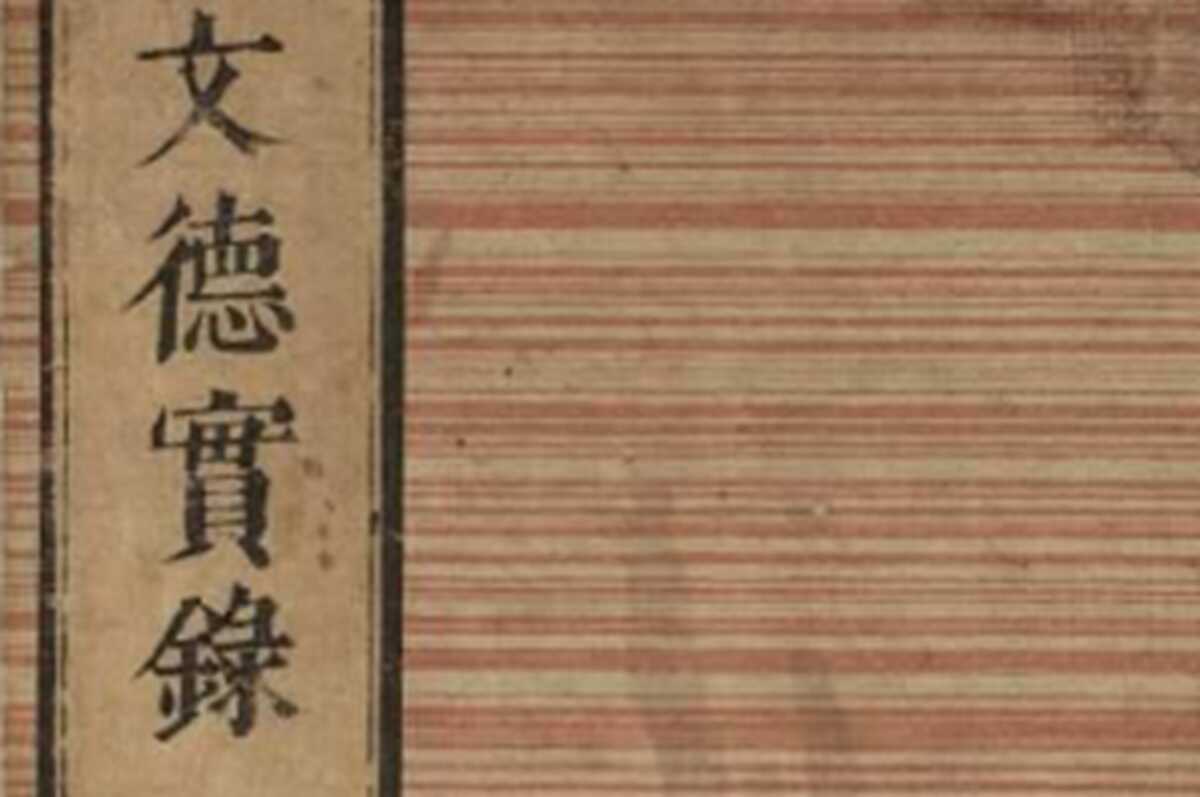
『日本文徳天皇実録(にほんもんとくてんのうじつろく)』は、六国史の第五にあたる勅撰国史です。文徳天皇の在位期間に特化して記録されたもので、全10巻から成り、文徳天皇一代(850~858年)の政治・社会・宗教などを中心にまとめられています。六国史の中で最初に「一代一紀」の形式をとった歴史書であり、天皇一代を記録する「実録」として後の国史編纂の基盤を築きました。本記事では、この歴史書の編纂背景や内容、さらに原文と現代語訳を交えて、その特徴をわかりやすく解説します。
広告
日本文徳天皇実録の編纂の背景と成立
『日本文徳天皇実録』は、879年に完成しました。編纂に関与したのは藤原基経ら当時の有力貴族であり、藤原北家が摂関政治を固める途上にありました。漢文体で記され、中国の「実録」に倣いながらも、日本独自の政治史観が表れています。六国史の中では唯一、文徳天皇の在位期間に限定されている点が最大の特徴です。
六国史(りっこくし)とは?
六国史(りっこくし)とは、奈良時代から平安時代にかけて編纂された日本の正史(勅撰国史書)の総称です。『日本書紀』から『日本三代実録』までの6つの歴史書を指し、天皇の命によって国家事業として編まれました。中国の正史を手本にしながら、日本独自の歴史叙述を確立した六国史は、当時の政治・社会・文化を知るうえで欠かせない史料となっています。
六国史は以下の6つで構成されており、それぞれ扱う時代が異なります。
| 国史名 | 編纂年代 | 内容の対象時期 | 時代区分 |
|---|---|---|---|
| 日本書紀 | 720年 | 神代~持統天皇(697年) | 奈良時代初期に編纂、神話から律令国家成立まで |
| 続日本紀 | 797年 | 文武天皇(697年)~桓武天皇(791年) | 奈良時代全般 |
| 日本後紀 | 840年 | 桓武天皇(781年)~淳和天皇(833年) | 奈良後期~平安初期 |
| 続日本後紀 | 869年 | 仁明天皇(833年)~文徳天皇(850年) | 平安時代前期 |
| 日本文徳天皇実録 (日本文徳天皇實録) |
879年 | 文徳天皇(850年~858年) | 平安時代前期 |
| 日本三代実録 (日本三代實録) |
901年 | 清和天皇(858年)~光孝・宇多・醍醐天皇(887年) | 平安時代前期 |
広告
日本文徳天皇実録に記録されている時代の流れ
『日本文徳天皇実録』が対象とするのは、文徳天皇のわずか8年間の治世です。しかし、その短い期間の中で、皇位継承をめぐる問題や藤原氏の権力拡大など、後の平安政治に直結する出来事が多く記録されています。
| 天皇 | 在位期間 | 主な出来事 |
|---|---|---|
| 文徳天皇 | 850~858年 | 藤原良房の権力基盤強化、惟仁親王(のちの清和天皇)の立太子、藤原氏の摂関体制への布石 |
広告
日本文徳天皇実録に見える出来事
皇位継承と藤原氏の影響
文徳天皇の后である藤原良房の娘・明子が産んだ惟仁親王が皇太子に立てられ、のちの清和天皇となります。これにより藤原北家の血統が天皇家に深く結びつき、摂関政治の確立へとつながる大きな一歩となりました。
政治と仏教の関係
この時期も仏教は政治と密接に関わっており、国家的な仏教行事や寺院造営の記事が記録されています。文徳天皇自身が仏教を重んじ、国の安泰を祈る姿勢が史書に刻まれています。
広告
原文・書き下し・現代語訳の例
原文(漢文)
「嘉祥三年九月、立皇太子惟仁親王。」
原文は、国書データベースなどで確認できます。
書き下し文
「嘉祥三年九月、皇太子に惟仁親王を立つ。」
現代語訳
「嘉祥3年(850年)9月、惟仁親王が皇太子に立てられた。」
この短い記述に、後の清和天皇即位、さらに藤原氏が外戚として権力を握る契機となる重大な歴史的意味が込められています。
広告
日本文徳天皇実録の特徴
『日本文徳天皇実録』は、六国史の中で初めて天皇一代を対象とする「実録」の形式をとり、以後の正史に大きな影響を与えました。藤原氏の権力上昇を背景にしているため、政治的意図が色濃く反映されていると考えられますが、同時に仏教・儀礼・災害の記録も含まれており、平安前期社会の実態を知る手がかりとなります。
広告
まとめ
『日本文徳天皇実録』は、文徳天皇一代の記録をまとめた六国史の第五であり、平安時代前期の政治と社会を知るための貴重な史料です。特に藤原氏の台頭と皇位継承の動きが詳細に記され、摂関政治の基盤形成を理解する上で欠かせません。原文に触れることで、歴史の転換点を生きた人々の息遣いを感じ取ることができるでしょう。