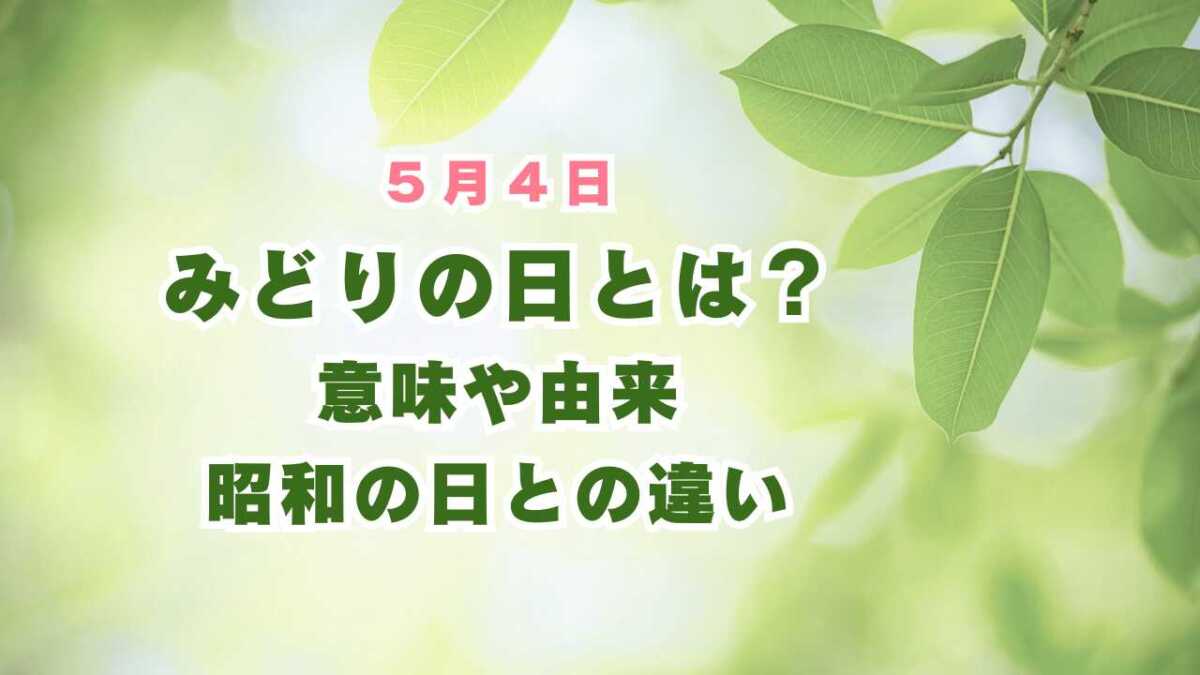
毎年5月4日は「みどりの日」として祝われていますが、かつては昭和天皇の誕生日である4月29日がこの名で親しまれていたことをご存じでしょうか。「みどりの日」は、昭和天皇の自然への関心に由来しながらも、その後の歴史的な経緯により日付と趣旨が変遷してきた特異な祝日です。本記事では、「みどりの日」の成立と変遷をたどりつつ、「昭和の日」との違いやゴールデンウィークにおける役割を詳しく解説し、日本の祝祭日文化の奥深さに迫ります。
広告
みどりの日の由来と昭和の日との違いを歴史的にひもとく
春の大型連休として多くの人に親しまれているゴールデンウィーク。その中でも5月4日の「みどりの日」は、比較的新しい祝日のように思われがちですが、実は日本の近代史や皇室と深く関係する由緒ある日です。もともと4月29日は「みどりの日」として知られていましたが、現在は「昭和の日」とされ、「みどりの日」は5月4日に移動しています。なぜこのような経緯をたどったのでしょうか。本記事では、「みどりの日」の由来と意味、そして「昭和の日」との違いについて詳しく解説しながら、日本の祝日文化の背景にある歴史を紐解きます。
広告
みどりの日の起源とは?昭和天皇の自然への思いから生まれた祝日
「みどりの日」の起源は、昭和天皇の誕生日である4月29日にあります。昭和天皇は1901年4月29日にお生まれになり、戦前・戦中・戦後と激動の時代にわたって在位されました。戦後の日本では天皇の「政治的中立性」が憲法によって定められたこともあり、天皇誕生日をそのまま存続させることには一定の議論がありました。しかし、長年国民に親しまれてきた4月29日をただの平日に戻すことに対しては強い反発があり、象徴的な意味を保ちながらも政治的な色合いを避ける目的で、1989年の昭和天皇崩御後、1990年からこの日が「みどりの日」として新たに祝日に制定されることになりました。
「みどりの日」という名称には、昭和天皇が植物や自然科学に対して深い関心を持っていたことが反映されています。天皇は学者肌の人物として知られ、植物分類学や海洋生物学に造詣が深く、在位中も研究に取り組まれていました。このため、「自然を慈しみ、緑を大切にする日」として、4月29日はみどりの日と名付けられたのです。
広告
2007年に変更された「みどりの日」と「昭和の日」
しかし、平成も時代を重ねるにつれ、昭和という時代の歴史的評価や記憶を次世代に伝える必要性が強く意識されるようになりました。2005年に祝日法が改正され、2007年から4月29日は「昭和の日」として新たに定められ、これまで「みどりの日」とされていた祝日は5月4日に移されることとなったのです。
「昭和の日」は、「激動の日々を経て、日本の復興を成し遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」ことを趣旨として掲げています。これは単なる天皇誕生日の再評価ではなく、昭和という歴史的時代区分そのものの記憶を国民的に共有し、後世に語り継ぐ日として位置づけられているのです。
一方、5月4日に移った「みどりの日」は、もともと祝日法で「祝日と祝日に挟まれた平日は国民の休日とする」とされていたことから、長らく「国民の休日」として扱われていました。そこに新たに「自然に親しむ日」という意味づけを持たせて「みどりの日」としたことで、祝日としての意義が明確化されるとともに、ゴールデンウィーク全体の構成もより連続性を持つものとなりました。
広告
みどりの日と昭和の日の違い
同じく4月29日を起点とするこの2つの祝日は、もとは同じ日を起源としながらも、その趣旨には明確な違いがあります。「昭和の日」は、昭和という時代全体を振り返り、その教訓と記憶を国民的に考察する日です。戦争と復興、経済成長と公害など、さまざまな課題を乗り越えてきた昭和の歩みを振り返ることに主眼が置かれています。
一方で、「みどりの日」は、政治的・歴史的文脈を避けて、自然への関心や生命の尊さ、環境保全への意識を高めることを目的とした祝日です。現在の日本社会においても環境問題への関心は高まっており、「みどりの日」は単なる休日ではなく、持続可能な社会づくりを考える象徴的な日にもなりつつあります。
広告
ゴールデンウィークに見る日本の祝日文化
「みどりの日」と「昭和の日」は、どちらも春の連休であるゴールデンウィークを構成する重要な日ですが、それぞれ異なる由来と意味を持っています。加えて、5月3日の「憲法記念日」、5月5日の「こどもの日」と並び、日本の祝日文化の豊かさを物語る存在でもあります。
この連休期間は、ただの休暇として楽しむだけでなく、日本の歴史や自然、文化に思いを馳せる時間として活用することで、祝日の本来の意味をより深く感じ取ることができるでしょう。
広告
おわりに
「みどりの日」は、もともと昭和天皇の誕生日であった4月29日に由来し、天皇の自然への関心から命名された祝日です。その後、「昭和の日」が設けられたことで、みどりの日は5月4日に移動しましたが、その本質は変わることなく、自然への感謝と共生の精神を象徴する日として、現在も大切にされています。祝日の背景にある歴史と意味を知ることで、私たちはより豊かにこの日を過ごすことができるはずです。





