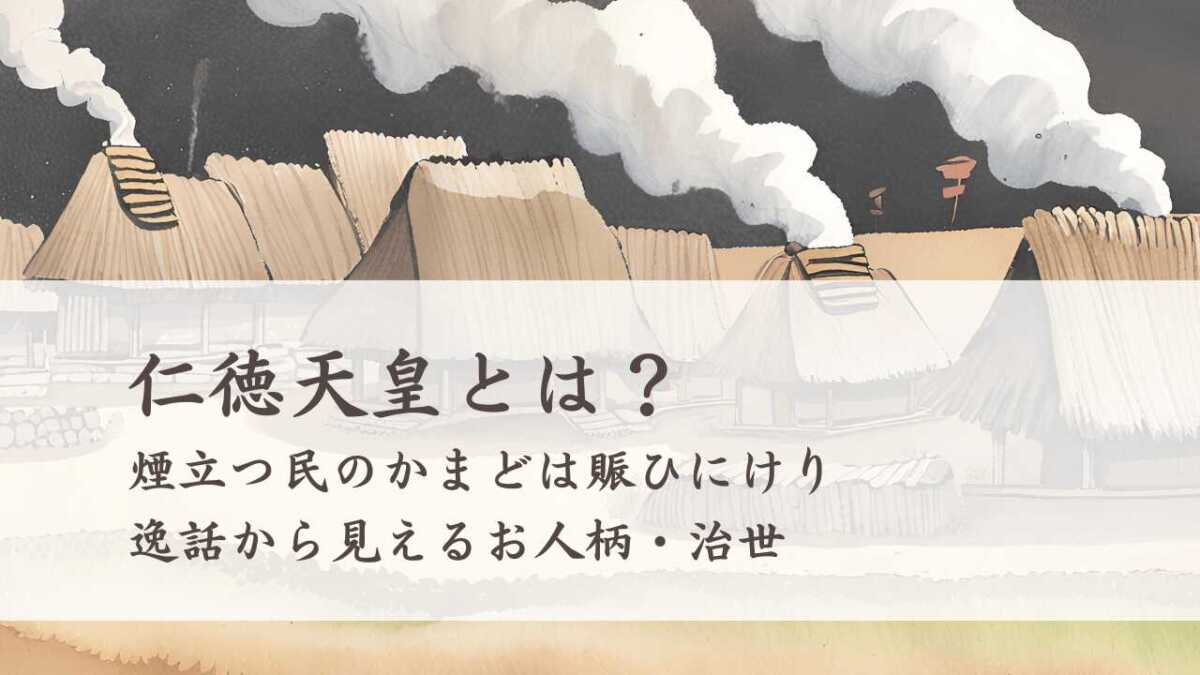『呪術廻戦』の最強の呪いとして描かれる「両面宿儺(りょうめんすくな)」は、虚構だけの怪物ではありません。
古代史料『日本書紀』には、2つの顔と四本の腕を持つ異形の「宿儺」が、王権に背く凶賊として討たれたと記されています。一方で飛騨・美濃の在地伝承や寺院縁起は、宿儺を悪龍退治や開発・教化に尽くした英雄、あるいは宗教的権威として語り継いできました。2つの面をもつ宿儺は、ヤマト王権の編纂意図と地域社会の記憶という異なる見方が同一の人物像を映し出した結果でもあります。
奇形を思わせる身体描写は字義通りの記録なのか、それとも異端の首長を「異形化」する政治的なものなのか。史料批判と造形・縁起の検討を重ねることで、宿儺は怪奇談の登場人物ではなく、実在した可能性を帯びてきます。
この記事では、正史と地方伝承、そして現代ポップカルチャーの交差点に立ち、宿儺とは何者だったのかを学術的関心に基づいて読み解いていきます。呪術廻戦ファンの方も、日本の歴史に重ねて読むとまた新しい発見や好奇心がわくのではないかと思います。
広告
日本書紀に記された宿儺の姿
日本書紀には、仁徳天皇の時代の記事として宿儺の名が登場します。そこでは顔が二つ、腕が四本という異形の姿が描かれ、朝廷の命に従わない凶賊として討伐されたと記されています。この描写は当時の政治的文脈のなかで、中央の秩序に背く在地勢力を強く退けるための表現であった可能性があります。つまり、日本書紀の宿儺像は、王権を正当化する語りの中で生まれた厳しい評価であると考えられます。
日本書紀での宿儺の記述
六十五年 飛騨國有一人 曰宿儺 其爲人 壹體有兩面 面各相背 頂合無項 各有手足 其有膝而無膕踵 力多以輕捷 左右佩劒 四手並用弓矢 是以 不随皇命 掠略人民爲樂 於是 遣和珥臣祖難波根子武振熊而誅之
現代語訳
六十五年、飛騨国にひとりの人がいた。宿儺という。一つの胴体に二つの顔があり、それぞれ反対側を向いていた。頭頂は合してうなじがなく、胴体のそれぞれに手足があり、膝はあるがひかがみと踵がなかった。力強く軽捷(けいしょう)で、左右に剣を帯び、四つの手で二張りの弓矢を用いた。そこで皇命(すめらみこと)に従わず、人民から略奪することを楽しんでいた。それゆえ和珥臣(わにうじ)の祖、難波根子武振熊(なにわのねこたけふるくま)を遣わしてこれを誅した。
広告
飛騨や美濃に残るもう一つの宿儺
一方で、飛騨高山や美濃地方に伝わる両面宿儺(りょうめんすくな)のイメージは大きく異なります。宿儺は、悪龍を退治したり、農耕や用水の整備に尽力したり、社寺の建立に関わったりした人物として、地域の恩人のように語られてきました。寺院縁起や土地の物語では、宿儺は観音などの尊格と結び付けられることもあり、霊験を持つ存在として敬われています。ここでは、異形というよりも、地域を導いたリーダーや聖的な人物としての側面が前面に出ています。
広告
二面四臂の造形と奇形説の受け止め方
宿儺の2つの顔や4本の腕、踵がないといった具体的な身体描写から、奇形であった可能性を指摘する見解もあります。
ただし、古代の文献における「異形」は、実際の身体の特徴をそのまま写しただけではなく、畏敬や恐れ、超人的な力を象徴的に表すための表現でもありました。王権に従わないその土地の長を異形として描くことは、政治的なメッセージを強める効果を持ちます。他方、地域の造形や縁起では、その異形性が聖性のしるしとして受け止められ、木彫像や仏像風の表現に引き継がれてきました。
広告
宿儺は実在した人物だった可能性
史料の性格を踏まえると、宿儺が実在した人物であった可能性は十分に考えられます。
地域社会の基盤整備や祭祀を担った長が、中央の記録では反逆者として、地域の記憶では恩人として語られることは珍しくありません。日本書紀の厳しい評価と、飛騨や美濃の称揚的な伝承は、同じ人物を異なる立場から記述した結果とみなすことができます。そう考えると、宿儺は古代飛騨周辺で影響力を持った在地豪族、あるいは宗教的リーダーであったという像が浮かび上がります。
広告
呪術廻戦での両面宿儺
『呪術廻戦』に登場する両面宿儺は、名と象徴的な造形を伝承から取り入れたキャラクターです。作品の宿儺はフィクションとして独自に再構成されていますが、二面四臂という強烈なモチーフが古代から受け継がれ、現代の物語世界で新しい意味を与えられている点は興味深いところです。
宿儺の伝承における、朝廷に逆らった者という異端や荒々しさ、怪物か妖怪かを思わせるキャラ設定、何かを守っている守護神的な雰囲気と、それらを封じ込めた呪術などが、日本人の感性としてちょうどはまり受け入れられたと考えられます。
宿儺を理解するうえでは、まず日本書紀という正史の性格を踏まえ、政治的編集の可能性を考えることが大切です。次に、寺院縁起や地域の伝承が後世の信仰や地域振興の文脈で整えられてきたことにも注意します。造形資料や地名、祭礼の伝承など、多様な証拠をつなぎ合わせることで、宿儺という存在が単純な怪人でも完全な虚構でもなく、歴史の層を重ねて形成された複合的な人物像であることが見えてきます。
広告
まとめ
宿儺は、日本書紀では反逆の異形として、飛騨や美濃の伝承では地域を導く英雄として描かれてきました。二つの像は対立しているように見えますが、視点を変えると同じ人物に対する評価の違いとも受け取れます。二面四臂という強烈な造形は、奇形を示す可能性と同時に象徴表現としての意味も帯び、後世の信仰や造像、そして現代のエンターテインメントにまで連なっています。史料をていねいに読み比べることで、宿儺は古代の地域社会に生きたリーダー像として、より立体的に理解できるようになります。