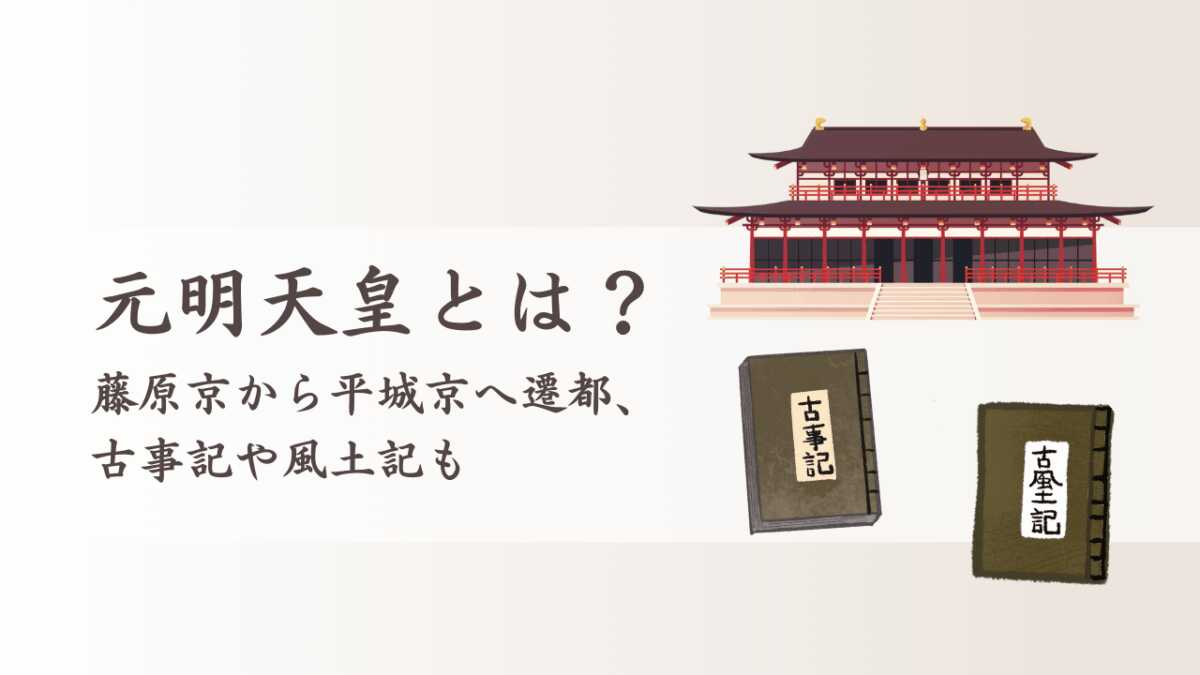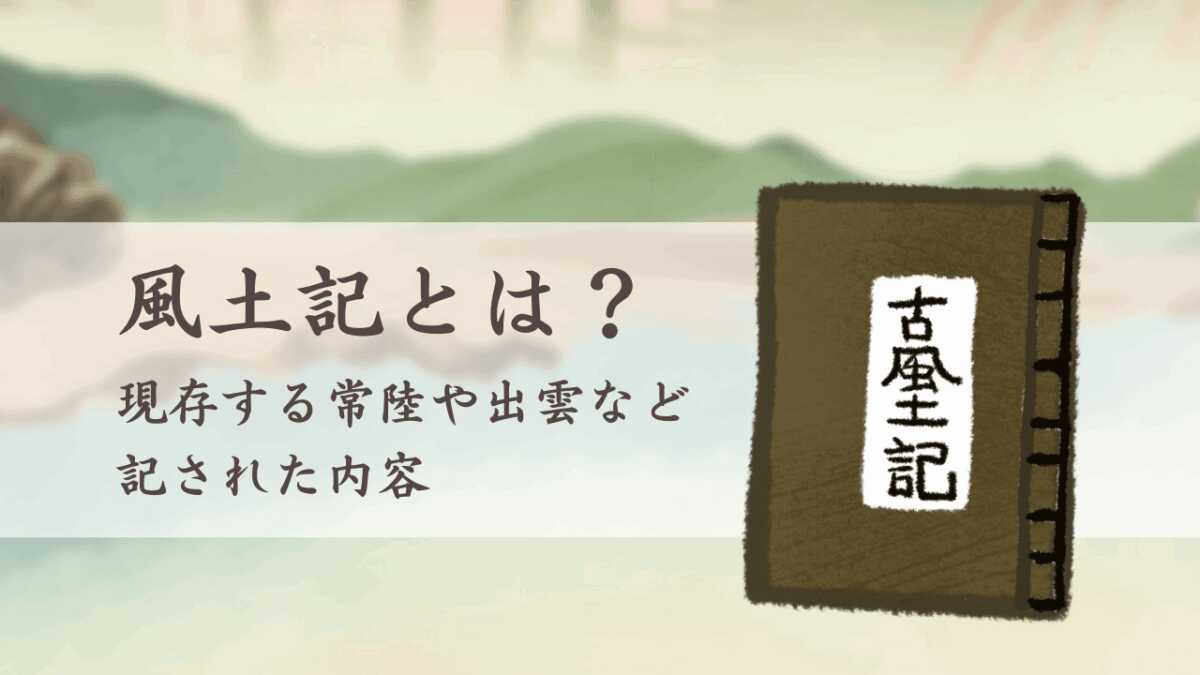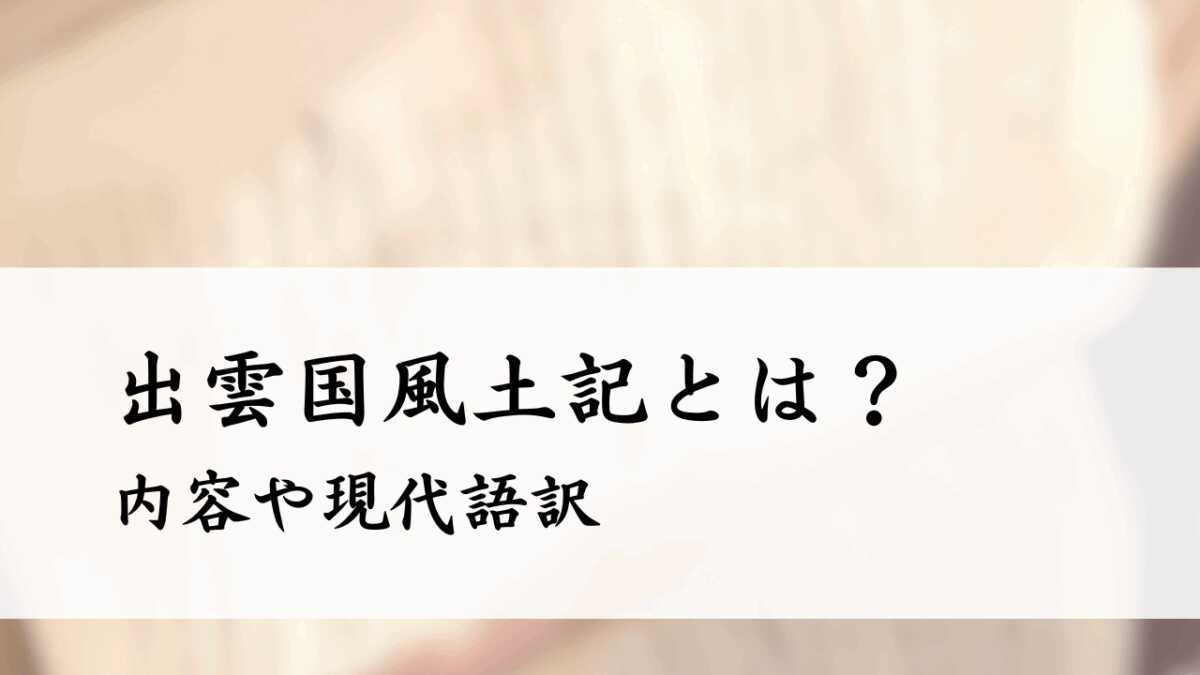
『出雲国風土記』は、奈良時代に編纂された日本最古の地方地誌の一つであり、現存する風土記の中で唯一、ほぼ完全な形で残されている貴重な史料です。神話の国・出雲の地における地名の由来や産物、神々の伝承が記され、中央とは異なる地域の視点で描かれた「もうひとつの日本神話」とも言えます。本記事では、『出雲国風土記』の成立背景や構成、原文の抜粋とその現代語訳を通して、古代出雲の世界観に迫ります。
広告
風土記とは何か?編纂の目的と背景
風土記が編纂されたのは、和銅6年(西暦713年)、元明天皇の勅命によるものでした。この頃はちょうど飛鳥時代か奈良時代に移行する時期で、元明天皇は藤原京にあった都を平城京に遷都し、世の中も大きく変わる時でした。
元明天皇は全国に風土記撰進の詔を発し、各国の風俗や地理をまとめ、提出するよう命じました。風土記は後に平安時代に「風土記」と称されるようになったと考えられています。
この命令では、各国の国司に対して、郡名の由来や土地の特徴、産物、伝承などを記録して朝廷に提出するよう求められました。その背景には、大宝律令による中央集権的な支配体制の整備が進む中で、地方の実情を把握し統治に役立てる意図があったとされています。また、土地の神話や信仰に関する記録は、律令国家の正当性を支える思想的基盤としても重視されていました。
風土記は、単なる地誌にとどまらず、地名の由来に関する神話や説話を豊富に含んでおり、地域視点の歴史叙述として高く評価されています。
広告
出雲国風土記の成立と特徴
『出雲国風土記』は、元明天皇の勅命により和銅6年(713年)から全国の国ごとに編纂が命じられた風土記のひとつで、完成は天平5年(733年)とされています。編者は出雲守・忌部子首(いんべのこびと おびと)とされており、記録内容は律令制の行政単位に基づいて郡ごとに整理されています。この頃はちょうど飛鳥時代か奈良時代に移行する時期で、元明天皇は藤原京にあった都を平城京に遷都し、世の中も大きく変わる時でした。
この風土記の最大の特徴は、他の風土記が断片しか残っていない中で、本文がほぼ完全な形で現存している点にあります。また、『古事記』や『日本書紀』とは異なり、中央からの視点ではなく、地域住民の語りや伝承が色濃く反映されているのも魅力です。
広告
内容の構成
『出雲国風土記』は、出雲国を構成する以下の五郡を中心に編成されています。
- 意宇郡(おうのこおり)
- 飯石郡(いいしのこおり)
- 出雲郡(いずものこおり)
- 楯縫郡(たてぬいのこおり)
- 島根郡(しまねのこおり)
各郡ごとに、地名の由来、神話・伝説、神社や祭祀、土地の様子、産物、租税の記録などが詳細に述べられています。中でも注目されるのは、「国引き神話」や「神魂命(かみむすびのみこと)」の伝承など、出雲独自の神々が登場する話が豊富に含まれていることです。
広告
原文と現代語訳の例
国引き神話より
『出雲国風土記』の冒頭には、出雲の土地がいかにして形成されたかを語る有名な「国引き神話」が記されています。その一部を、原文とともに紹介します。
原文
抑(そもそも)出雲國は、古(いにしえ)神代の時、八束水臣津野命(やつかみずおみつぬのみこと)といふ大神の坐(ま)しし時に、國を引き寄せて造らしめき。
現代語訳
そもそも出雲国というのは、遠い昔の神代の時代に、八束水臣津野命という大神がおられ、その神が他の土地を引き寄せて、出雲の国土を造られたものである。
このように、出雲という土地の成り立ちを、「他国から土地を引っ張ってきて国土を広げた」という神話的叙述で語るのが、出雲国風土記の大きな特徴です。
地名の由来
原文(意宇郡の条より)
意宇の郡の名の所以(ゆえ)は、神日本磐余彦尊(かむやまといわれびこのみこと)出雲を巡幸(めぐ)りし時に、「ここは心の意(おも)ふ所なり」と詔(の)らせたまへり。
現代語訳
意宇郡の名の由来は、神武天皇が出雲を巡られたときに、「ここは私の心の思いにかなう地だ」とおっしゃったことにちなむ。
このように、地名の由来が神の言葉や天皇の意志によって説明されている点は、風土記全体を通してよく見られる特徴であり、当時の土地観・国土観のあり方を伝えてくれます。
出雲郡・熊野神社に関する記述
原文
熊野大神坐(いま)す社、熊成峯にあり。昔、熊野大神の命、熊成の峯に天降り坐しき。ゆゑに社を立てて祭るなり。
現代語訳
熊野大神がおられる社は、熊成峯という山の上にあります。昔、熊野大神の命がこの山に天から降りて来られたと伝えられ、それゆえにここに社を建てて祀っているのです。
このように、神社の創建理由も「天降り=天からの降臨」という神話的背景をもって語られています。地形と神話が一体化した記述は、出雲国風土記の魅力のひとつです。
島根郡・島根という地名の由来
原文
島根の郡、名の所以(ゆゑ)は、神代の時、神の坐(いま)しし島、海中にありき。これを引き寄せて、根(ね)を著(つ)けて、国に加へし故に、島根といふ。
現代語訳
島根郡の名の由来は、神代の時代に、神が住んでいた島が海の中にあったのを、陸へ引き寄せてその根を地に固定し、国土に加えたという伝承に由来しています。そのため、「島の根」すなわち島根と呼ばれるようになったのです。
このように、「島を根づかせる」という地名の成立神話は、出雲が「国づくりの地」であったという認識を裏づけています。
意宇郡・神魂命の社に関する記述
原文
神魂命(かみむすびのみこと)の坐(いま)す社、意宇の郡、神魂の社にあり。昔、国の始めに天降り坐しき。
現代語訳
神魂命が祀られている社は、意宇郡の神魂社にあります。神話によれば、国の始まりのときに、この地に天から降りてこられたとされています。
ここでは、出雲が「国のはじまり」の舞台であるという意識が明確に記されており、神話の国・出雲の根源的な地位が語られています。
出雲郡・須佐の条より
原文
須佐の郷、名の所以は、須佐之男命、此の郷に坐(いま)して国土を治め給ひき。よって須佐といふ。
現代語訳
須佐の郷という地名の由来は、須佐之男命(スサノオノミコト)がこの土地にお住まいになり、国土の整備を行われたことにあります。ゆえにこの地は「須佐」と呼ばれるようになりました。
これは『古事記』にも記述のあるスサノオが「八重垣を作った地」とされる須佐神社の伝承と結びついており、地域信仰と神話が密接に融合している例です。
以上のように、『出雲国風土記』の原文には土地に宿る神々の物語が豊富に記録されており、その一つ一つが地名や神社と結びついて、現在の出雲地方の信仰や文化に深く根付いています。現代語訳を通じてその世界を追体験することは、古代人の自然観や神々との関係性を感じ取る貴重な機会となるでしょう。
広告
出雲国風土記の現代的意義
『出雲国風土記』は単なる古代の地誌ではなく、日本神話と地理、地域信仰が結びついた希少な文献として、現代でも多くの示唆を与えてくれます。古代人の自然観や信仰、地域社会の構造を知るだけでなく、現代の郷土意識や神社祭祀、地域文化を理解するための重要な手がかりにもなっています。
また、観光や地域活性化の文脈でも、風土記の記述をもとにした神話の舞台や由緒ある地名が脚光を浴びており、「神話の国・出雲」としてのイメージを支える文化資源となっています。
広告
おわりに
『出雲国風土記』は、日本最古の地方地誌としてのみならず、地域と神話の融合が生んだ古代日本の知恵と信仰の記録です。地名ひとつをとっても、それが単なる言葉ではなく、神の行為や天皇の言葉と結びついた「物語」として存在していたことが、読み取れるのです。古代の出雲人が見ていた世界を、現代の私たちがたどることができるのは、この風土記が千年以上の時を越えて伝えられてきたからにほかなりません。