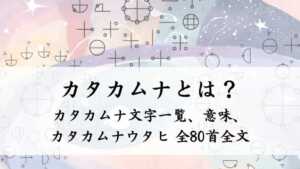夏の夜空を彩る隅田川花火大会は、東京の風物詩として多くの人々に親しまれています。しかし、その始まりは単なる娯楽ではなく、飢餓と疫病に苦しんだ江戸の人々への慰霊と祈りに根ざしていました。本記事では、水神祭の由来や、隅田川花火大会の歴史的背景、そして復活の経緯までを詳しくご紹介します。
広告
享保の飢饉と疫病、そして川施餓鬼
享保17年(1732年)、江戸は深刻な飢饉と疫病に見舞われました。とくに西日本ではイナゴの大発生や冷害によって農作物が壊滅的な被害を受け、多くの民が餓死しました。江戸でも物価の高騰や物資の不足が起こり、死者が続出する事態となります。そのうえ、疫病、いわゆるコレラのような伝染病も広まり、街は悲しみに包まれていました。
時の八代将軍・徳川吉宗は、民の苦しみを受け止め、翌享保18年(1733年)に「川施餓鬼(かわせがき)」と呼ばれる死者供養の法会を隅田川の河畔で行わせました。この法会は、無縁仏や疫病で亡くなった人々の霊を弔うために行われたもので、宗教的な意味と共に政治的配慮も込められていたと考えられます。
広告
水神祭と花火の起源
川施餓鬼とあわせて、同年には水神をまつる祭り「水神祭」も催されました。水神祭とは、水の神に対して感謝を捧げ、また災いの発生を防ぐための儀礼です。水辺に住む江戸の人々にとって、水神は生活と密接な関係を持つ神でした。水神への祈願と死者の慰霊、そして町の復興を願って、水神祭の夜には花火が打ち上げられました。
このとき、両国橋周辺の料理屋が幕府からの許可を得て花火を打ち上げたことが、現在の隅田川花火大会の起源とされています。当時の隅田川は「大川」とも呼ばれ、古典落語などでもその名称が使われています。
広告
両国の川開きと花火師の登場
水神祭にあわせて行われたこの行事は「両国の川開き」と呼ばれ、夏の到来を告げる風物詩として江戸の町民に浸透していきました。花火の打ち上げは専門の職人「花火師」が担い、特に「玉屋」と「鍵屋」の二大流派が人々の人気を集めます。
観客はお気に入りの花火師の名前を呼びながら、夜空に咲く一瞬の光に歓声を上げました。こうした文化は次第に娯楽性を強めながらも、元来の祈りや慰霊の意味を忘れずに、江戸の庶民文化として根付いていったのです。
広告
明治維新から現代へ 途絶と再開の歴史
この伝統行事は、明治維新や戦争の混乱により幾度となく中断されてきました。特に第二次世界大戦中は空襲の危険や資源の不足から花火大会は中止となりました。また、高度経済成長期の昭和37年(1962年)から昭和52年(1977年)頃には、隅田川の水質汚染が深刻化し、衛生面や安全面の問題から開催が見送られていました。
しかし昭和53年(1978年)、水質の改善や護岸の整備が進んだことを受け、「隅田川花火大会」と名称を新たにして復活しました。これにより、江戸時代から続く伝統が再び現代の都市空間で蘇ることとなったのです。
広告
「隅田川花火大会」という名前の誕生と現在の形
今でこそ定着している「隅田川花火大会」という名称は、昭和53年に復活した際に付けられたもので、それ以前は「両国の川開き」として親しまれていました。打ち上げ場所も当初は両国橋の上流で行われていましたが、交通事情や観客の安全への配慮から、次第に上流へと移動されるようになります。
現在では、隅田川に架かる桜橋から言問橋の間に設けられた第一会場と、駒形橋から厩橋の間の第二会場で花火が打ち上げられ、花火師たちによるコンクール形式で競演が行われています。毎年7月末に開催され、東京都内で最大規模を誇る大会として知られ、100万人近い人々が訪れます。テレビやインターネットでの中継も行われ、東京の夏の一大イベントとなっています。
広告
おわりに
水神祭と隅田川花火大会は、単なる季節の風物詩にとどまらず、飢饉や疫病といった歴史的災厄を背景に生まれた祈りと再生の文化です。時代の変遷に応じて中断と復活を繰り返しながらも、花火の一発一発には今なお、江戸の人々の願いと精神が込められています。
夜空に咲く花火の光は、亡き人への供養であり、生きる人への希望でもあります。隅田川の水辺に集う人々の笑顔の背後には、そんな日本人の精神の歴史が静かに息づいているのです。