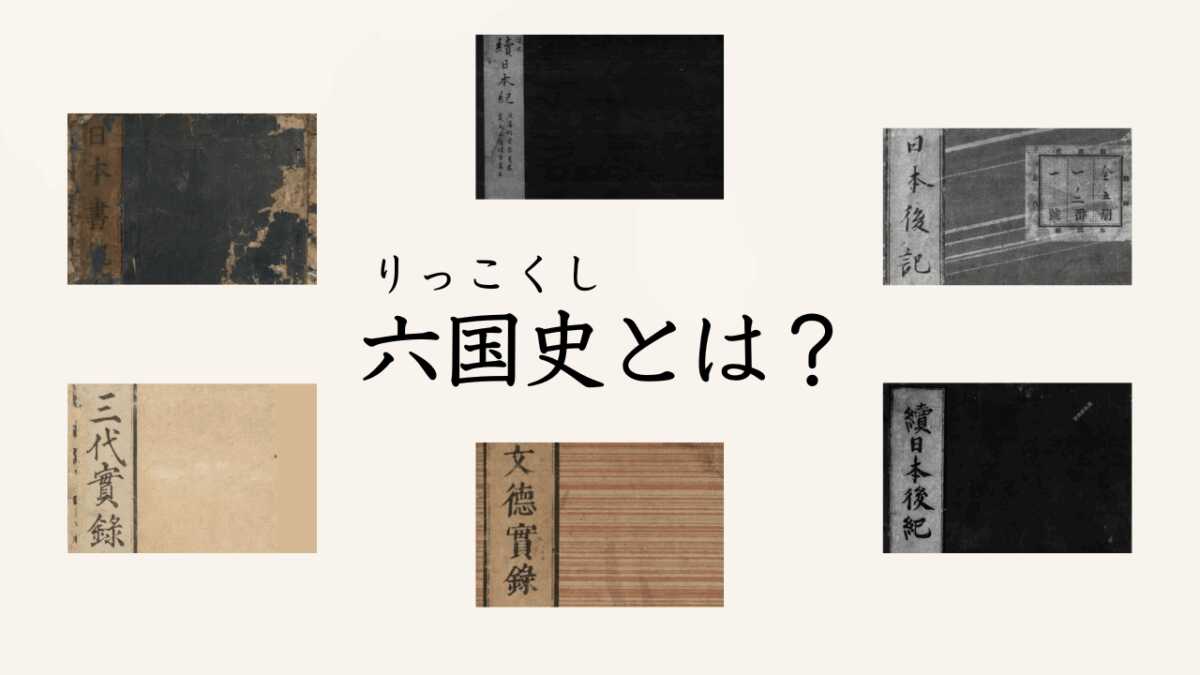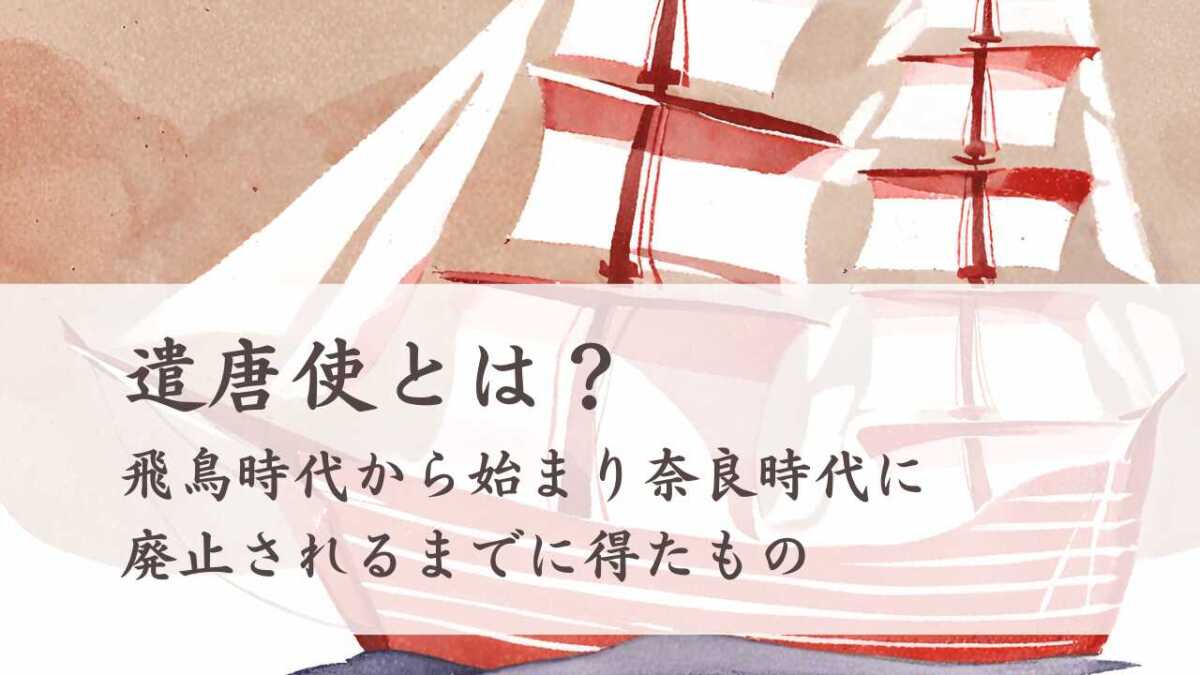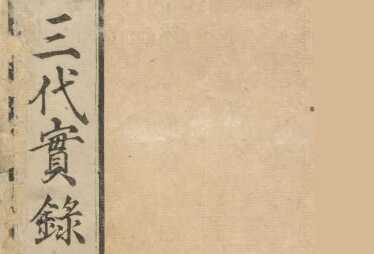
『日本三代実録(にほんさんだいじつろく)』は、六国史の最後に位置づけられる勅撰国史です。清和天皇、陽成天皇、光孝天皇の三代にわたる約30年間(858~887年)の出来事を記録し、醍醐天皇の勅命により901年に完成しました。全50巻から成る大部の史書であり、平安時代前期の政治、外交、仏教、そして社会生活を知るための重要な資料です。本記事では、『日本三代実録』の編纂背景や記録された内容を整理し、原文・書き下し・現代語訳を通じてその特徴を解説していきます。
広告
日本三代実録の編纂と背景
『日本三代実録』は、醍醐天皇の命により藤原時平らによって編纂されました。中国の実録形式に倣い、天皇一代ごとの記録を体系化しています。六国史の掉尾を飾るこの史書は、国家としての公式な歴史叙述の一つの完成形とも言える存在で、以後は国史編纂の伝統が途絶えるため、日本古代史の最後を飾る勅撰国史としても大きな意味を持っています。
この時代は藤原氏の摂関政治が確立していく過程にあり、また遣唐使の廃止など国際関係の転換期でもありました。そのため、『日本三代実録』には、国内の政治制度や宗教的行事に加え、外交上の重要な記録も含まれています。
六国史(りっこくし)とは?
六国史(りっこくし)とは、奈良時代から平安時代にかけて編纂された日本の正史(勅撰国史書)の総称です。『日本書紀』から『日本三代実録』までの6つの歴史書を指し、天皇の命によって国家事業として編まれました。中国の正史を手本にしながら、日本独自の歴史叙述を確立した六国史は、当時の政治・社会・文化を知るうえで欠かせない史料となっています。
六国史は以下の6つで構成されており、それぞれ扱う時代が異なります。
| 国史名 | 編纂年代 | 内容の対象時期 | 時代区分 |
|---|---|---|---|
| 日本書紀 | 720年 | 神代~持統天皇(697年) | 奈良時代初期に編纂、神話から律令国家成立まで |
| 続日本紀 | 797年 | 文武天皇(697年)~桓武天皇(791年) | 奈良時代全般 |
| 日本後紀 | 840年 | 桓武天皇(781年)~淳和天皇(833年) | 奈良後期~平安初期 |
| 続日本後紀 | 869年 | 仁明天皇(833年)~文徳天皇(850年) | 平安時代前期 |
| 日本文徳天皇実録 (日本文徳天皇實録) |
879年 | 文徳天皇(850年~858年) | 平安時代前期 |
| 日本三代実録 (日本三代實録) |
901年 | 清和天皇(858年)~光孝・宇多・醍醐天皇(887年) | 平安時代前期 |
広告
日本三代実録に記録されている時代の流れ
『日本三代実録』が対象とするのは、清和・陽成・光孝の三代の天皇期です。それぞれの治世における政治的変化や文化の動向を知ることができます。
広告
日本三代実録に見える出来事
摂関政治の確立
清和天皇が幼少で即位したため、外祖父の藤原良房が初の摂政となり、藤原氏による摂関政治が制度化されました。以後、藤原氏が天皇の外戚として権力を握る政治体制が確立していきます。
外交と遣唐使廃止
この時期、唐の衰退を背景に遣唐使が廃止されました。『日本三代実録』には、遣唐使派遣停止に関する記事があり、日本が独自の文化を育んでいく契機となったことが読み取れます。
災異や社会状況
『日本三代実録』には地震や疫病、飢饉など災異に関する記録が多く残されており、当時の人々が自然現象をどのように受け止めていたかを知る貴重な手がかりとなります。
広告
原文・書き下し・現代語訳の例
原文(漢文)
「貞観八年四月、廃遣唐使。」
書き下し文
「貞観八年四月、遣唐使を廃す。」
現代語訳
「貞観8年(866年)4月、遣唐使を廃止した。」
この短い記述から、日本が唐との直接的な交流を終え、新たに国風文化を発展させていく時代の始まりを読み取ることができます。
原文は、国書データベースなどで確認できます。
広告
日本三代実録の特徴
『日本三代実録』は、政治・宗教・災害・外交など多岐にわたる記録を網羅しており、平安前期の社会全体を知るための総合的な史料です。特に神社に関する記事が多く、神階の授与記録は神社史研究に欠かせません。また、摂関政治の成立や遣唐使廃止といった日本史の大転換点を公式記録として伝える点で、歴史上の価値が極めて高い書物です。
広告
まとめ
『日本三代実録』は、六国史の最後を飾る勅撰国史であり、清和・陽成・光孝の三代にわたる時代を記録した全50巻の史書です。摂関政治の確立や遣唐使廃止など、日本の政治と文化が大きく変わる節目を伝える重要な資料であり、当時の社会や信仰を知るための第一級の史料でもあります。原文に触れることで、古代日本の国家意識と文化的自立の歩みを感じることができるでしょう。