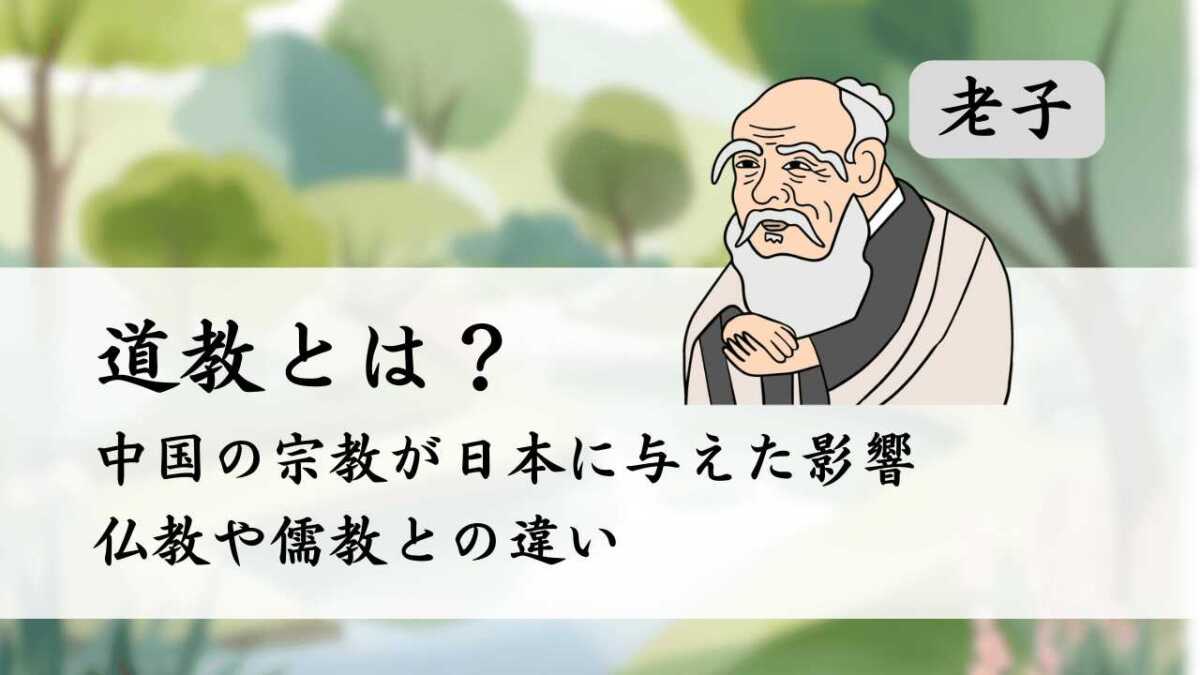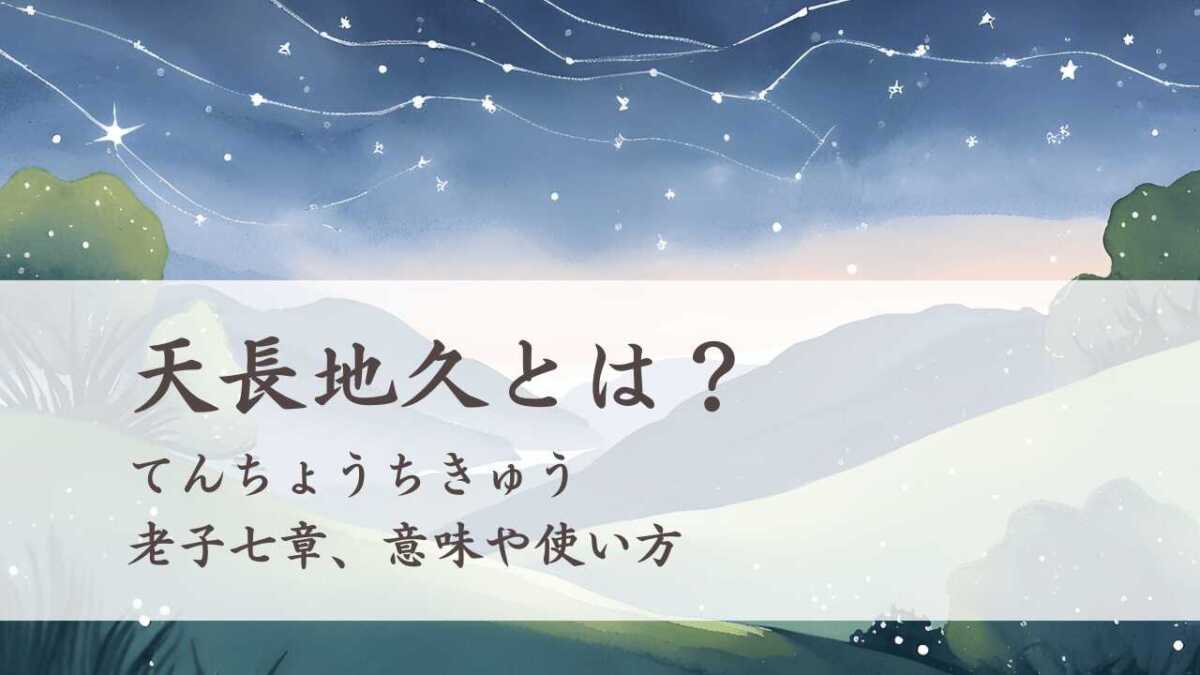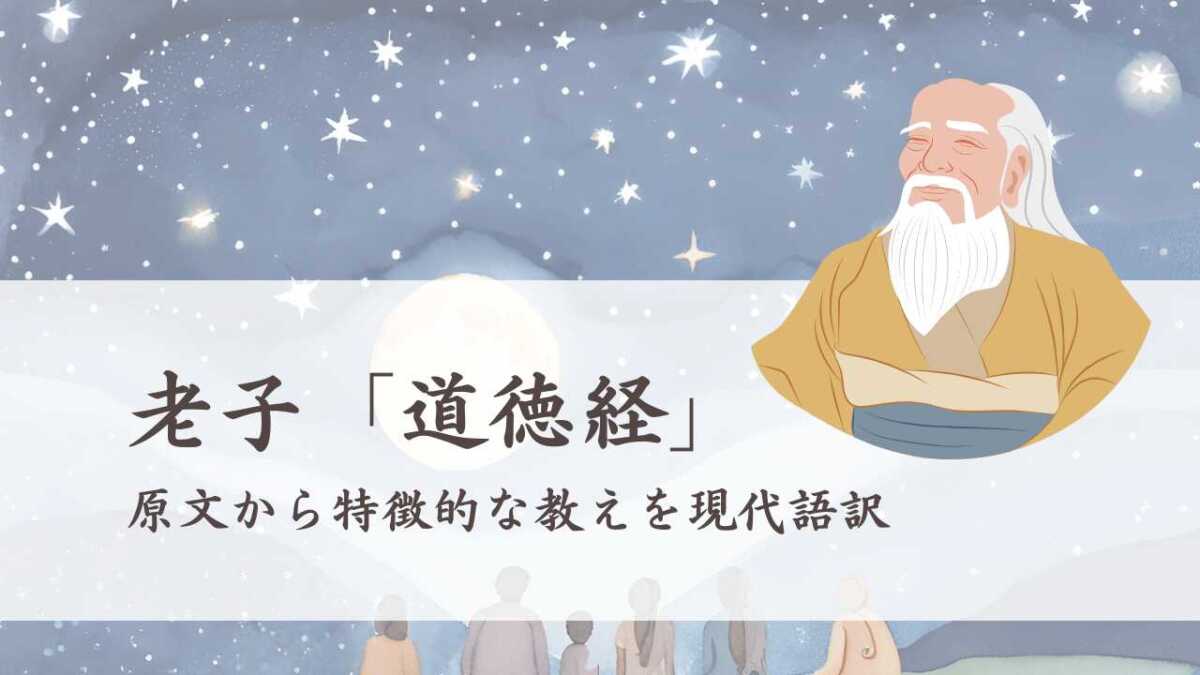
『道徳経』は、中国の思想家・老子によってまとめられたとされる書物で、道家(道教)の根本経典として知られています。本書は、宇宙の根源である「道(タオ)」について説く前半の「道経」と、その道に従って生きるための指針を示す後半の「徳経」の二部から構成され、老子の哲学が凝縮されています。本記事では、『道徳経』の原文とともに、その現代語訳をできる限り多く掲載し、それぞれの章がどのような意味や教えを持っているのかを詳しく解説します。老子の思想が示す「自然に逆らわず、調和の中で生きる」道とは何か、その本質を紐解いていきましょう。
広告
道徳経とは?いつの時代にまとめられたのか
『道徳経』(どうとくきょう)は、中国の春秋戦国時代に生きたとされる思想家・老子(ろうし)によって書かれたと伝えられる書物である。『老子』とも呼ばれ、儒教や仏教と並ぶ東洋思想の一大潮流である道家(道教)の根本経典とされている。
道徳経は全81章から成り、前半の「道経(どうきょう)」と後半の「徳経(とくきょう)」に分かれている。前半では宇宙の根源である「道(タオ)」について説かれ、後半では道に従って生きる際の「徳(あり方)」が語られている。成立時期については諸説あるが、春秋時代末期から戦国時代(紀元前6世紀~4世紀)の間にまとめられたと考えられている。漢代にはすでに広く読まれ、道教の聖典とされるとともに、後の中国哲学や政治思想に多大な影響を与えた。
広告
道徳経の原文と現代語訳
第一章「道の本質」
原文
道可道、非常道。名可名、非常名。
無名天地之始。有名万物之母。
故常無、欲以観其妙。常有、欲以観其徼。
此両者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄、衆妙之門。
現代語訳
「道」とは、言葉で完全に説明できるものではない。「名」とは、すべてを表し尽くせるものではない。
「無」という状態は、天地が始まる前の根源であり、「有」という状態は、万物が生まれる母のようなものである。
だからこそ、無の状態に目を向ければ、道の奥深い本質を見ることができる。有の状態に目を向ければ、形あるものの限界を知ることができる。
この「有」と「無」は本来一つのものであり、異なる言葉で表されているだけである。どちらも「深遠なるもの」と呼ばれ、それはさらに奥深い真理へと続いている。これこそが、すべての神秘が生まれる源である。
この章では、「道(タオ)」は固定された概念ではなく、言葉や知識で完全に捉えることができないことを説いている。「無」と「有」は対立するものではなく、互いに補い合いながら存在しているという考え方が示されている。
第二章「相対的な世界」
原文
天下皆知美之為美、斯悪已。皆知善之為善、斯不善已。
故有無相生。難易相成。長短相形。高下相盈。音声相和。前後相随。
是以聖人処無為之事、行不言之教。
現代語訳
この世界では、人々が「美しい」と知ることで「醜さ」が生まれ、「善い」と知ることで「悪」が生まれる。
「有」と「無」は互いに生じ合い、「難しい」と「易しい」は互いに補い合い、「長い」と「短い」は互いに関係し、「高い」と「低い」は互いに成り立ち、「音」と「無音」は互いに調和し、「前」と「後」は互いに依存している。
だからこそ、聖人は「無為の行い(自然の流れに逆らわない生き方)」を実践し、言葉ではなくその行いによって人々に教えを示すのである。
この章では、世界はすべて対立する概念によって成り立っており、一方がなければ他方も存在しないことを説いている。聖人はこうした相対的な価値観にとらわれず、自然の流れに従いながら生きることが大切だとされる。
第七章「天長地久、自己の利益を最優先にせず、他者のために行動する」
原文
天長地久。
天之所以長而地之所以久者、以其不自生。故能長生。
是以聖人後其身而身先、外其身而身存。
非以其無私邪?故能成其私。
書き下し文
天は長く、地は久し。
天の長くして地の久しきは、その自らを生ぜざるを以(も)ってなり。故に能(よ)く長生(ちょうせい)す。
是(ここ)を以って聖人は、その身を後(おく)るも身は先んじ、その身を外(はず)るるも身は存(そん)す。
それその無私なるを以ってならずや?故に能くその私を成す。
現代語訳
天は永遠に続き、地もまた久しく存在し続ける。
それは、天も地も自らのために生きるのではなく、すべてを包み込むように存在しているからである。だからこそ、天も地も長く続くことができるのだ。
このように、聖人(理想的な人間)は自らを後回しにすることで結果的に先んじ、自分のことを考えずに生きることで、最終的にその身を保つことができる。
これは、彼が私心を持たず無私の心で生きるからではないだろうか?だからこそ、最終的には自分の本当の願いも叶うのだ。
解釈と教え
この章では、自然界の摂理と、人がどのように生きるべきかの道理が説かれている。天と地は自らの利益を求めず、ただあり続けることで永続する。それと同じように、人もまた自己の利益を最優先にせず、他者のために行動することで結果的に自身の目的を達成できる。これは「無私」の重要性を示す教えであり、謙虚な姿勢を持つことで、かえって人々から信頼され、社会の中で長く生き続けることができるという考え方である。
第八章「水のように生きる」
原文
上善若水。水善利万物而不争。処衆人之所悪、故幾於道。
居善地。心善淵。与善仁。言善信。正善治。事善能。動善時。
夫唯不争、故無尤。
現代語訳
最高の善とは水のようなものである。水は万物を潤しながらも争うことなく、自ら最も低いところへ流れていく。だからこそ、道に最も近い存在といえる。
水は、どんな環境にも適応し、心は深く静かで、他者に対しては誠実であり、言葉は信頼に満ち、政治は公平であり、仕事は能力に応じて行われ、行動は時機を見極めて行われる。
このように、ただ争わずに自然に従って生きることで、問題や過ちを避けることができる。
この章では、水の性質を例に挙げて、柔軟さと謙虚さの大切さを説いている。水は何ものとも争わず、どこにでも適応し、常に最も低い場所へと流れる。これは、人が無理に争うことなく、自然に身を任せながら生きることの重要性を示している。
第六十六章「リーダーのあるべき姿」
原文
江海所以能為百谷王者、以其善下之、故能為百谷王。
是以聖人之欲上民也、必以言下之。欲先民也、必以身後之。
是以聖人処上而民不重。処前而民不害。
是以天下楽推而不厭。
現代語訳
大河や海が多くの川の水を集めることができるのは、それが低い場所にあるからである。だからこそ、多くの川を従えることができる。
このように、聖人(理想的なリーダー)が人々の上に立とうとするなら、まず謙虚に振る舞わなければならない。人々の先頭に立ちたいなら、まず後ろに下がらなければならない。
そのため、聖人は人々の上にいても威圧感を与えず、前に立っていても邪魔にならない。だからこそ、民衆は聖人を敬いながらも、抵抗することなく自然に従うのである。
この章では、真のリーダーとは支配するのではなく、謙虚な姿勢を持ち、人々の信頼を得ることが重要であると説いている。権力を誇示するのではなく、人々と共に歩むことで、自然と周囲から支持される存在となるのだ。
広告
まとめ
『道徳経』は、老子の思想をまとめた書であり、自然に逆らわず、柔軟に生きることの大切さを説いている。現代でも、人間関係やリーダーシップ、自己成長に応用できる教えが数多く含まれている。老子の言葉は、時代を超えてなお、多くの人々に深い示唆を与え続けている。