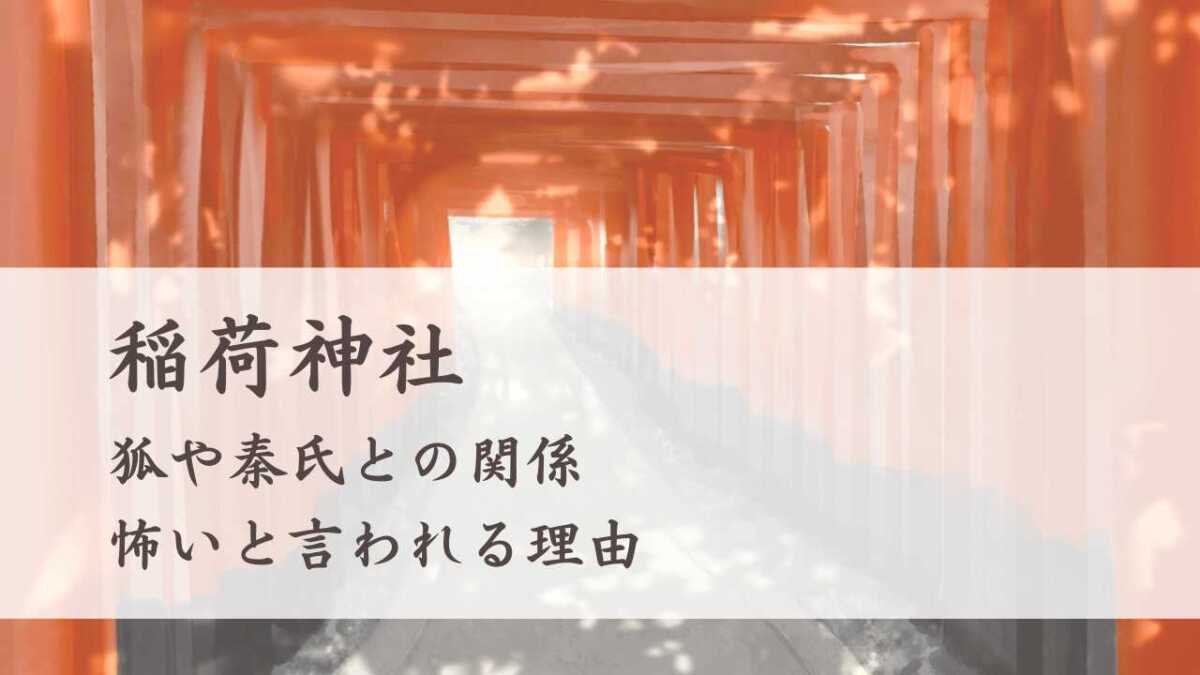初午(はつうま)とは、旧暦2月最初の午(うま)の日に全国の稲荷神社で行われる伝統的な祭りです。この日は、伏見稲荷大社(京都)に稲荷大神が降臨した日とされ、それを祝う神事が執り行われます。稲荷神は、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全などのご利益をもたらす神として広く信仰されており、初午祭はその恩恵に感謝し、さらなる繁栄を祈願する重要な行事です。本記事では、初午の由来や歴史、稲荷神社での神事の意味、全国の初午祭の特色について詳しく解説します。
広告
初午(はつうま)とは?
初午(はつうま)とは、旧暦2月最初の午(うま)の日に行われる伝統的な神道の祭りで、全国の稲荷神社(いなりじんじゃ)で盛大に祝われます。この日は、稲荷神の総本社である伏見稲荷大社(京都)に稲荷大神(いなりのおおかみ)が降臨した日とされ、これを記念して稲荷信仰の神事が執り行われるようになりました。
稲荷大神は、日本全国に約3万社ある稲荷神社の祭神であり、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、産業振興の神として広く信仰されています。初午の日には、神前に供物を捧げ、神恩に感謝するとともに、さらなる繁栄や豊作を祈る祭典が行われます。
広告
初午祭の由来と歴史
伏見稲荷大社の縁起
初午祭の起源は、奈良時代の和銅4年(711年)2月の初午の日に遡ります。この日、京都の伏見稲荷大社の稲荷山に稲荷大神が降臨したと伝えられ、それ以来、稲荷信仰が広まりました。伏見稲荷大社は、全国の稲荷神社の総本社として現在も多くの参拝者を集めています。
稲荷信仰の広がり
平安時代には、朝廷や貴族の間で稲荷信仰が盛んになり、農業や商業の守護神として崇められました。中世以降は、武士や商人、庶民の間にも広がり、全国各地で稲荷神社が建立されるようになりました。特に江戸時代には、商売繁盛を願う町人たちの間で初午祭が重要な年中行事となり、現在に至るまで続いています。
広告
初午祭の神事と意味
稲荷神のご利益
稲荷神は五穀豊穣や商売繁盛の神であり、農業・商業・工業・家業など、あらゆる仕事の繁栄をもたらすと信じられています。初午祭では、次のような願いが込められます。
- 五穀豊穣(農業の豊作)
- 商売繁盛(企業や商店の発展)
- 家内安全(家族の健康と幸福)
- 産業振興(職業・事業の成功)
- 学業成就(勉学や習い事の上達)
しるしの杉(杉玉)
伏見稲荷大社をはじめとする多くの稲荷神社では、「しるしの杉」と呼ばれる杉の枝を授かることができます。
平安時代の中期以降になると、紀州への熊野詣が盛んになり、その道中では稲荷社への参詣が習わしとなっていました。参拝の際には、稲荷社の杉の小枝「しるしの杉」を授かり、身につけることが広く行われていたとされています。
稲荷大神の加護を受ける象徴であり、商売繁盛や家内安全の祈願として自宅や店舗に飾られます。
赤飯や油揚げのお供え
稲荷神の使いである狐(きつね)は、油揚げを好むとされ、初午の日には油揚げや赤飯を供える風習があります。これは、稲荷神の恩恵に感謝し、さらなる繁栄を願うものです。
火焚き祭(ひたきさい)
一部の稲荷神社では、火焚き祭(ひたきさい)が行われます。これは、古いお札やお守りを焚き上げ、浄火の力によって穢れを祓い、新たな一年の繁栄を祈る儀式です。
広告
初午祭の全国の特色
伏見稲荷大社(京都府)
全国の稲荷神社の総本社である伏見稲荷大社では、初午祭が特に盛大に行われます。この日には、全国から多くの参拝者が訪れ、神事や火焚き祭が執り行われます。
豊川稲荷(愛知県)
曹洞宗の寺院でありながら稲荷信仰を持つ豊川稲荷では、商売繁盛や開運を願う多くの人々が初午の日に訪れます。特に企業経営者や商人に人気があります。
笠間稲荷神社(茨城県)
関東三大稲荷の一つとして知られる笠間稲荷神社でも、初午祭が盛大に行われます。地元の伝統芸能や神楽の奉納が行われ、参拝者で賑わいます。
太宰府天満宮(福岡県)
学問の神・菅原道真公を祀る太宰府天満宮でも、初午に関連した行事「天開稲荷社のおまつり」が行われます。「九州最古のお稲荷さん」と言われる「天開稲荷社」で、五穀豊穣、商売繁盛、開運を願ってお祭りが行われます。天神信仰と稲荷信仰が結びつき、学業成就の祈願が行われます。
広告
初午祭の豆知識
初午と「午(うま)」の関係
「午(うま)」は、十二支の一つであり、火の気を持つとされています。稲荷神は火や豊穣を司る神でもあるため、「午の日」に祭りを行うことで、火の神の加護を受け、作物の豊穣や商売繁盛を祈る意味が込められています。
初午大祭と二の午、三の午
旧暦の初午は毎年日付が異なり、年によっては「二の午」「三の午」が存在することもあります。特に「二の午」「三の午」には、商売繁盛を願う追加の祈願を行う神社もあります。
広告
まとめ
初午(はつうま)は、稲荷神が降臨した日を祝う神道の伝統的な祭りであり、全国の稲荷神社で大切にされています。稲荷神は、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全など多くのご利益を授ける神であり、初午祭では感謝と祈りを捧げる神事が行われます。
伏見稲荷大社をはじめとする全国の稲荷神社では、火焚き祭やしるしの杉の授与、油揚げや赤飯の供物などが行われ、参拝者が新たな一年の繁栄を願います。日本の神道文化に根付いたこの伝統行事を通じて、神々への感謝と祈りの大切さを再認識し、日々の暮らしに活かしてみてはいかがでしょうか。