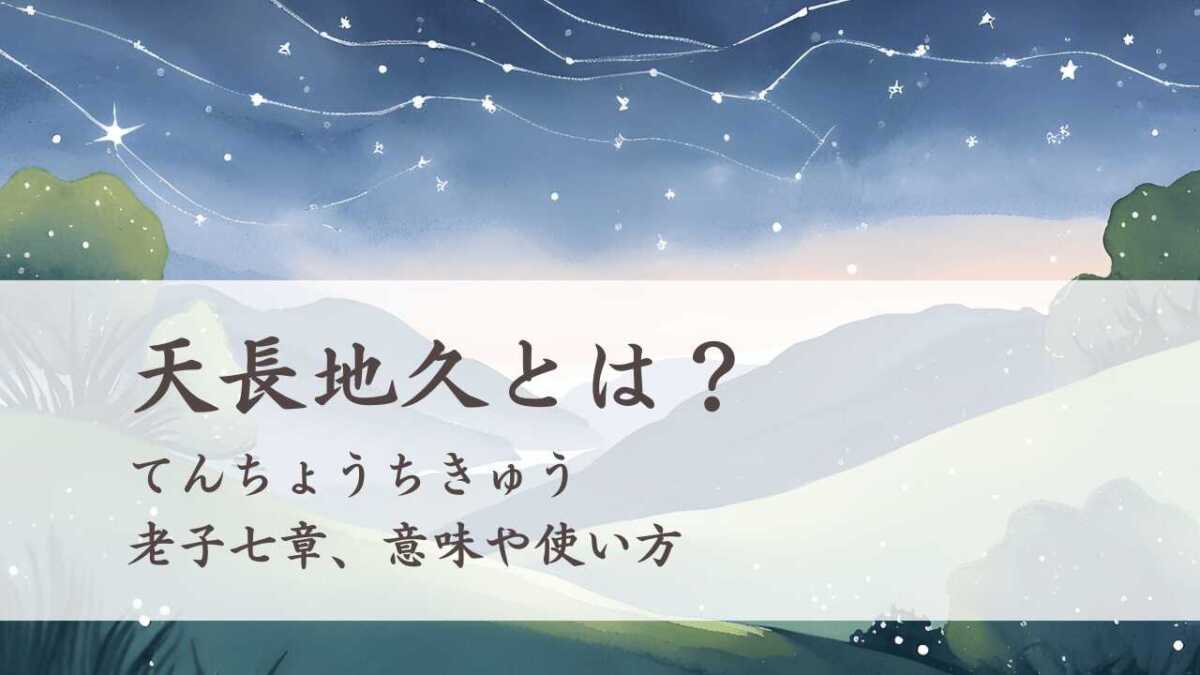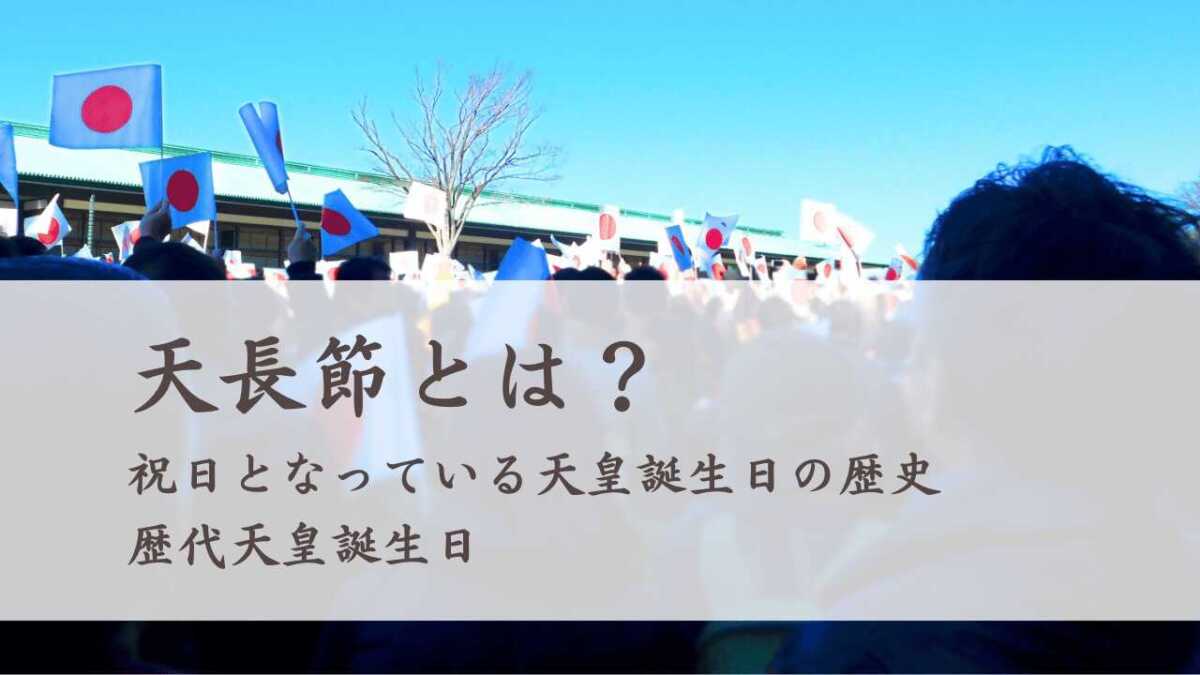
天長節とは、天皇の誕生日を祝う特別な祝日であり、その歴史は明治時代に正式に制定されたことに始まります。戦前は「天長節」として国家的に祝われていましたが、戦後は「天皇誕生日」として名称が変わり、歴代天皇の即位に伴い日付が変化してきました。神道において天皇は神聖な存在とされ、その誕生日は国家の安寧を願う重要な祭日でもあります。また、天皇誕生日には全国の神社で祝賀の神事が行われ、皇居では天皇陛下が国民と直接触れ合う一般参賀が開催されます。本記事では、天長節の歴史や神道における意義、各時代の天皇誕生日、そして現在も続く一般参賀の詳細について詳しく解説します。
広告
天長節とは?歴史と意味
天長節(てんちょうせつ) とは、天皇の誕生日を祝う儀式 であり、日本の国民的な祝日です。現在では「天皇誕生日」として国民の祝日になっていますが、歴史的には天長節という名称で親しまれてきました。
天長節の由来
「天長節」という名称は、中国・唐の時代に由来し、天長地久「天が長く、地が久しいように、天子の治世も長く続くことを願う」という意味が込められています。この思想が日本に伝わり、天皇の誕生日を祝う国家的行事 として定着しました。
天長節の変遷
明治時代(1873年):「天長節」として正式に祝日化
戦後(1948年):GHQの意向により「天長節」という名称は廃止され、「天皇誕生日」として存続
現在:「天皇誕生日」として祝日になっており、歴代天皇が変わるごとに日付も変わる
広告
天長節は神道でどんな意味を持つのか
神道において、天皇は 「現人神(あらひとがみ)」 として 天照大御神(あまてらすおおみかみ)の子孫 であり、神聖な存在とされています。そのため、天皇の誕生日である天長節は、単なる祝日ではなく、国家の安寧と繁栄を願う重要な祭日 でした。
神道的な意義
天皇必ずの長寿と国家安泰を願う日
「天長地久(てんちょうちきゅう)」という言葉に表されるように、天皇の寿命が永く、国が繁栄することを祈る日
国家祭祀の一環
神社で行われる 国家安寧の祝詞奏上 や 奉祝祭 も、この日を特別なものとして位置づけている
広告
天皇誕生日に神社ではどのような天長節の祭儀(天長祭)が行われるか
天長節(天皇誕生日)には、全国の神社で天皇の長寿と国家の繁栄を祈る神事「天長祭」や「天皇御誕辰奉祝祭」が執り行われます。特に、伊勢神宮 や 宮中三殿 では厳粛な儀式が行われます。
| 神社名 | 祭儀内容 |
|---|---|
| 伊勢の神宮 | 天長祭として、皇大神宮で天皇陛下の長寿と国家の安泰を祈る祭典 |
| 靖国神社 | 天皇御誕辰奉祝祭として、英霊とともに天皇の御代の平安を祈る |
| 全国の護国神社 | 天長節祭として、各都道府県の護国神社で奉祝の祝詞を奏上 |
| 宮中三殿(賢所) | 皇室の祖先神・天照大御神に天皇陛下の健康を祈願 |
広告
明治から令和までの歴代天皇誕生日
天皇の誕生日は、歴代ごとに日付が変わります。以下に明治以降の天皇誕生日をまとめます。
歴代天皇の誕生日と天長節の日
| 天皇 | 在位期間 | 誕生日 | 天長節の日 |
|---|---|---|---|
| 明治天皇 | 1867-1912 | 1852年11月3日 | 11月3日(明治時代の天長節)→現在は文化の日 |
| 大正天皇 | 1912-1926 | 1879年8月31日 | 8月31日(大正時代の天長節)→廃止 |
| 昭和天皇 | 1926-1989 | 1901年4月29日 | 4月29日(昭和の日として存続) |
| 平成天皇(上皇陛下) | 1989-2019 | 1933年12月23日 | 12月23日(現在は平日) |
| 令和天皇(今上陛下) | 2019-現在 | 1960年2月23日 | 2月23日(現行の天皇誕生日) |
現在、天皇が代替わりすると天皇誕生日(祝日)が変わるため、昭和天皇や平成天皇の誕生日は別の形で存続しています。
広告
天皇誕生日の一般参賀とは?
一般参賀とは
天皇誕生日には、毎年 皇居で「一般参賀(いっぱんさんが)」 が行われます。これは 国民が直接天皇陛下にお祝いを伝えられる貴重な機会 です。
天皇誕生日の一般参賀は、毎年2月23日に皇居で行われ、天皇陛下のお誕生日を祝うために多くの国民が訪れます。
例年の一般参賀の流れ・タイムスケジュール
午前中には、天皇皇后両陛下をはじめとする皇族方が宮殿「長和殿」のバルコニーに3回お出ましになり、参賀者に向けてお言葉を述べられます。参賀者は午前9時30分から11時20分までに皇居正門(二重橋)から参入し、宮殿東庭で天皇陛下のお姿を拝し、お祝いを伝えることができます。
午後には皇族方のお出ましはありませんが、宮内庁庁舎前に設けられた記帳所で、参賀者が天皇陛下への祝意を記帳することができます。午後の参賀は12時30分から15時30分まで行われ、退出門は16時に閉門されます。
一般参賀は非常に混雑するため、手荷物検査が行われ、キャリーバッグなどの大きな荷物の持ち込みが制限されます。皇居内は砂利道や坂道が多く、履物には十分な注意が必要です。また、立ち止まりや列の乱れを防ぐため、職員の指示に従いながら整然と移動することが求められます。毎年多くの参賀者が訪れるこの行事は、天皇陛下と国民が直接触れ合う貴重な機会となっています。
広告
まとめ
天長節(天皇誕生日)は、日本の歴史と深く関わる重要な祝日です。かつては「天長地久」を願う国家的な祭日として行われていましたが、戦後は「天皇誕生日」として祝日化され、時代とともに変化してきました。
神道では、天皇は天照大御神の子孫とされ、天長節は単なる誕生日ではなく、国の平安と繁栄を願う特別な日 です。全国の神社での祝賀行事や、皇居での一般参賀は、日本文化の重要な一面を示しています。
歴代天皇の誕生日は時代とともに変化しましたが、その精神は今も受け継がれています。令和の時代においても、天皇誕生日は 国民が一体となってお祝いする大切な日 であり続けるでしょう。