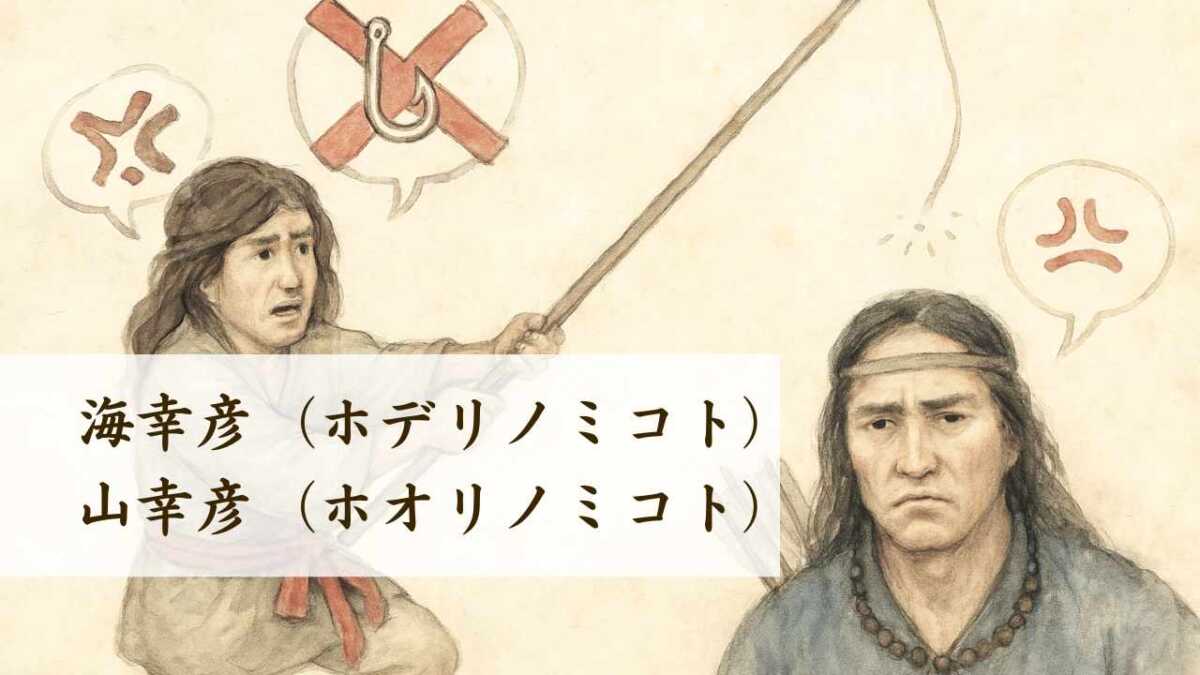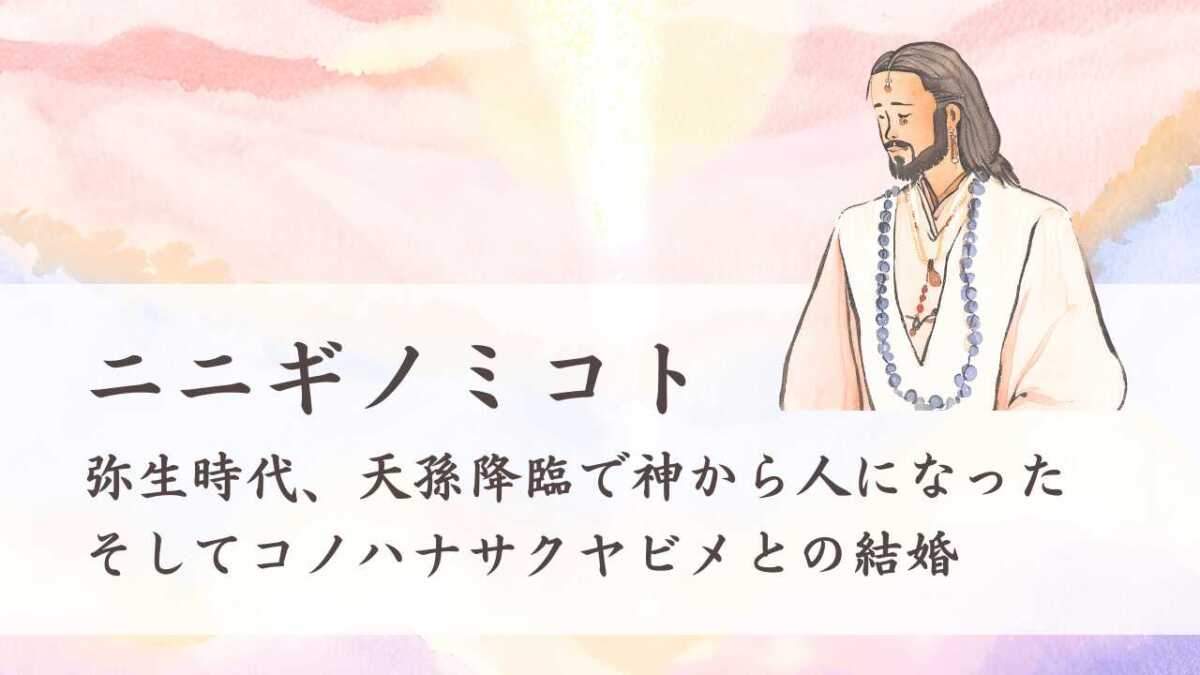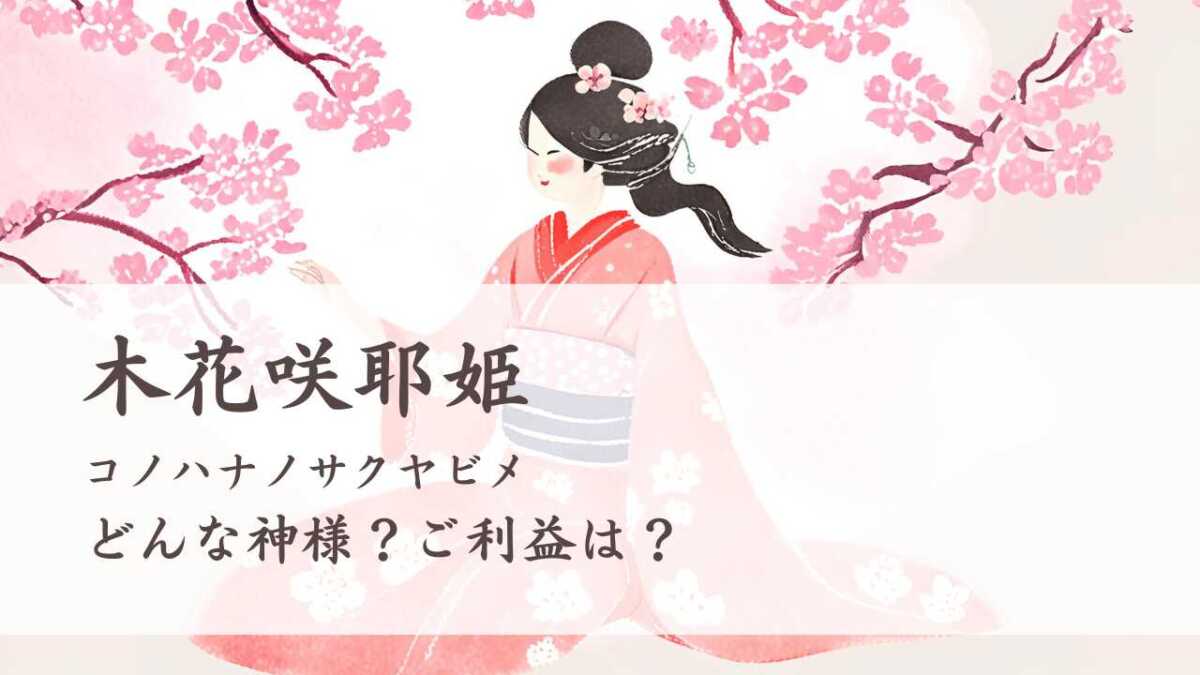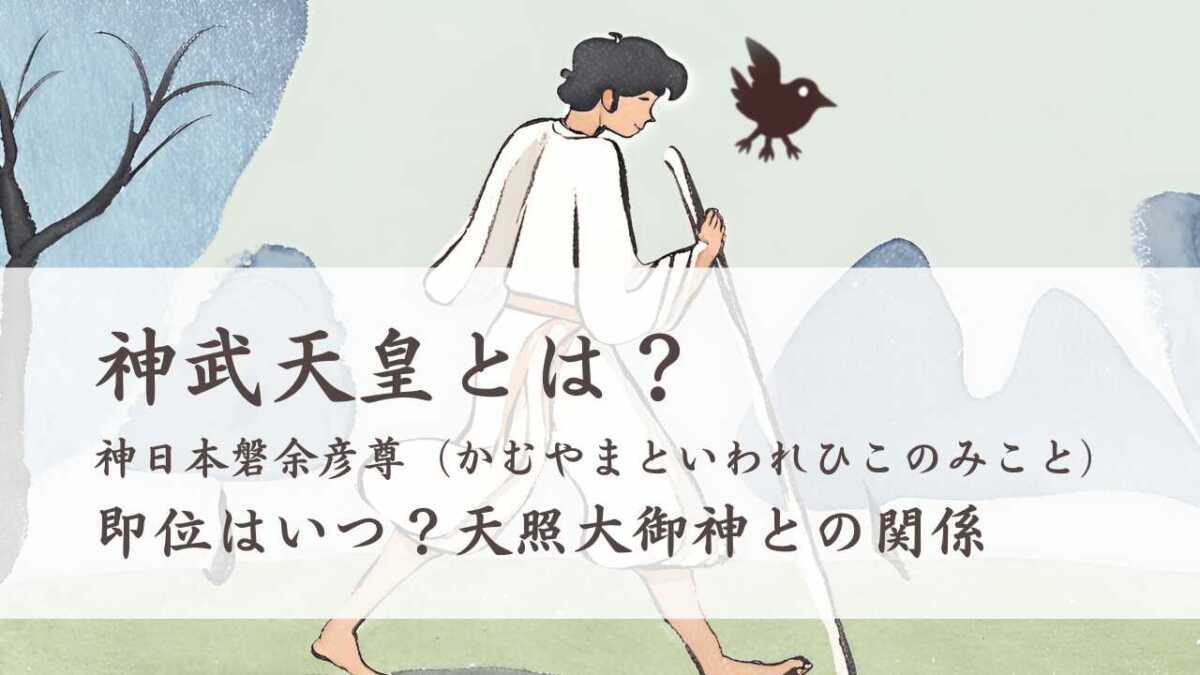ホオリノミコト(山幸彦)は、日本神話に登場する重要な神であり、天孫ニニギノミコトと木花開耶姫の子として生まれました。兄との釣り針をめぐる争いや、海神の娘との婚姻、さらには初代天皇である神武天皇の祖先としての役割など、数々の神話にその名が刻まれています。本記事では、ホオリノミコトの名前の意味や系譜、兄弟神との対立、海神宮でのエピソード、日本神話における位置づけまでをわかりやすく解説します。
広告
ホオリノミコトの名前と意味
ホオリノミコト(山幸彦)は、日本神話に登場する神で、漢字では「火遠理命」「火折命」「穂織命」などと表記されます。最も一般的な「火遠理命」という名前は、「火が遠くまで及ぶ働きを持つ者」と解釈され、自然現象としての火や、その霊力の広がりを象徴しています。別名である「穂織命」は、稲穂や農作物との関係を連想させるものであり、ホオリノミコトが農耕神的な性格も持つことを示しています。
さらに、『古事記』では「海幸山幸」の段として、『日本書紀』では「火折尊(ホオリノミコト)」の条として、「山幸彦」という名前で語られている日本神話の重要な神様です。
広告
系譜と神武天皇とのつながり
ホオリノミコトは、天孫ニニギノミコトと木花開耶姫の第三子として生まれました。
兄にあたるのはホデリノミコト、次兄はホスセリノミコトとされます。このうち特にホデリノミコトとの関係が神話上で大きく取り上げられています。
また、ホオリノミコトとトヨタマビメとの間にはウガヤフキアエズノミコトが生まれ、その子が初代天皇である神武天皇であることから、ホオリノミコトは皇祖神の一柱とされています。
物語の系譜をわかりやすくするために、『古事記』系の並びをもとに簡略化して示します。
| 世代 | 神名・人物 | 説明 |
|---|---|---|
| 父 | 邇邇芸命(ににぎのみこと) | 天照大御神の命で高天原から天孫降臨した |
| 母 | 木花開耶姫(このはなさくやびめ) | 山の神である大山祇命(オオヤマツミ)の娘 |
| 三兄弟 | 長男・火照命(ほでりのみこと)=海幸彦 | 海の漁労を象徴する兄 |
| 三兄弟 | 次男・火須勢理命(ほすせりのみこと) | 中つ子(物語ではあまり中心に立たない) |
| 三兄弟 | 三男・火折尊(ほおりのみこと)=山幸彦 | 山・狩猟を象徴する末子、本話の主人公 |
| 山幸彦の妻 | 豊玉毘売命(とよたまびめ) | 海神・大綿津見神の娘。山幸彦の妻となる |
| 山幸彦と豊玉姫の子 | 鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと) | 海の一族と天孫の血が合流した子。 豊玉姫の妹・玉依姫(たまよりひめ)が育てる。 |
| 鵜葺草葺不合尊と玉依姫の子 | 神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと)=神武天皇 | 鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)と玉依姫(たまよりひめ)の間に生まれ、初代天皇となる |
このようにして見ると、海幸山幸の物語は、兄弟の争いというレベルにとどまらず、「海の神々の血」と「天孫の血」を皇統のところで結び合わせるための、神話上の説明装置になっていることが分かります。
三男・火折尊(ほおりのみこと)=山幸彦の子は、鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)。
鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)と玉依姫(たまよりひめ)の子が神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと)=神武天皇とつながっていくのです。
広告
釣り針をめぐる兄弟神の対立
ホオリノミコトとホデリノミコトのあいだには、釣り針の交換をめぐる「海幸山幸」神話が語られています。
狩猟を得意とするホオリと、漁を専門とするホデリは、それぞれの技を試すために道具を交換します。ホオリは兄の釣り針を借りますが、うまく使いこなせず海中に落としてしまい、兄に返せと言われて困り果ててしまいます。探しても見つからなかったホオリは、釣り針を取り戻すために海の神「大綿津見神(オオワタツミノカミ)」のもとへ向かいます。
広告
海神の宮殿での結婚と釣り針の返還
ホオリノミコトは海神の宮にたどり着くと、その娘トヨタマビメと出会い、三年の月日を過ごすことになります。海神はホオリに親切に対応し、失くした釣り針を見つけ出して返してくれます。そして満ち潮と引き潮を操る珠を授け、これを使えば人を溺れさせることも救うこともできると教えます。この神具は後に兄との争いを終わらせるために用いられます。
広告
ホデリとの和解と力の逆転
地上に戻ったホオリは、釣り針を返すだけでなく、潮の珠を使って兄を懲らしめます。ホデリは次第に追い詰められ、自ら非を認めて謝罪します。このエピソードは、ただの兄弟喧嘩にとどまらず、古代社会における権力の逆転や、狩猟と漁労、天孫族と海神族といった文化の交差を象徴していると解釈されています。
広告
トヨタマビメの出産と神と人の境界
ホオリノミコトはトヨタマビメとの間に子をもうけますが、出産の際にトヨタマビメは本来の姿である鰐(和邇・ワニ)の姿に戻ります。ホオリがその姿を覗き見てしまったことで、トヨタマビメは深く傷つき、子を産んだ後、海に帰ってしまいます。この話は、神と人との間にある越えられない境界や、神聖なるものを覗き見ることの禁忌といった、日本神話における重要な思想を表しています。
広告
日本神話における重要な役割
ホオリノミコトは、兄弟神との対立、海神との婚姻、皇統神話への接続といった、神話構造の要所をつなぐ存在です。彼の物語は、自然と神の力、人間の行動、文化の変化を重ね合わせて描かれており、日本古代社会の価値観を読み解く手がかりとなります。天孫降臨後の地上世界を舞台に、神と人との関係、力の正当性、和解と支配の形を体現する神であり、今日においても多くの神社や信仰において重んじられている理由がそこにあります。