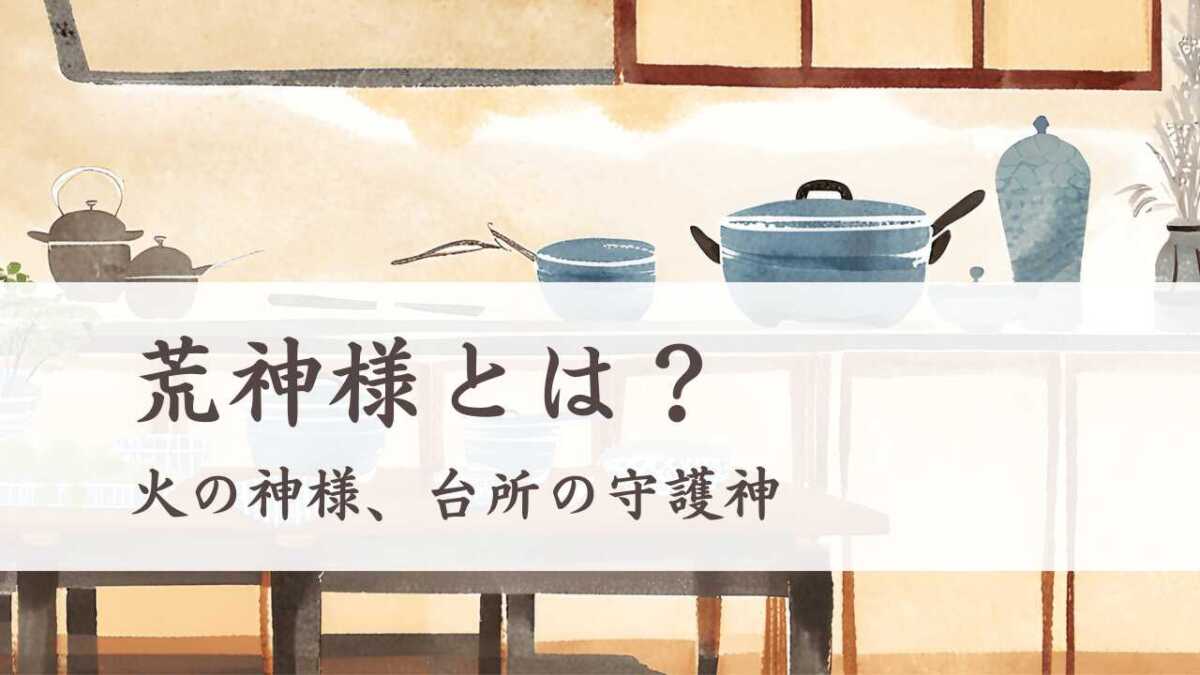
荒神様(こうじんさま)は、火を司り、台所やかまどを守る神様として古くから日本の家庭で信仰されてきました。日々の暮らしに欠かせない火は、便利であると同時に恐ろしさも秘めた存在。その火を御し、災いを防ぐ存在として荒神様は台所の守り神とされ、多くの家庭に祀られています。本記事では、日本神話や神道の考え方、日本で古来から信仰されてきた風習に基づき、荒神様の由来、ご神徳、お札の入手方法、神棚や台所での祀り方まで丁寧に解説します。
広告
荒神様とはどんな神様か
荒神様(こうじんさま)とは、主に火やかまど、台所を守る神様として古くから信仰されてきた存在です。「荒(あら)」という文字から荒々しい神をイメージするかもしれませんが、実際には人々の暮らしを見守る身近な守護神として親しまれています。民間信仰では「三宝荒神(さんぼうこうじん)」として、台所に祀られることが多く、火難除けや家庭の繁栄、無病息災をもたらす神様とされています。
広告
日本神話と荒神信仰の関係
荒神様は、記紀神話には明確には登場しませんが、火の神である「火産霊神(ほむすびのかみ/カグツチ)」との関連で信仰されるようになったと考えられています。火産霊神は、伊弉冉尊(いざなみのみこと)が火の神カグツチを生んだ際に火傷を負い亡くなったことで、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)に斬られた神であり、その身体から多くの神々が生まれました。
こうした背景から、火の神は強い霊力を持つとされ、慎重に扱うべき存在とされてきました。荒神様もまた、火の浄化力と破壊力の両面を持ち、扱い方によって吉凶が分かれるとされてきたのです。
広告
荒神様の神道における位置づけ
神社本庁の正式な教義においては「荒神様」という特定の神名は明示されていません。しかし、地域信仰や民間信仰のなかで大切にされてきた神霊であり、「台所の神」「火伏せの神」として神社の摂社・末社に祀られることもあります。特に神社のかまど神として「竈神(かまどがみ)」や「火結神(ほむすびのかみ)」などと習合して信仰されている場合があります。
広告
荒神様のご神徳と役割
荒神様の主なご神徳には、以下のようなものがあります。
- 火難除け・火伏せ
- 台所・かまどの安全
- 家内安全・商売繁盛
- 清浄と浄化
- 悪霊退散・魔除け
日々の食事や火を扱う生活の中で、清潔に保ち丁寧に暮らすことが、荒神様への祈りとされてきました。
広告
荒神様のお札の入手方法
荒神様のお札は、火の神を祀る神社や、地元で荒神信仰を伝える神社で頒布されています。とくに「三宝荒神社」や「愛宕神社」など火防の神を祀る神社では荒神札を扱っていることが多いです。近年では神社の公式ホームページから郵送対応をしている場合もあるため、確認するとよいでしょう。
お札は毎年新しいものに交換するのが基本です。古いお札は、神社に納める「古札納所」に返納します。
広告
台所や神棚での祀り方と向き
荒神様は一般的には台所の清浄な場所に祀られます。台所の高い棚の上や、壁に設けた「荒神棚」にお札を安置します。設置の際の注意点は以下のとおりです。
- 向きは南向きまたは東向きが吉とされる
- 目線よりも高い位置に設置する
- お札はきれいな状態で丁寧に扱う
- 毎朝、榊やお水、ご飯などを供えるとよい(可能な範囲で)
神棚にすでに天照大御神などの神々を祀っている場合は、別の棚や空間に荒神様を祀る方が良いとされます。荒神様は独立した神として扱い、他の神と並列にしないほうがよいとされてきたためです。
広告
現代における荒神様信仰
現代でも、荒神様への信仰は、火を扱う職人、料理人、飲食業の方々の間で根強く残っています。また、家庭でもキッチンを清めるという意味で、掃除の節目や新年に荒神棚を整える方も多く見られます。
火は便利でありながら危険も伴うもの。だからこそ、火を祀り、感謝し、敬意を払うという日本人の精神が、荒神様信仰を今も支えているのです。





