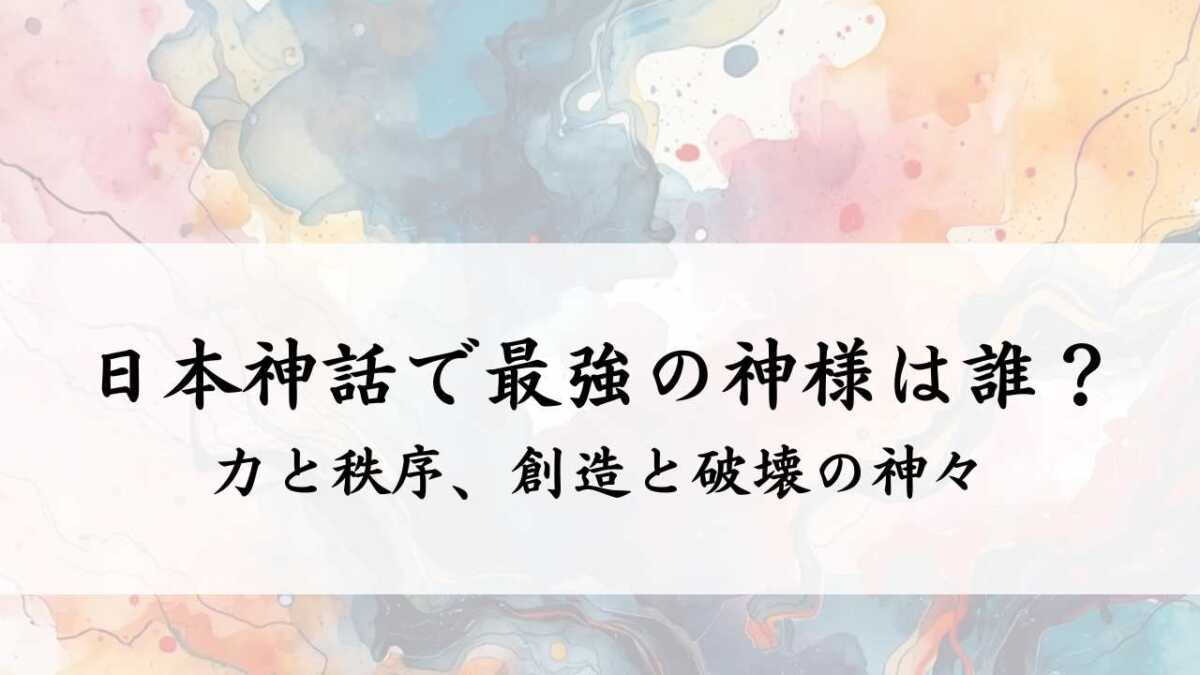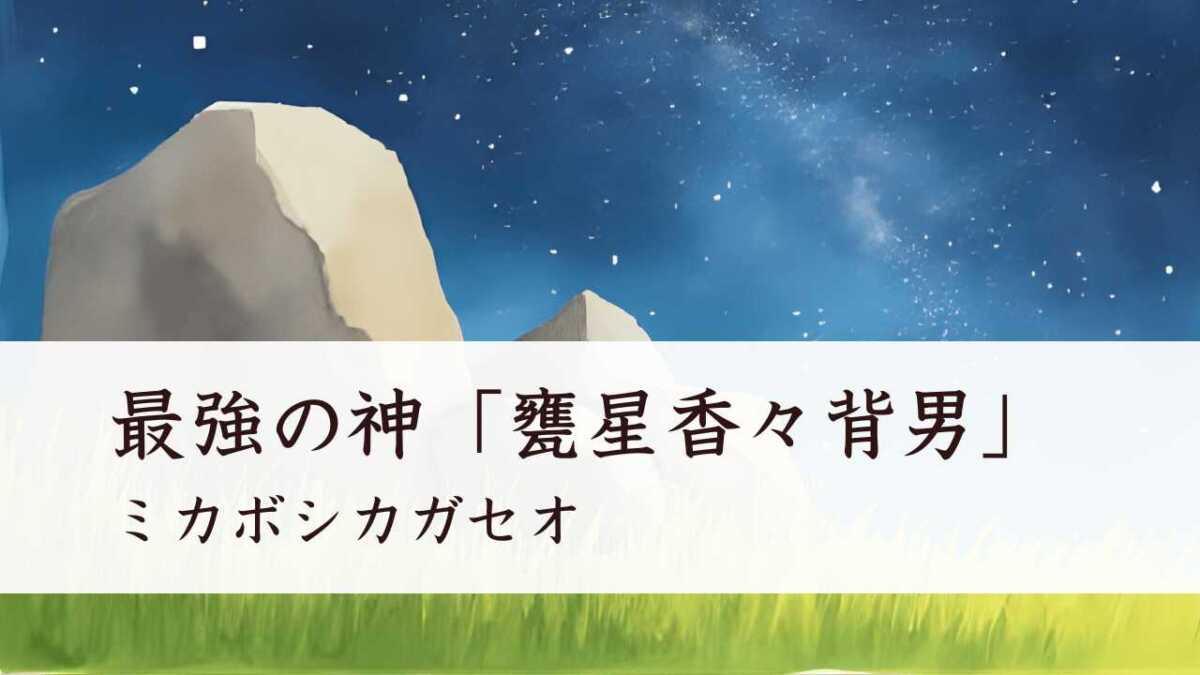
日本神話には数多くの神々が登場しますが、その中でも特異な存在として語られるのが甕星香々背男(ミカボシカガセオ)です。『日本書紀』では「天津甕星」「天香香背男」とも記され、天に坐す「悪神」として描かれました。国譲りの際には武甕槌神や経津主神でさえも容易に屈服させられなかったと伝えられ、その強大な力から「最強の神」と呼ばれることもあります。
この記事では、日本書紀の原文や現代語訳を紹介しつつ、甕星香々背男がどのような神であったのか、また祀られる神社やご利益についても詳しく解説します。
広告
甕星香々背男とはどんな神様?
甕星香々背男(みかぼしかがせお)は、日本神話に登場する異色の神で、日本書紀には「天津甕星(あまつみかぼし)」、またの名を「天香香背男(あめのかがせお)」と記されています。単に「香香背男(かがせお)」とも呼ばれ、星の神、特に「金星(明星)」を象徴する神であると考えられています。
日本書紀では、天照大御神の命を受けて葦原中国を平定する神々の中で、最後まで従わずに抵抗した最強の神として描かれています。その異名の多さからも、古代において特別な存在感を放つ神であったことがうかがえます。
広告
甕星香々背男を討伐できなかった伝承
鹿島神(武甕槌神)と香取神(経津主神)の二柱は、葦原中国において国津神をはじめ草木や石に至るまでを次々と平定しました。しかしただ一つ、甕星香々背男と呼ばれる星の神だけは、その強大な力ゆえに屈服させることができなかったと伝えられています。この時、両神に代わって大甕の地に赴き、地主神の霊威を宿した宿魂石に甕星香々背男の力を封じ込めたのが、倭文神・武葉槌命であったとされています。
この伝承は、茨城県日立市の大甕神社に残されており、境内には「宿魂石(しゅくこんせき)」と呼ばれる巨石が今も祀られています。ここに甕星香々背男が封じられたと伝えられ、星神の畏怖すべき力を伝える神話的痕跡として信仰されています。
広告
日本書紀に見る甕星香々背男
『日本書紀』には、甕星香々背男の存在が「天における悪神」として記されています。その記述を見てみましょう。
原文
一書曰、天神、遣經津主神・武甕槌神、使平定葦原中國。時二神曰「天有惡神、名曰天津甕星、亦名天香香背男。請先誅此神、然後下撥葦原中國。」
書き下し文
一書に曰(いは)く、天神、経津主神(ふつぬしのかみ)・武甕槌神(たけみかづちのかみ)を遣(つか)はして、葦原中国(あしはらのなかつくに)を平定(たいら)げしむ。時に二神(ふたはしらのかみ)曰はく、「天に悪しき神有り。名を天津甕星(あまつみかぼし)と曰ひ、亦(また)の名を天香香背男(あめのかがせお)と曰ふ。請(こ)ひて先づ此の神を誅(う)ちて、然る後に葦原中国に下撥(しず)めむ。」とのたまふ。
現代語訳
ある伝えにこうある。天神は経津主神と武甕槌神を遣わして、葦原中国を平定させようとした。すると二神は申し上げた。「天には悪しき神がいます。その名は天津甕星、またの名を天香香背男といいます。まずこの神を討ち滅ぼし、その後に葦原中国を平定したいと存じます。」
広告
星の神としての性格
甕星香々背男は、多くの研究者により「金星(明星)の神」と考えられています。金星は明けの明星として夜明け前の空に強く輝き、また宵の明星として日没後の空に存在感を放つ星であり、古代人にとって特別な畏敬の対象でした。
中国神話における「太白(たいはく=金星の神)」と同一視されることもあり、大陸文化の影響を受けつつ、日本で独自に神格化された可能性があります。
広告
甕星香々背男を祀る神社
甕星香々背男は、日本全国で広く祀られているわけではありませんが、いくつかの神社でその名を見ることができます。特に、関東地方を中心に信仰が伝えられています。
大甕(おおみか)神社|茨城県日立市
大甕神社(おおみかじんじゃ)は、茨城県日立市大みか町にある神社で、御祭神として、主神は武葉槌命(たけはつちのみこと)、地主神として甕星香々背男(みかぼしかがせお)をお祀りしています。大甕神社の社伝によると、甕星香々背男は常陸国の大甕山を中心として東国を支配していたと伝わっています。
鹿島神(武甕槌神)と香取神(経津主神)の二柱の神が、国津神をはじめ草木や石に至るまで次々と平定していったものの、ただ一つ、甕星香々背男と呼ばれる星の神だけは屈服させることができませんでした。そこで両神に代わり、大甕の地へ赴き、地主神の霊威を宿した宿魂石にその力を封じたのが、倭文神・武葉槌命であったと伝えられています。
大甕神社(茨城県日立市) 最強のお守り・縁切りのパワースポット
星神社|愛知県名古屋市
名古屋市西区に鎮座する星神社は、大己貴命を主祭神とし、天香香背男神・牽牛星・織女星を合祀する由緒ある神社です。平安時代の延喜式神名帳に坂庭神社として記され、また「酒庭星社」とも呼ばれ、七夕の星祭では土壇を築いて酒を供える古い祭祀が行われてきました。仁和年間には大江一族が深く信仰し社殿を再興、さらに南北朝期には藤原実秋が社殿や楼門を復興させています。戦国時代には信長公の時代まで社領を有しましたが、太閤期に没収されました。地名「小田井」も当社の歴史と結びついており、今も地域と星祭の伝統を伝える神社です。
広告
ご利益
甕星香々背男は星の神として、方位や天体の運行にまつわるご利益があるとされています。とりわけ戦勝祈願や邪気祓いの神格が強く、古代には「敵対する者を屈服させる力」を持つ神として崇められました。また、金星の神格から、恋愛や縁結び、芸能・美に関わるご利益を求める信仰も生まれています。
広告
まとめ
甕星香々背男(ミカボシカガセオ)は、日本神話において最後まで天津神に抵抗した最強の神として登場します。その異名「天津甕星」「天香香背男」は、金星の輝きを神格化したものであり、古代人にとって特別な畏怖の対象でした。現在でも星宮神社をはじめとする一部の神社で祀られ、戦勝や邪気祓い、さらには縁結びや芸能のご利益を授ける神として信仰を集めています。