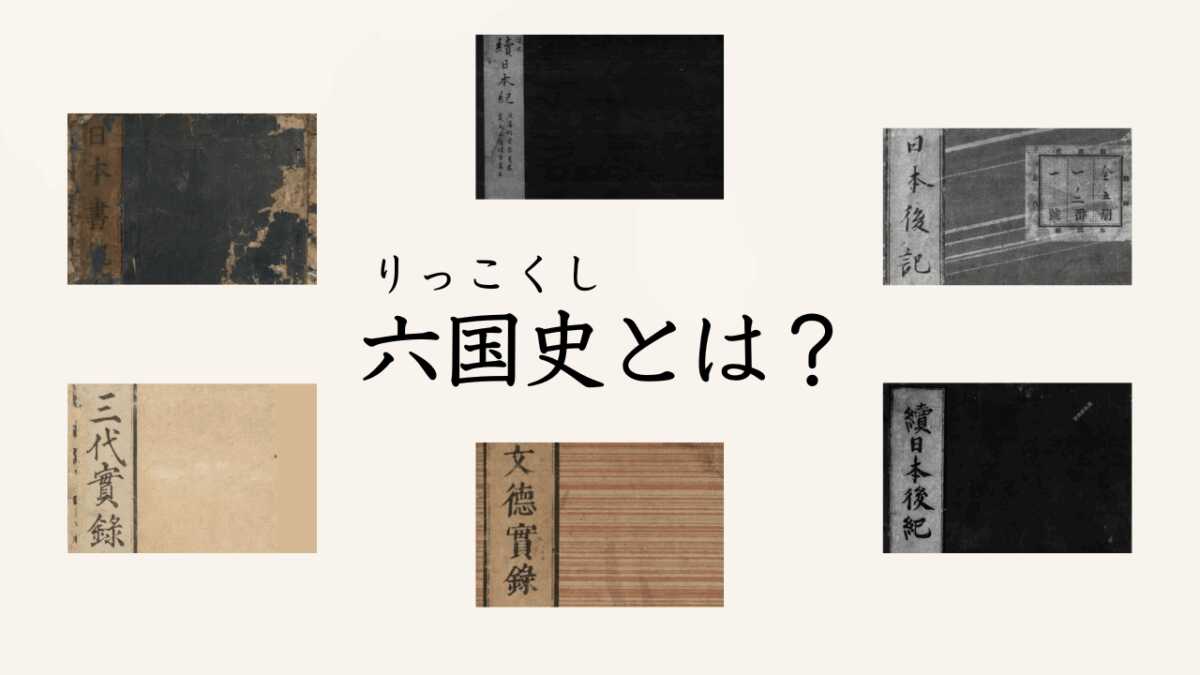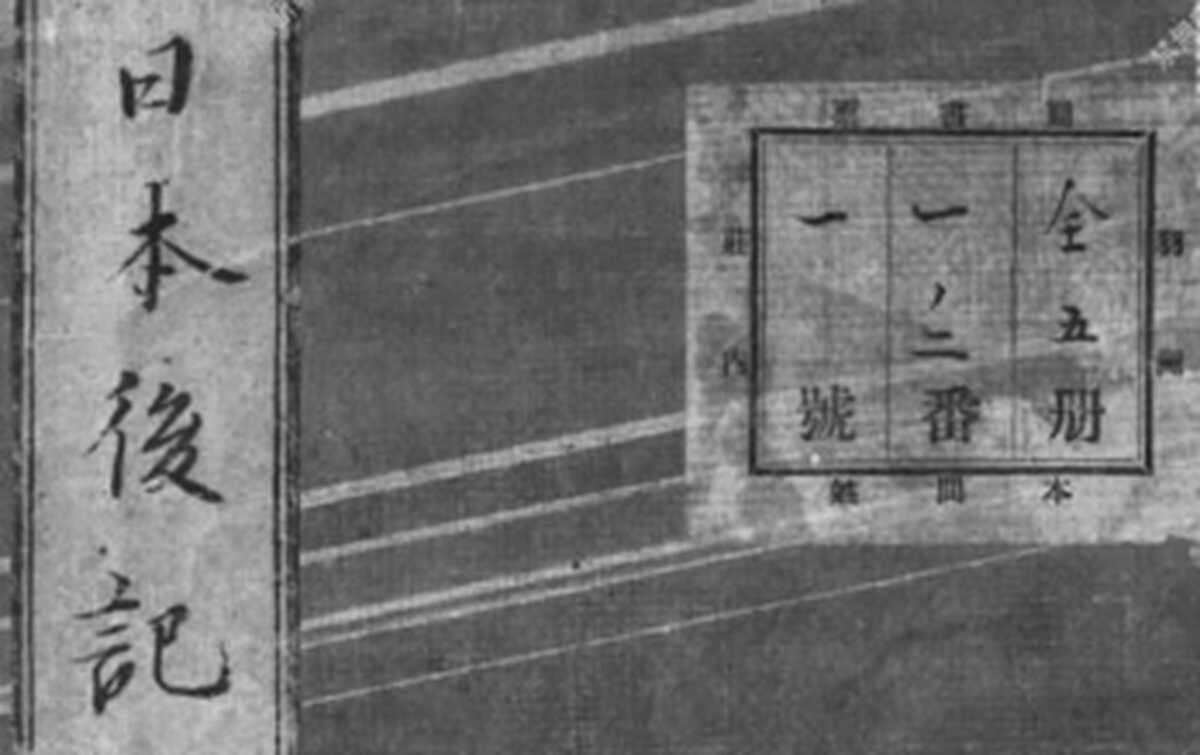
『日本後紀(にほんこうき)』は、六国史の第三にあたる勅撰国史で、奈良時代の後期から平安初期にかけての歴史を記録した書物です。桓武天皇の即位(781年)から淳和天皇の治世末(833年)までの52年間を扱い、政治や外交、宗教、災害など幅広い記録が残されています。奈良時代から平安時代へと移り変わる時期の重要な史料であり、特に桓武天皇による平安京遷都や蝦夷討伐の記録は日本史において大きな意味を持っています。本記事では、『日本後紀』の編纂背景や特徴、具体的な記述を原文と現代語訳を交えて紹介していきます。
広告
日本後紀の編纂と背景
『日本後紀』は、840年に完成しました。編纂にあたったのは藤原緒嗣をはじめとする貴族たちで、文体は中国の史書に倣った漢文体です。六国史の中では初めて「勅命により編纂されたこと」が明確に記録されており、国家的事業としての性格が一層強まりました。この時期は律令国家体制が動揺し、仏教勢力の影響が政治に色濃く及んだ時代でもあります。
『日本後紀』はそうした奈良後期~平安初期の時代の政治的緊張や社会変動を映し出しているといえるでしょう。
六国史(りっこくし)とは?
六国史(りっこくし)とは、奈良時代から平安時代にかけて編纂された日本の正史(勅撰国史書)の総称です。『日本書紀』から『日本三代実録』までの6つの歴史書を指し、天皇の命によって国家事業として編まれました。中国の正史を手本にしながら、日本独自の歴史叙述を確立した六国史は、当時の政治・社会・文化を知るうえで欠かせない史料となっています。
六国史は以下の6つで構成されており、それぞれ扱う時代が異なります。
| 国史名 | 編纂年代 | 内容の対象時期 | 時代区分 |
|---|---|---|---|
| 日本書紀 | 720年 | 神代~持統天皇(697年) | 奈良時代初期に編纂、神話から律令国家成立まで |
| 続日本紀 | 797年 | 文武天皇(697年)~桓武天皇(791年) | 奈良時代全般 |
| 日本後紀 | 840年 | 桓武天皇(781年)~淳和天皇(833年) | 奈良後期~平安初期 |
| 続日本後紀 | 869年 | 仁明天皇(833年)~文徳天皇(850年) | 平安時代前期 |
| 日本文徳天皇実録 (日本文徳天皇實録) |
879年 | 文徳天皇(850年~858年) | 平安時代前期 |
| 日本三代実録 (日本三代實録) |
901年 | 清和天皇(858年)~光孝・宇多・醍醐天皇(887年) | 平安時代前期 |
広告
記録されている時代の流れ
『日本後紀』が対象とする時代は、奈良から平安へと移る大きな転換期でした。
| 天皇 | 在位期間 | 主な出来事 |
|---|---|---|
| 桓武天皇 | 781~806年 | 平安京遷都、蝦夷征討(坂上田村麻呂の活躍)、長岡京遷都の混乱 |
| 平城天皇 | 806~809年 | 病を理由に譲位、嵯峨天皇へ政権移譲 |
| 嵯峨天皇 | 809~823年 | 弘仁格式の整備、空海・最澄による仏教の発展 |
| 淳和天皇 | 823~833年 | 行財政の改革を試みるが、律令国家の衰退傾向が顕著化 |
広告
日本後紀に見える出来事
平安京遷都の記録
『日本後紀』には、桓武天皇が長岡京から平安京へ遷都した経緯が記されています。遷都は国家の安定を願うと同時に、怨霊や不吉を避ける意味も含まれていました。
蝦夷征討と坂上田村麻呂
阿弖流為や母礼を率いる蝦夷との戦いも記録され、坂上田村麻呂が征夷大将軍として東北経営にあたったことが描かれています。これは後の日本の東北支配の始まりを告げる出来事でした。
仏教の影響
嵯峨天皇期には、空海や最澄が登場し、真言宗や天台宗の基礎が築かれます。仏教が国家と密接に結びつき、文化・政治に大きな影響を及ぼしていた様子がうかがえます。
広告
原文・書き下し・現代語訳の例
原文(漢文)
「延暦十三年、遣将軍坂上田村麻呂、征討蝦夷。」
書き下し文
「延暦十三年、将軍坂上田村麻呂を遣わして、蝦夷を征討す。」
現代語訳
「延暦十三年(794年)、将軍の坂上田村麻呂を派遣して蝦夷を討伐させた。」
このように、『日本後紀』は軍事・政治・宗教など幅広い分野を記録しており、時代の生きた証言としての役割を果たしています。
日本後紀の原文は、国書データベース
広告
日本後紀の特徴
『日本後紀』は、国家の公式記録としての正史である一方、天皇を中心とした理想的な政治像を描こうとする側面もあります。そのため、必ずしも中立的ではなく、政治的意図が反映されているといえるでしょう。しかし同時に、自然災害や社会不安なども記録されており、古代日本の現実を知る上で欠かせない史料です。
広告
まとめ
『日本後紀』は、奈良時代後期から平安初期にかけての日本を記録した勅撰国史であり、六国史の第三に位置づけられます。平安京遷都や蝦夷征討、仏教の発展といった大きな出来事が詳細に残されており、政治と宗教、社会の姿を多角的に伝えています。原文に触れることで、平安初期の息づかいをより深く感じることができるでしょう。