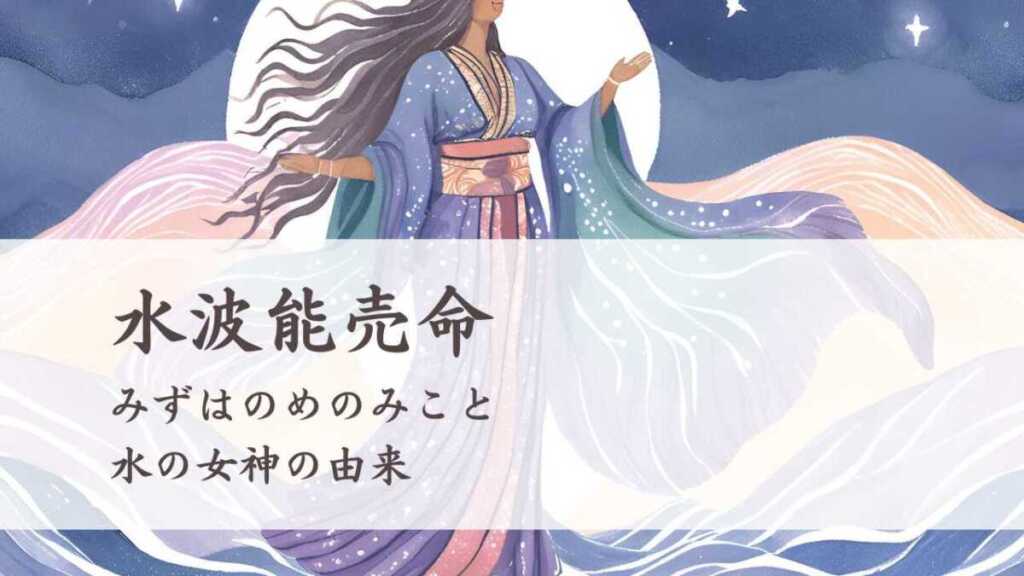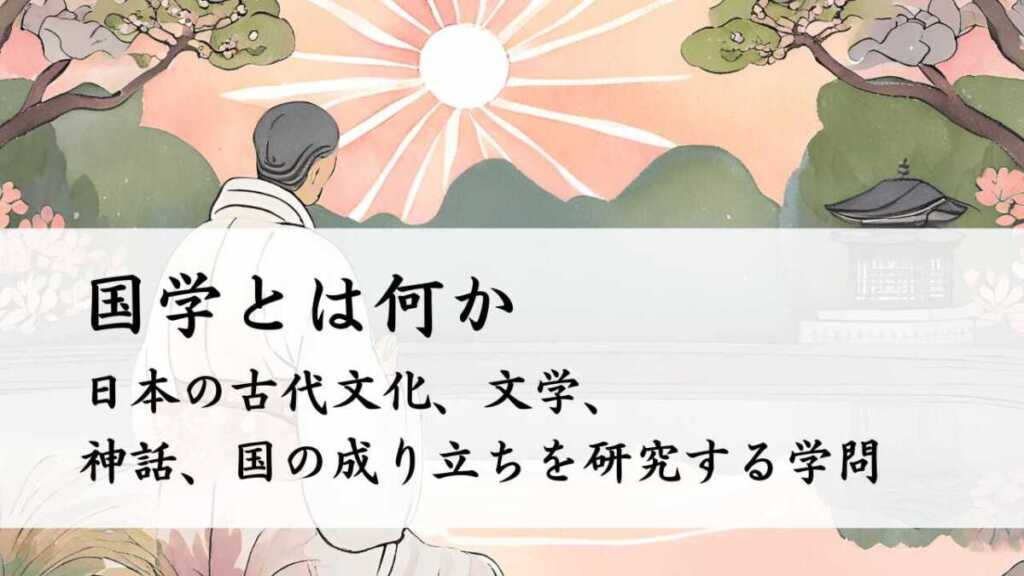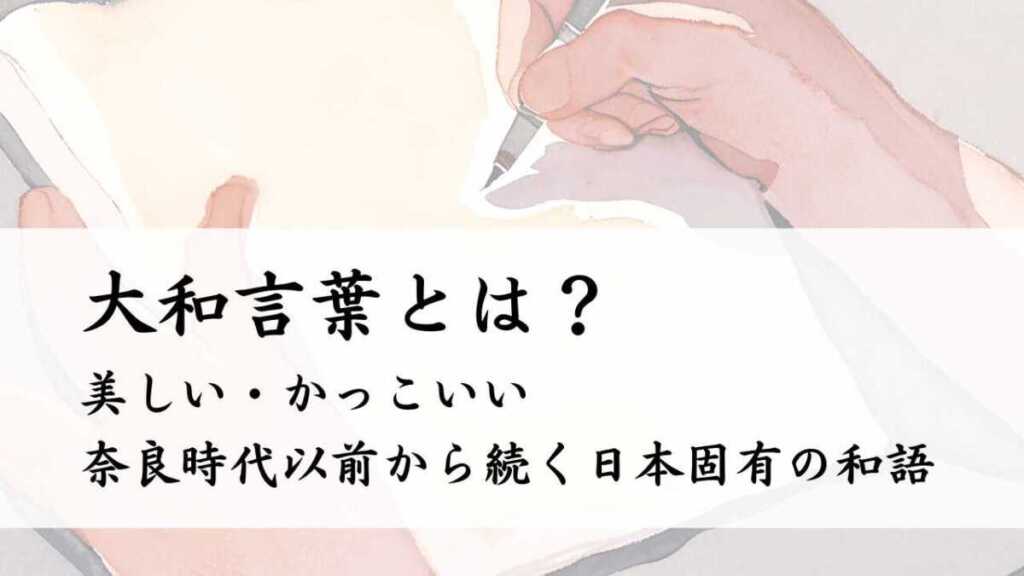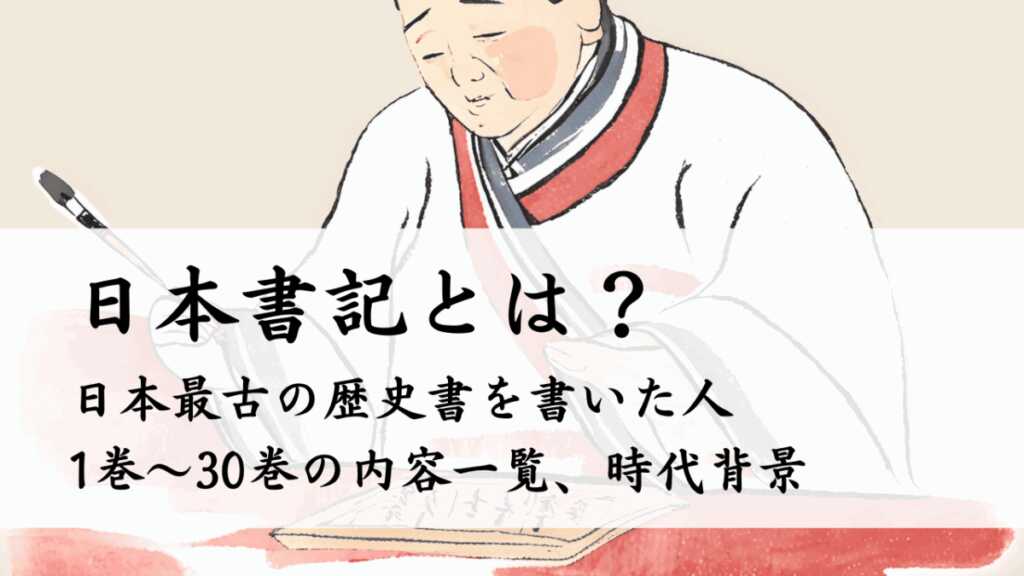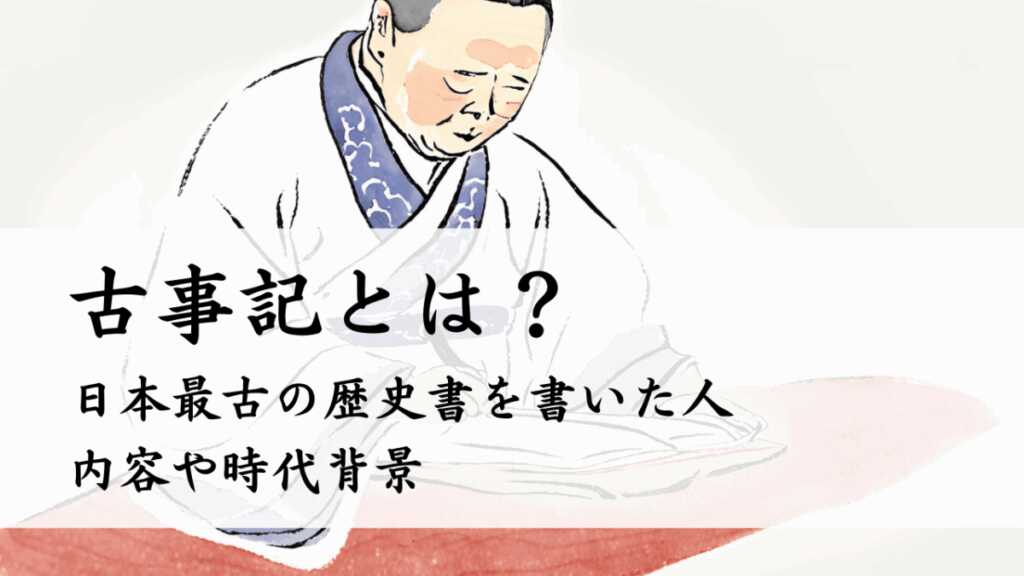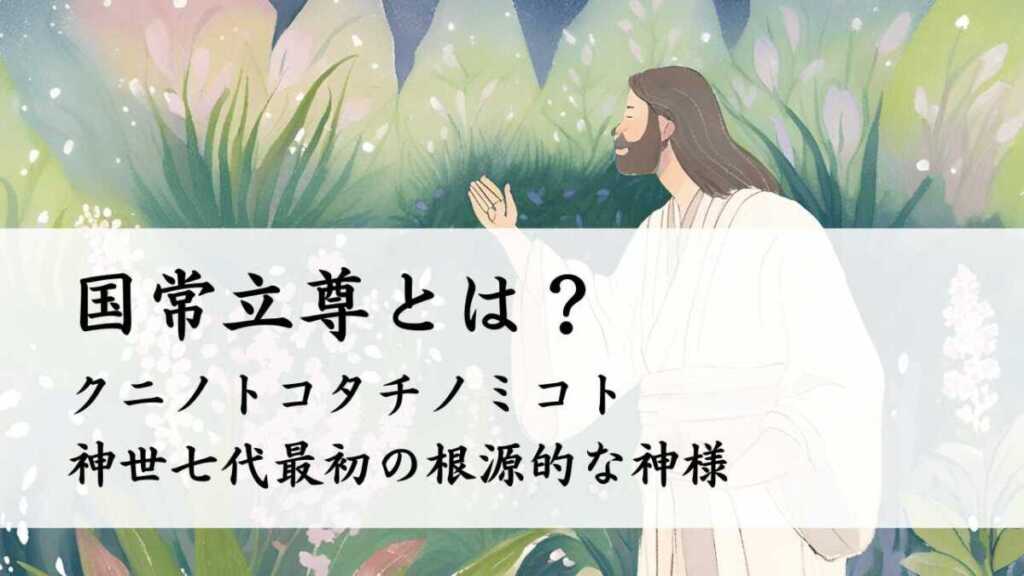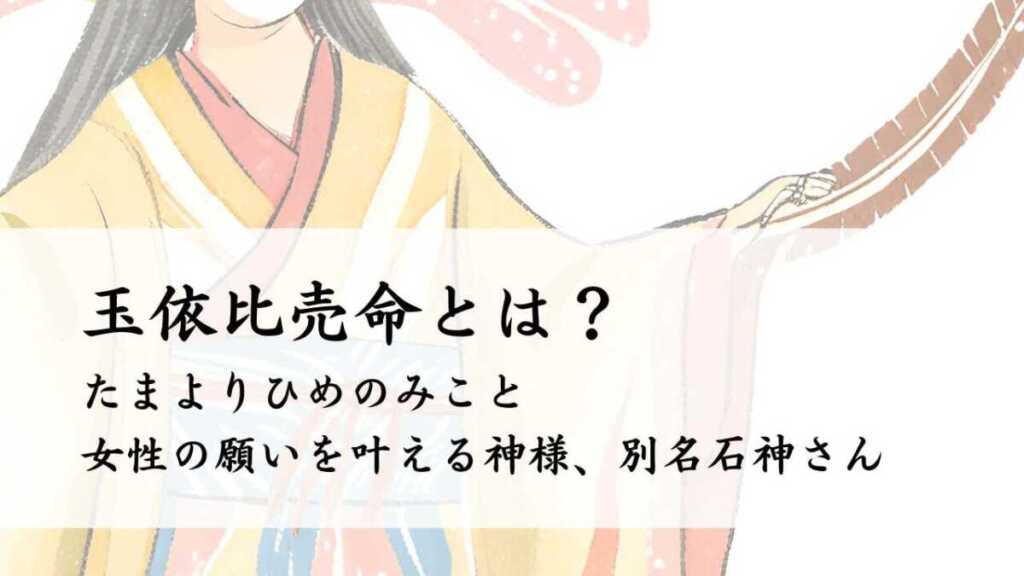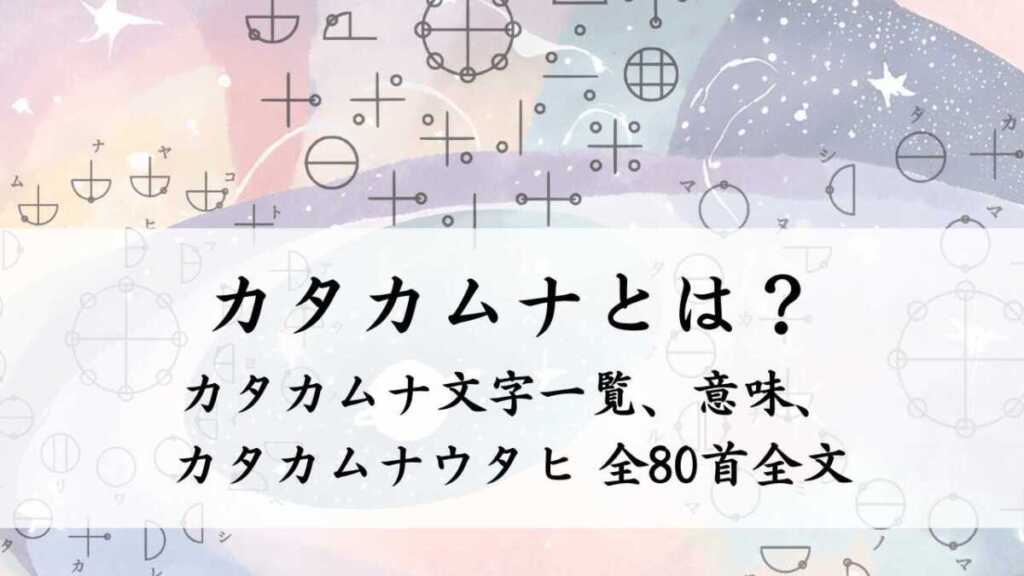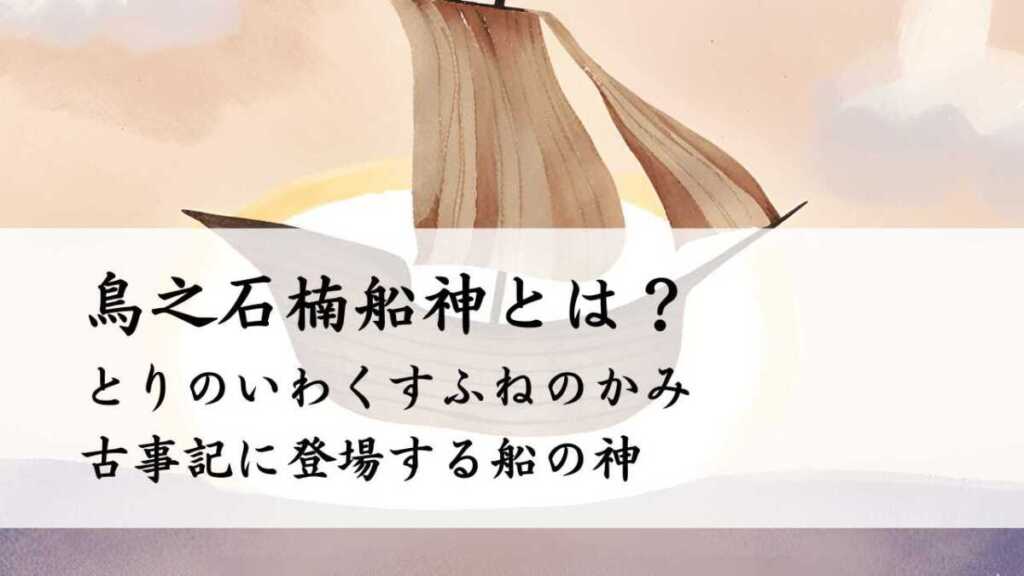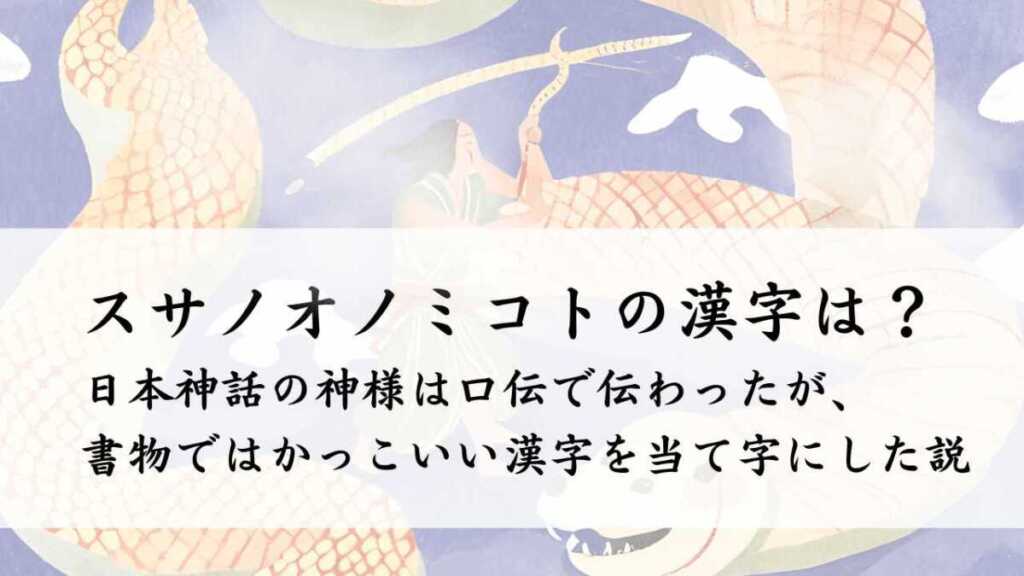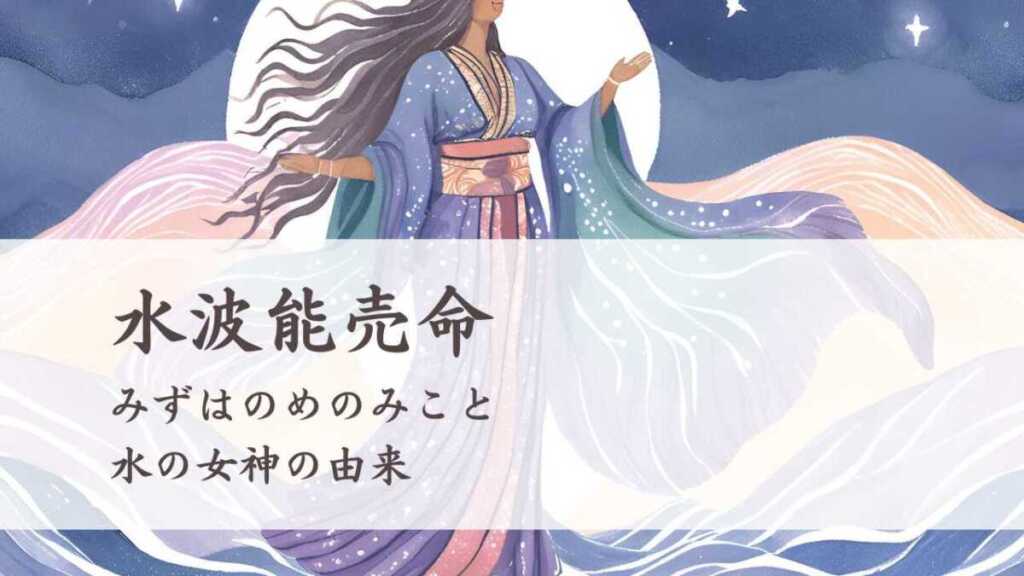
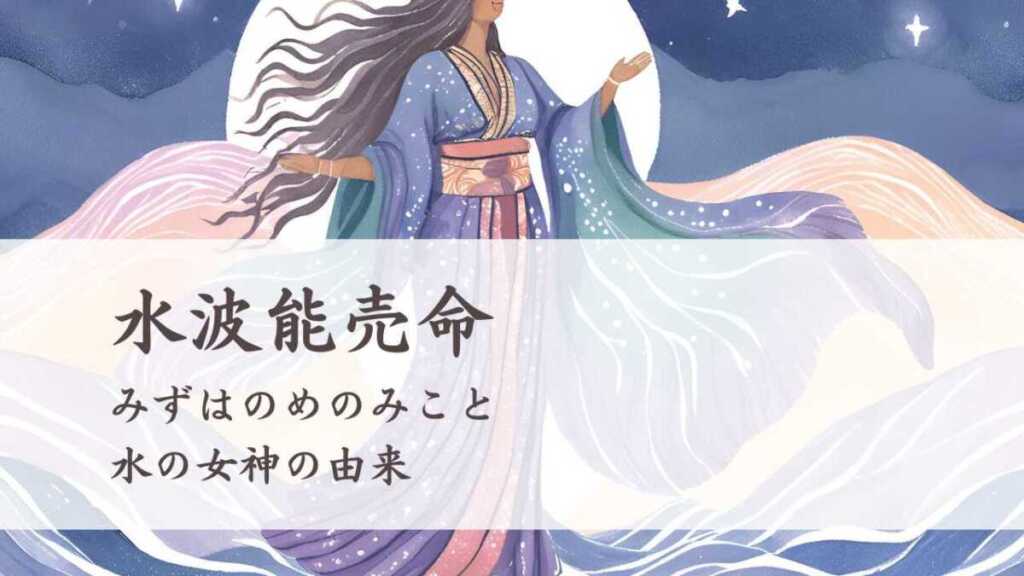
古事記(こじき)は、日本最古の歴史書とされる書物で、奈良時代の712年(和銅5年)に太安万侶(おおのやすまろ)によって編纂されたものです。
その内容は、神話や伝承、天皇の系譜など多岐にわたり、日本の成り立ちと天皇家の由来を語ることを目的としてまとめられました。書名の古事記とは「いにしえの事を記す」という意味であり、古代日本の世界観や価値観を今に伝える貴重な文献です。
古事記は全三巻で構成されています。第一巻では天地の開闢(かいびゃく)から始まり、高天原(たかまのはら)に現れた神々の物語が語られます。中でも伊耶那岐命(いざなぎのみこと)と伊耶那美命(いざなみのみこと)による国生み・神生みの神話は有名で、やがて天照大御神(あまてらすおおみかみ)、月読命(つくよみのみこと)、須佐之男命(すさのおのみこと)といった重要な神々が登場します。これらの神話は、自然や人の営みに神が宿るという日本独自の自然観・宗教観の基礎となっています。
第二巻では、初代神武天皇から第十五代応神天皇までの系譜が描かれています。ここでは、神々の子孫としての天皇がどのように地上世界を統治するようになったのかが語られ、神話から歴史への橋渡しのような構成となっています。第三巻では、応神天皇の後を継ぐ仁徳天皇から推古天皇までの系譜が記され、天皇家の血統の継承や治世に関する出来事が記録されています。
古事記は、稗田阿礼(ひえだのあれ)という人物が口承していた帝紀(ていき)と旧辞(きゅうじ)を、太安万侶が筆録したとされています。文体は漢字を使いながらも日本語で読むことを前提とした独特の表記がなされており、日本語の起源や古代語を研究するうえでも極めて重要な資料です。
また、古事記は単なる歴史書ではなく、神道の基礎となる神話体系を示した書物でもあり、現在でも多くの神社でその内容が御由緒や祭祀の根拠として用いられています。日本の伝統文化や精神性を理解するうえで欠かすことのできない、日本文化の原点ともいえる書物です。