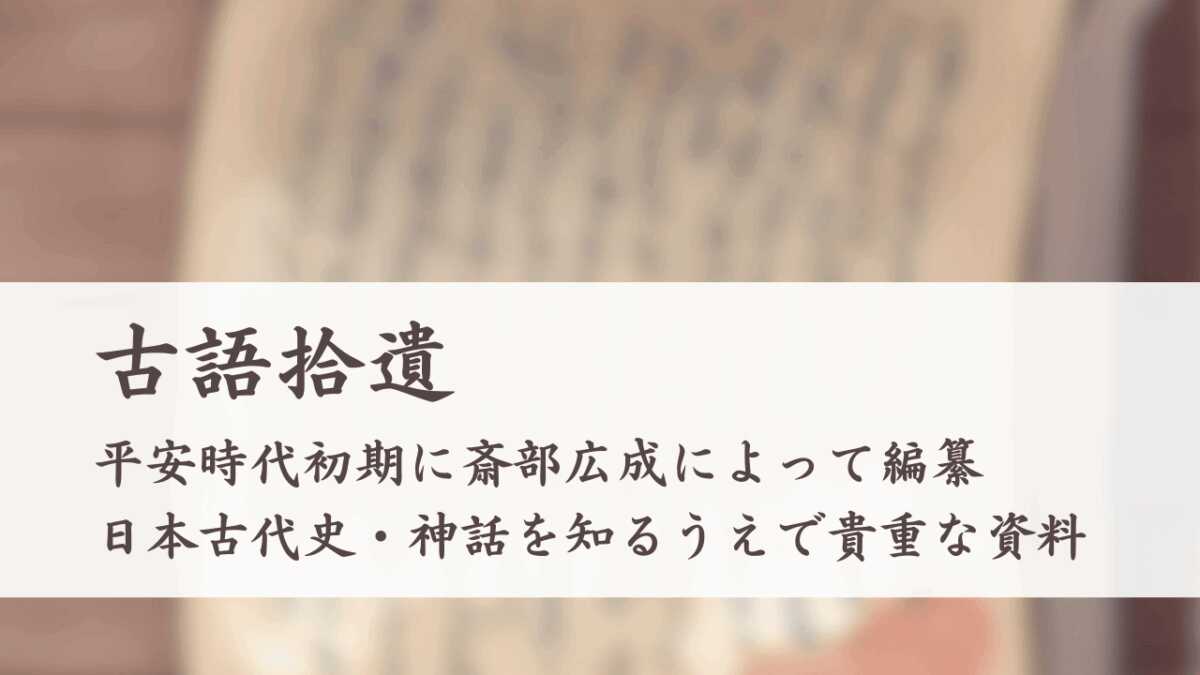
『古語拾遺(こごしゅうい)』は、古事記・日本書紀と並ぶ日本古代の重要な歴史書のひとつで、807年(大同2年)に斎部広成によって編纂されました。神道祭祀に深く関わる斎部氏の視点から、神話や神宝の由来、祭祀の詳細が記録されており、他の史書には見られない貴重な伝承が数多く含まれています。本記事では、『古語拾遺』が成立した背景やその内容を解説するとともに、原文と現代語訳の一例を紹介し、その魅力と意義に迫ります。
広告
古語拾遺とは?内容の原文や現代語訳
『古語拾遺(こごしゅうい)』は、平安時代初期に成立した歴史的な文献で、古事記や日本書紀と並ぶ日本古代史・神話を知るうえで貴重な資料のひとつです。特に神祇(じんぎ)祭祀の伝承や、神話の異説、祝詞の用例などが数多く記されており、神道や宮廷祭祀の研究において重要な文献とされています。
広告
古語拾遺の成立と作者
『古語拾遺』は、平安時代初期の807年(大同2年)に、斎部広成(いんべのひろなり)によって編纂されました。斎部氏は古代の祭祀を司る家系であり、中臣氏(後の藤原氏)と並び、神祇官に深く関わる氏族です。
この書物は、当時の朝廷において斎部氏の地位が低下しつつある中で、自らの家系の正統性と神事における役割を主張する目的で編まれました。古事記や日本書紀とは違い、神祇官の内部事情や儀礼の詳細、そして祝詞の原型に近い表現が見られる点が大きな特徴です。
広告
古語拾遺の構成と特徴
古語拾遺は一巻構成で、以下のような内容が記されています。
- 日本神話に関する補足的な伝承
- 祭祀における斎部氏の役割と功績
- 天孫降臨神話における神々の随行者一覧
- 古代の神事や祝詞の文言の解説
- 斎部家に伝わる神宝や神具の由来
古事記や日本書紀に記されていない神話の一節や、異なる系譜、神事の詳細が収められており、「神話三部作」の補完的な立ち位置を担っています。
広告
原文の一部とその現代語訳
ここでは『古語拾遺』の有名な一節、「天孫降臨(てんそんこうりん)」に関わる部分を取り上げ、その原文と現代語訳を紹介します。
原文(抜粋)
時に、天照大神、斎部の遠祖天太玉命を以て神宝を捧げ奉らしむ。即ち、鏡、玉、剣を始めとして、亦種種の神宝を授け賜ふ。
現代語訳
その時、天照大御神は、斎部氏の祖先である天太玉命に命じて、神々の宝を捧げさせた。まずは鏡・玉・剣をはじめ、さまざまな神宝を授けたのである。
このように、『古語拾遺』では斎部氏の祖神・天太玉命が、神宝の奉納という重要な役割を果たしていたことが強調されています。これは同時代の他書ではそれほど重視されていない部分であり、斎部氏による自家の祭祀的地位の主張が読み取れます。
広告
古語拾遺の価値と現代での意義
古語拾遺は、単なる神話書ではなく、神道の実務・神事の伝統・古代社会における氏族の役割を記録した実用的な文献でもあります。そのため、歴史学者や神道学の研究者だけでなく、神職や祭祀を学ぶ人々にとっても必読の資料となっています。
また、現代の祝詞(のりと)や神道儀礼の中には、『古語拾遺』に起源をもつ表現や所作が多く残っており、日本文化の精神的基盤を知るうえでも極めて重要です。
広告
まとめ
古語拾遺は、807年に斎部広成によって編まれた、日本神話と神道祭祀の伝承を記録した貴重な歴史文書です。『古事記』や『日本書紀』とは異なる視点から、日本の神々や神事に関する情報が記されており、特に斎部氏の祭祀的地位や功績を強調しています。
現代語訳を通してその内容に触れることで、私たちは古代の人々がどのように神と共に生きてきたのかを深く理解することができます。歴史や神話を学ぶ上で、『古語拾遺』は今もなお新たな視点を与えてくれる重要な鍵と言えるでしょう。





