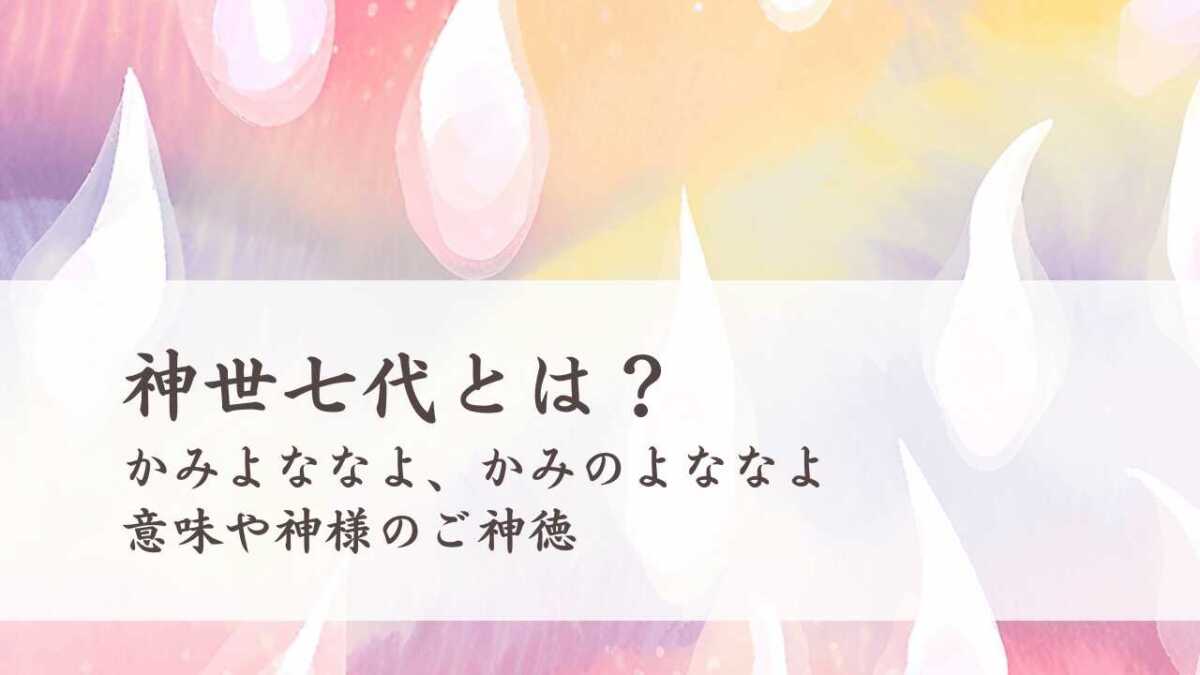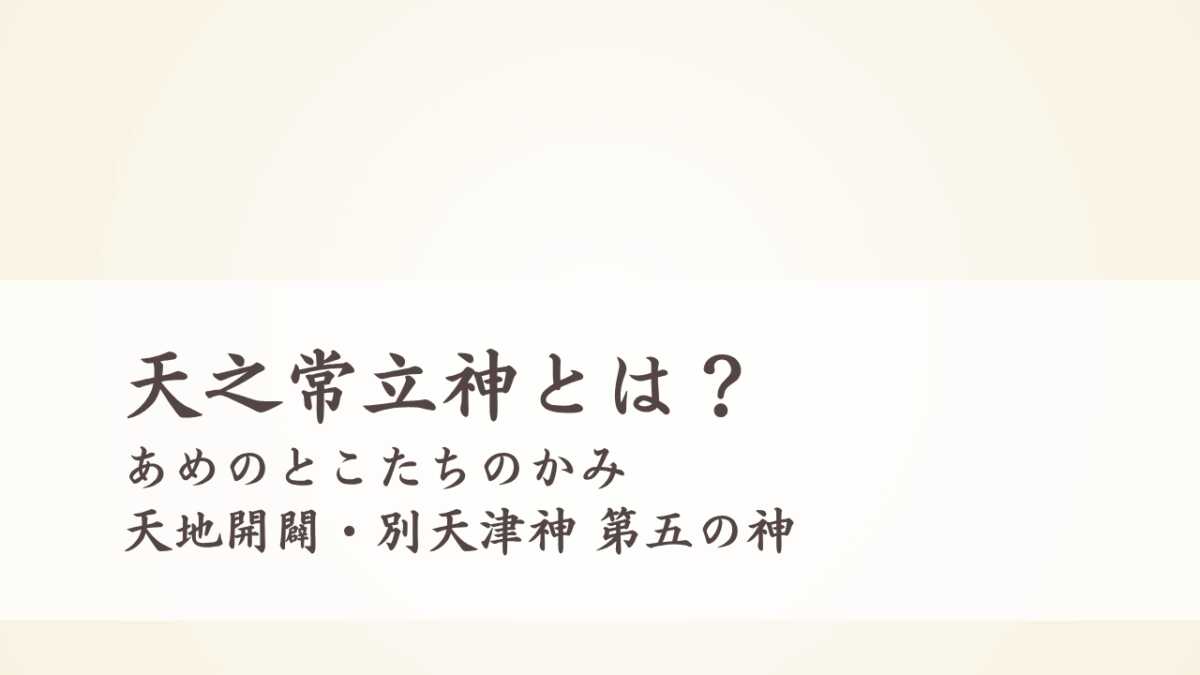
天之常立神(あめのとこたちのかみ)とは、『古事記』や『日本書紀』に記される天地開闢(てんちかいびゃく)の際に現れた神であり、最初に生まれた五柱の神々「別天津神(ことあまつかみ)」の第五の神です。その名にある「常立(とこたち)」は、天地が安定し、永遠に変わらぬ秩序が保たれることを意味します。天之常立神は、天地が形を成したのち、その秩序を確立し支える存在として、宇宙の根本原理を象徴しています。本記事では、天之常立神の登場背景や役割、『古事記』『日本書紀』における描かれ方、信仰の広がりまでを詳しく解説します。
広告
天之常立神(あめのとこたちのかみ)とは?
天之常立神(あめのとこたちのかみ)は、日本神話において天地開闢(てんちかいびゃく)のときに現れた神々のひと柱であり、「別天津神(ことあまつかみ)」と呼ばれる最初の五柱の神のうちの第五にあたります。
名の「常立(とこたち)」には「永遠に立つ」「変わらぬ秩序を保つ」という意味があり、天地が安定し、世界が秩序をもって存在し始めたことを象徴しています。天之常立神は、天地開闢の神々の中でも特に「地の安定」と「永続する世界の基盤」を司る存在とされています。
広告
天地開闢と別天津神の中での位置づけ
天地開闢とは、天と地が初めて分かれ、世界が形成された出来事を指します。『古事記』ではこのとき、五柱の神々が順に現れ、これを「別天津神」と呼びます。その順序と役割は以下の通りです。
| 順番 | 神の名前 | 読み方 | 意味・役割 |
|---|---|---|---|
| 第一柱 | 天之御中主神 | あめのみなかぬしのかみ | 宇宙の中心・根源神。天地のはじまりを司る。 |
| 第二柱 | 高御産巣日神 | たかみむすひのかみ | 天上界の生成力を象徴する創造神。 |
| 第三柱 | 神産巣日神 | かみむすひのかみ | 地上世界の生成力を象徴する創造神。 |
| 第四柱 | 宇摩志阿斯訶備比古遅神 | うましあしかびひこぢのかみ | 天地の分化が進む力を象徴する神。 |
| 第五柱 | 天之常立神 | あめのとこたちのかみ | 天地が安定し、世界が秩序をもって存在することを示す神。 |
天之常立神は、この五柱の神々の最後に現れた存在であり、天地創造の初期段階の「混沌」から「安定」への移行を象徴しています。つまり、天之常立神の出現は、天地が分かれるだけでなく、それが「恒久的な秩序」として保たれるようになったことを意味しているのです。
広告
『古事記』と『日本書紀』における天之常立神の描写
『古事記』では、天地が初めて開けたとき、五柱の神が順に出現し、その最後として天之常立神が登場します。
本文では「次に天之常立神成り坐す」と記されており、この「成り坐す(なりまします)」という言葉には「自然に成り現れる」という意味があります。これは、天之常立神が人間的な意志によって生まれたのではなく、天地そのものの秩序の中から自然発生的に現れた存在であることを示しています。
一方、『日本書紀』では、天之常立神の登場位置が異なり、第一に現れる神とされる場合もあります。
これは、『日本書紀』が陰陽思想など中国古代哲学の影響を強く受け、天地開闢を理論的に構築した結果とみられています。『日本書紀』では、天之常立神が「天の常なる原理」を象徴する存在として冒頭に置かれることで、宇宙の秩序の永続性を表しているのです。
広告
「常立」の名に込められた意味
天之常立神の「常(とこ)」は「永遠」「変わらないもの」を意味し、「立(たつ)」は「成立する」「安定して立つ」という意味を持ちます。これを合わせると、「天之常立」とは「天の永遠に変わらぬ秩序」「天地の不動なる安定」を示す言葉と解釈されます。
天地開闢における最初の神々は抽象的で姿を持たない存在でしたが、天之常立神は「天と地が確立したあとの安定」を象徴する神として、他の四神よりも具体的な宇宙構造に関与していると考えられます。これは、天地がただ分かれただけでなく、永続的に保たれる秩序がそこに生まれたことを示す重要な段階です。
広告
天之常立神と国土安泰・基盤の神格
後世において、天之常立神は「国土安泰」や「世界の根源神」として信仰されました。特に平安時代以降、天之常立神は「国の守護神」「天地の基神」として、祈祷や祝詞にその名が登場するようになります。天地が揺らがず、自然が調和し、国が長く栄えることを願う祈りの中で、この神は「とこしえに立つ」神として崇敬されました。
また、天之常立神は天地の境界を象徴する存在でもあり、混沌と秩序、変化と安定の間に立つ神ともいえます。これは日本人の自然観や宗教観における「調和」の思想と深く結びついており、すべての変化の中に「変わらぬ本質」があるという世界観を表しています。
広告
他の神々との関係と神世七代へのつながり
天地開闢の五柱の神々のあとには、「神世七代(かみのよななよ)」と呼ばれる七組の神々が現れます。
これは、より具体的な天地の生成や国土の形成に関わる神々であり、やがて伊邪那岐命(いざなぎのみこと)・伊邪那美命(いざなみのみこと)による国産み神話へとつながっていきます。
天之常立神はその前段階に位置し、神世七代が活動できる基盤となる「天地の安定」「創造の土台」を整えた神とされます。この流れは、神話的時間の中で「抽象から具体へ」「混沌から秩序へ」という生成のプロセスを象徴しており、日本神話の構造的特徴を理解するうえで欠かせないものです。
広告
まとめ
天之常立神(あめのとこたちのかみ)は、天地開闢において現れた五柱の別天津神の第五の神であり、天地が安定し、世界が秩序をもって存在し始めたことを象徴する存在です。その名の通り「常に立つ神」として、永遠不変の秩序と調和を体現しています。『古事記』と『日本書紀』では描写の違いが見られますが、どちらにおいても天之常立神は「天地の根源神」として重要な位置を占めています。
この神が象徴する「常に変わらぬ中心」「天地の安定」は、日本人の精神文化における「和」「調和」「持続」の価値観へと受け継がれ、今もなお静かにその思想的息づきを伝えています。