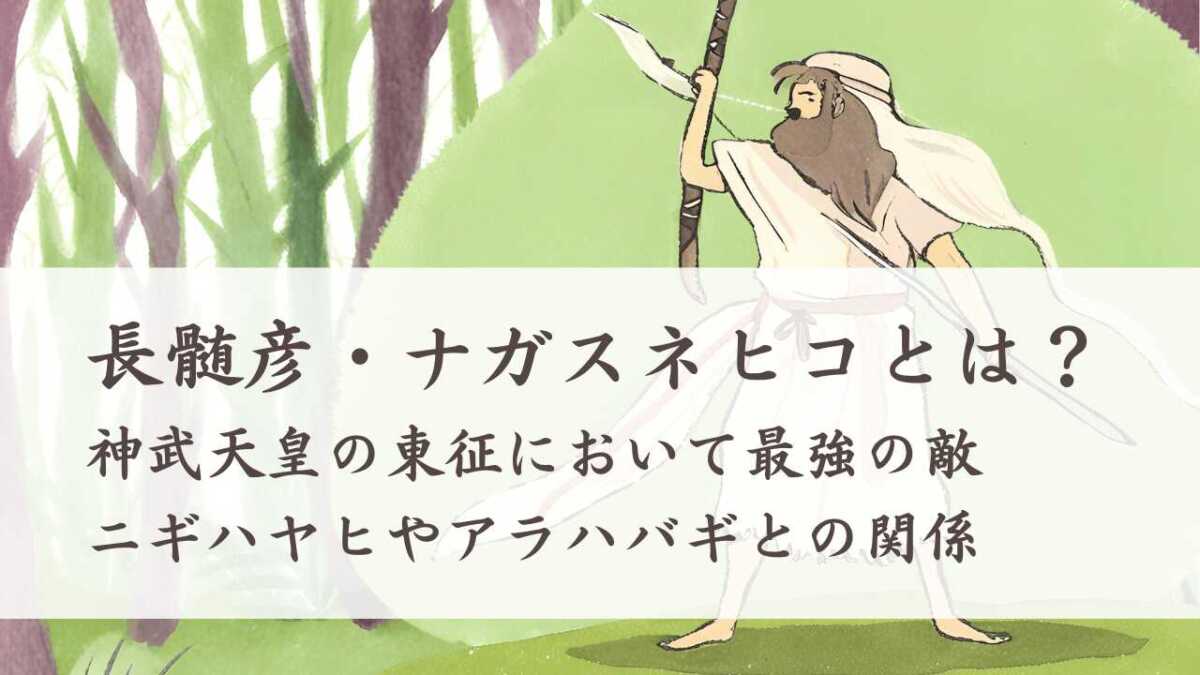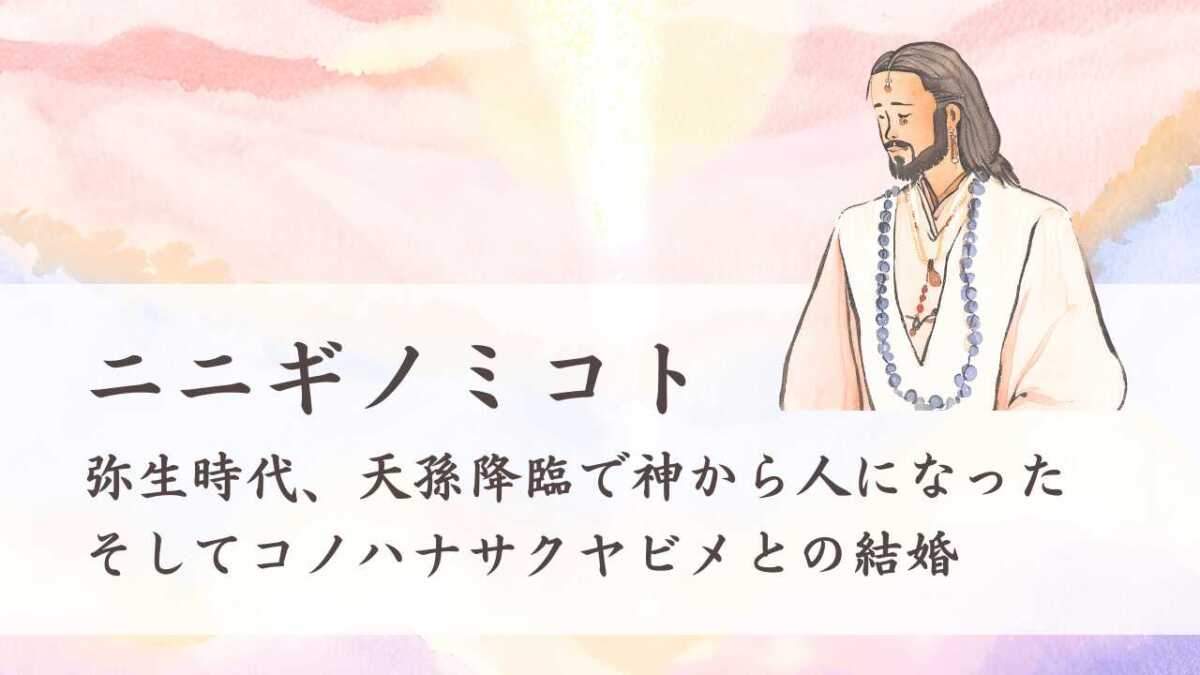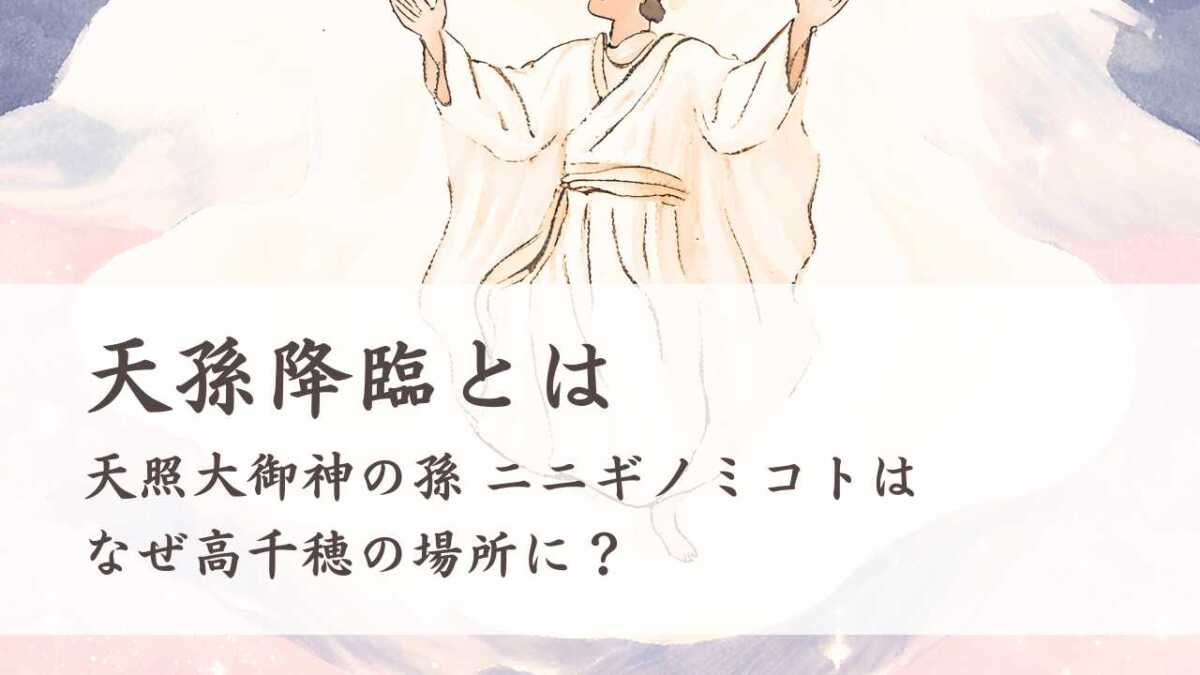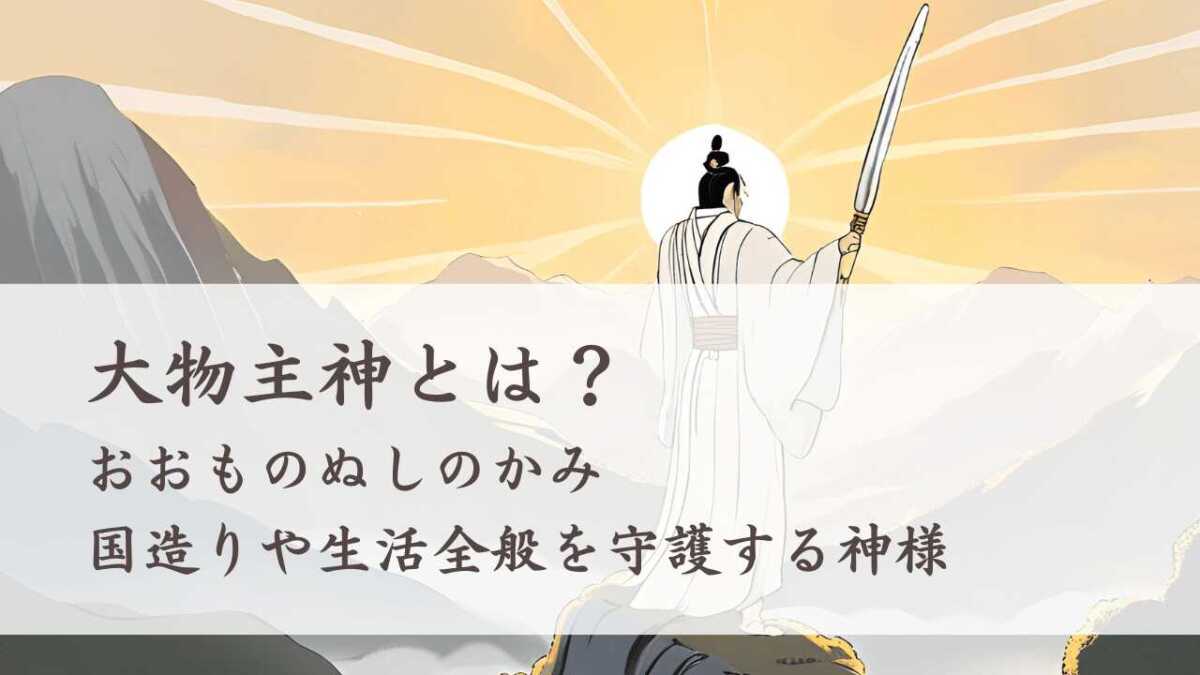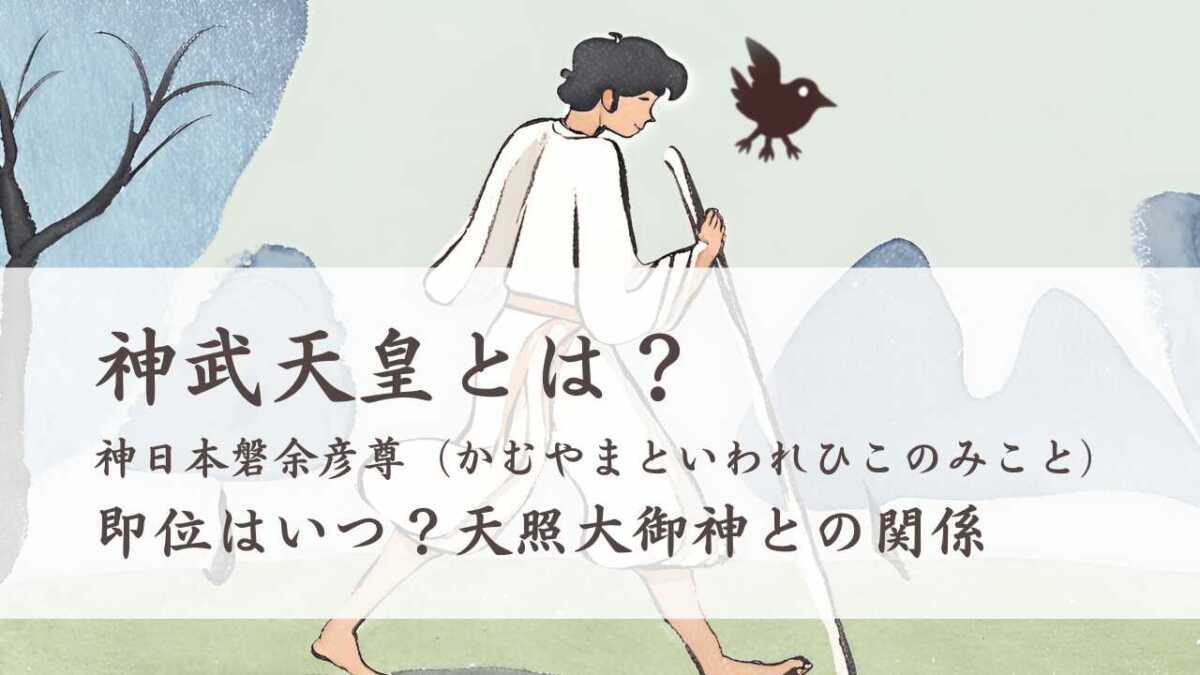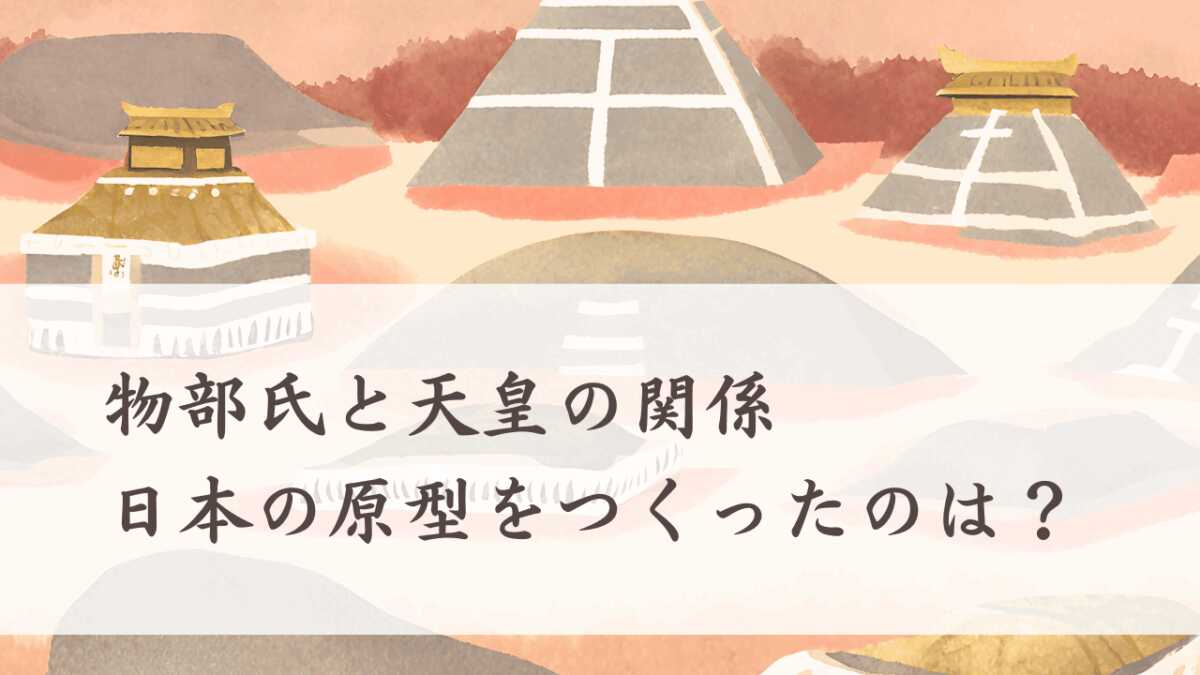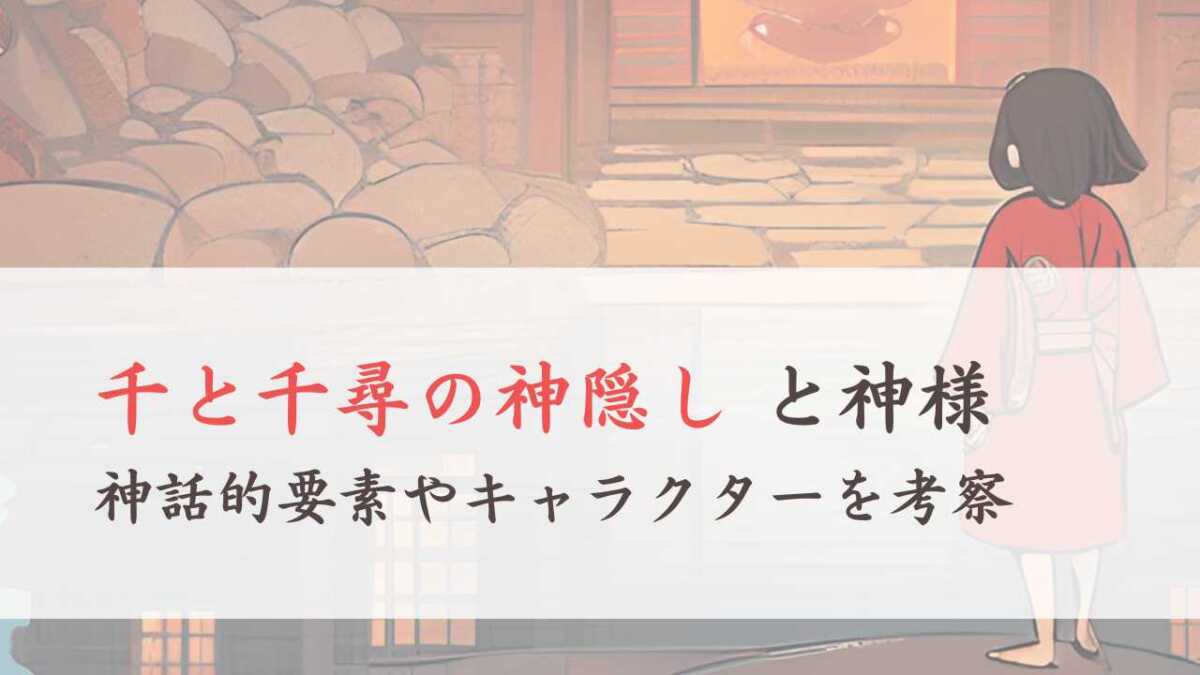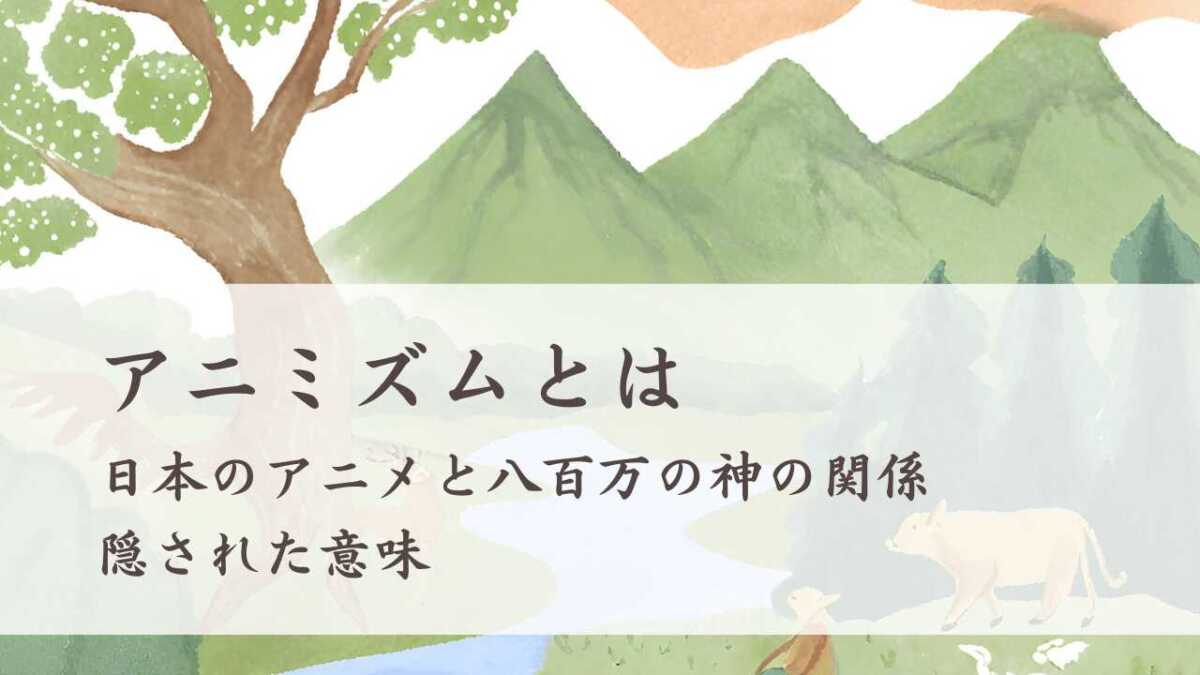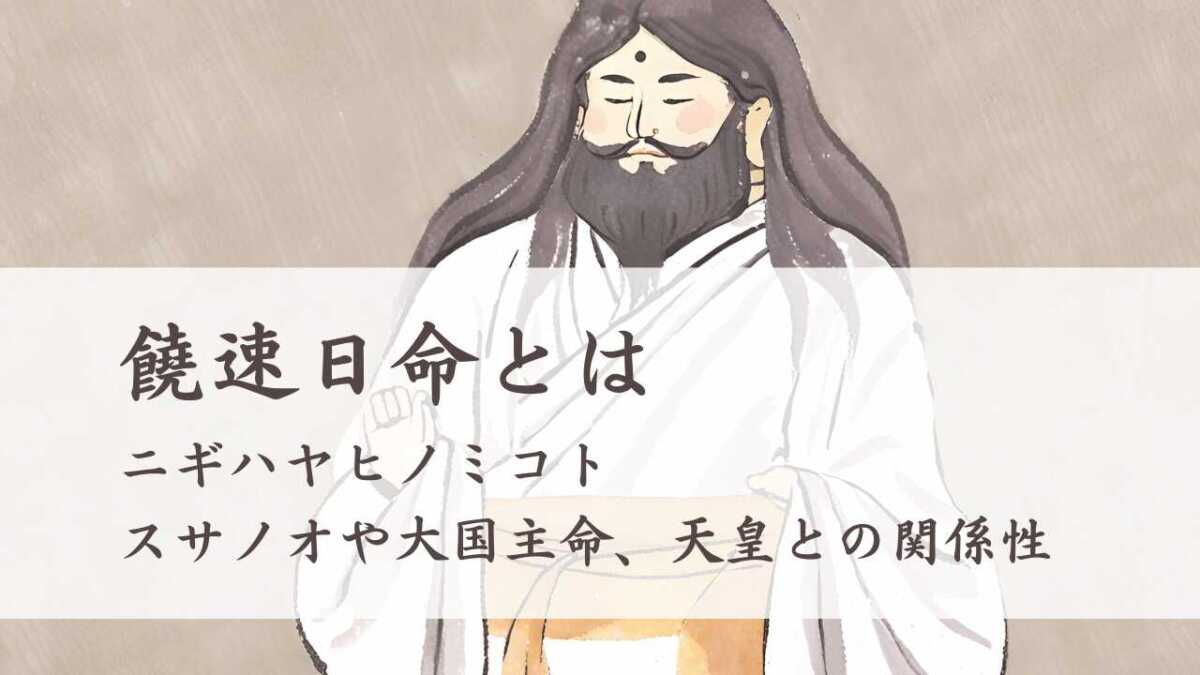
ニギハヤヒ(饒速日命)は、古代日本の神話に登場する重要な神様であり、その存在は多くの伝説や歴史的記録に影響を与えています。彼はスサノオや大国主命との関係性を持ち、特に物部氏の祖先とされています。しかし、天皇家の直系はニニギノミコト(邇邇芸命)を祖先としています。この背景には、神武天皇から続く血筋の正当性を証明するために神話が都合よく変更された可能性も指摘されています。この記事では、ニギハヤヒとはどのような神様か、彼とスサノオや大国主命との関係性について詳しく探ります。
広告
ニギハヤヒとは?
ニギハヤヒ(饒速日命・にぎはやひのみこと)は、日本神話に登場する神で、天孫降臨に関わる重要な存在です。『日本書紀』では天照大御神の命を受けて天磐船(あめのいわふね)に乗り、地上に降臨した神とされています。降臨先は大和国(現在の奈良県)で、物部氏の祖神とされることから、古代豪族との深い関係がうかがえます。
ニギハヤヒは大和の地で土着の勢力と結びつき、長髄彦(ながすねひこ)の妹を妻としました。
しかし、後に神武天皇(カムヤマトイワレヒコ)が東征し、大和を平定しようとすると、ニギハヤヒは自らが神の血統であることを示す「十種神宝(とくさのかんだから)」を掲げ、神武天皇に従いました。これにより、物部氏も天皇家に仕える立場となりました。
ニギハヤヒは、天孫降臨の神々の中でも異質な存在で、天皇家とは別系統ながら天から降りた神としての尊い血筋を持ち、後世の信仰にも影響を与えました。
広告
ニギハヤヒの来歴と役割
ニギハヤヒは、天照大御神の命を受けて天から降り、地上世界を統治するために地上に降臨しました。この降臨は、「天降り(あまくだり)」と呼ばれ、天孫族が地上を支配するための象徴的な出来事とされています。ニギハヤヒは大和地方に降り立ち、その地で天孫族の支配を確立するために努力しました。
広告
ニニギノミコトが天孫降臨したのとニギハヤヒが天降りしたのはどちらが先?
ニギハヤヒ(饒速日命、にぎはやひのみこと)とニニギノミコト(邇邇芸命、ににぎのみこと)のどちらが先に天孫降臨したかについては、『日本書紀』と『古事記』の記述に違いがあります。
『日本書紀』の記述
『日本書紀』には、ニギハヤヒがニニギノミコトより先に天孫降臨したと記されています。具体的には、ニギハヤヒは天照大御神の命を受けて天から降り立ち、大和地方において天孫族の支配を確立したとされています。その後、ニニギノミコトが天孫降臨し、地上世界の支配を拡大するために努力したと記されています。
『古事記』の記述
一方、『古事記』では、ニニギノミコトが先に天孫降臨したとされており、ニギハヤヒの天降りについてはあまり詳しく記述されていません。
『先代旧事本紀』の記述
十種神宝は『古事記』や『日本書紀』には登場せず、「先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ)」という平安時代に編纂された資料にのみ登場します。天照大御神は天孫降臨の際、ニニギノミコトに三種の神器を授け、地上を治める正統性を与えました。一方で、同時期または並行するもう一つの天降り伝承として、饒速日命が天磐船で地上に降り、十種神宝を授かったという伝承が登場します。
天皇家と中臣・藤原氏が中心の『日本書紀』に対して、『先代旧事本紀』は物部氏や尾張氏など別系統の豪族を正当化する目的があったため、十種神宝は三種の神器に対抗または補完する性質を持って語られたとも考えられています。
広告
スサノオとの関係
スサノオ(須佐之男命、すさのおのみこと)は、ニギハヤヒの先祖にあたる神様であり、出雲地方を中心に崇拝されています。スサノオは、天照大御神の弟であり、海や嵐の神として知られています。彼は出雲の国を支配しており、その子孫が大国主命(おおくにぬしのみこと)です。ニギハヤヒは、スサノオの後裔として、天孫族の一員として地上に降り立ったとされています。この関係性は、天孫族と国津神(地上の神々)との融合を示しています。
広告
大国主命との関係
大国主命は、スサノオの子孫であり、出雲地方を中心に信仰される国造りの神です。彼は、地上世界の統治者として多くの神話に登場します。ニギハヤヒは、大国主命が統治していた地域に天孫族の一員として降臨し、大国主命の支配下にある地を統治しました。この関係は、天孫族と国津神との協力と融合を象徴しています。ニギハヤヒは、大国主命の支配地域において、天孫族の統治を確立するために努力し、その結果、天孫族の支配が広がったとされています。
ニギハヤヒは大物主神のことであるという説
大物主神は、大神神社に祀られる神様で、大国主命と関連の深い神様です。大国主命の魂であるとも書かれています。
蛇神や龍神であるとも言われます。
広告
ニギハヤヒを祀る神社
ニギハヤヒは、物部氏の祖神としても崇められています。彼を祀る神社の一つに、奈良県の石上神宮(いそのかみじんぐう)があり、ここでは物部氏の祖神としてニギハヤヒが祀られています。また、奈良盆地とその周辺地域の大和地方を中心に多くの神社でニギハヤヒが祀られており、その存在は古代日本において非常に重要でした。
広告
天皇から続く血筋の正当性を証明するために神話を変更した可能性
現在の天皇家の直系の祖先とされているのは、ニギハヤヒ(饒速日命)ではなく、ニニギノミコト(邇邇芸命)です。神武天皇(初代天皇)の祖先はニニギノミコトとされています。
天皇家の直系
ニニギノミコトは、天照大御神の孫であり、天孫降臨の際に地上に降り立ったとされる神です。ニニギノミコトの曾孫が初代天皇である神武天皇です。この系譜は『古事記』や『日本書紀』に詳しく記されています。したがって、現在の天皇家の系譜はニニギノミコトを通じて天照大御神に遡るとされています。
ニギハヤヒと天皇家
ニギハヤヒも天孫族の一員として記録されていますが、彼の子孫は物部氏とされ、天皇家とは異なる系統とされています。物部氏は古代日本の有力な氏族であり、主に武力を担当した氏族です。
神話の変更の可能性
神話が都合の良いように変更された可能性については、歴史学や神話学の視点から以下の点が考えられます。
政治的目的
神話や伝説が政治的目的で改変された可能性はあります。特に、天皇家の正統性を主張するために、特定の系譜を強調したり、他の系譜を抑えたりすることがあったと考えられます。
『日本書紀』と『古事記』の違い
『日本書紀』と『古事記』などの書物は、奈良時代に編纂されました。編纂者たちは、当時の政治的背景や宗教的信念を反映して、天皇家の正統性を強調するために神話を調整した可能性があります。
物部氏と天皇家の関係
物部氏と天皇家の関係が緊張していた時期があったことも、神話の記述に影響を与えたかもしれません。物部氏がニギハヤヒの子孫とされていることは、氏族間の権力闘争や政治的な対立を反映していると考えられます。
広告
ニギハヤヒとジブリアニメ
ニギハヤヒという神様はこのように、高天原から地上世界に降り立った天津神でありながら、神武天皇より先に地上で過ごしており、結果的に神武天皇が東征をして大和を平定することで正当な天孫の系譜となっていくという歴史があります。変わった流れがあることから、宮崎駿作品のジブリ作品でもニギハヤヒがモデルになったと言われるキャラクターもいます。
千と千尋の神隠し「ハク」(ニギハヤミコハクヌシ)
ハクの本名は、龍神「ニギハヤミコハクヌシ」です。名前を見てわかるように、ニギハヤミというところがまさにニギハヤヒと類似しており、何かしらの思惑を感じられます。ニギハヤヒは紹介してきたように、古代日本である大和に先住していた天孫系の神であり、後から来た神武天皇が私が正統だと示して譲り渡したという神様です。ハクも地上のコハク川の神としていましたが、埋め立てられて場を失ったという話があり、おそらく川とともにニギハヤミコハクヌシという神様も消されてしまったという暗示もあります。ニギハヤヒと似たような境遇を重ねているのかもしれません。
まとめ
現在の天皇家の直系の祖先はニニギノミコトとされていますが、神話や伝説が政治的な目的で改変された可能性は存在します。これらの改変があったとすれば、天皇家の正統性を強調するためのものであったと考えられます。歴史的な文献や神話を解釈する際には、当時の政治的背景や社会的状況を考慮することが重要です。