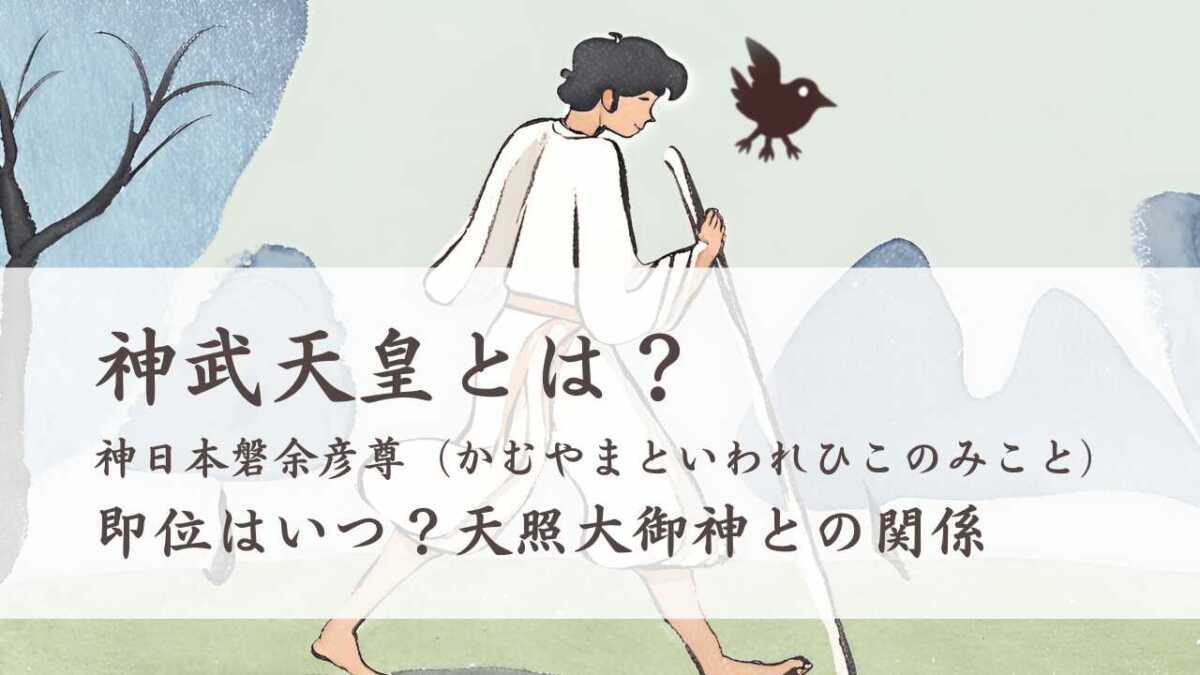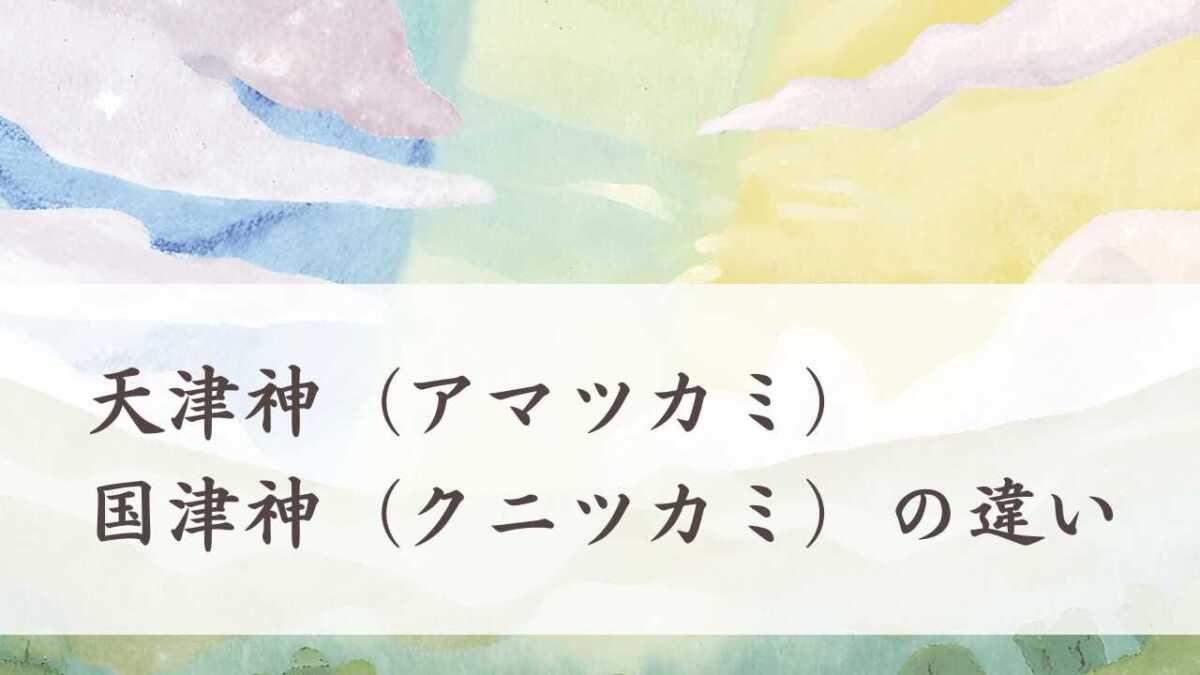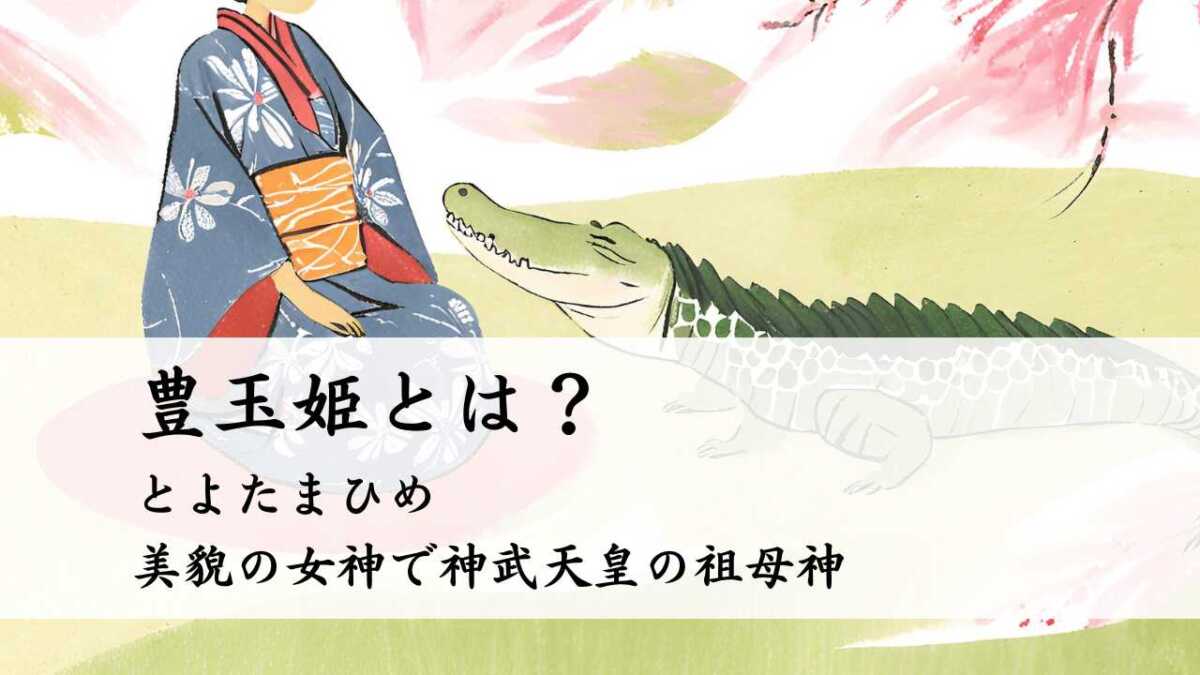
豊玉姫(トヨタマヒメ)は、日本神話に登場する海の女神であり、海神ワタツミノカミの娘にして、天孫ホオリノミコトの妻となった神格です。その美貌と神秘性、そして神武天皇の祖母としての重要な系譜により、神話全体の中でも特に印象的な存在です。海と山、神と人との結びつきを象徴する豊玉姫の神話は、出産や別れ、母性と神聖の境界を描きながら、今日に至る信仰にも強い影響を残しています。
広告
豊玉姫の名前と意味
豊玉姫(とよたまひめ)は、日本神話に登場する海の女神であり、海神オオワタツミノカミの娘とされています。
漢字では「豊玉毘売命」「豊玉姫命」などと表記され、「豊玉」は「豊かな玉」「宝玉があふれる」という意味を持ち、海底の豊かさや神秘性、美しさを象徴する名と考えられています。玉は古来より霊力や神秘を帯びた存在とされており、豊玉姫の神性や美貌がこの名前にもよく表れています。
広告
系譜と神武天皇の祖母としての位置づけ
豊玉姫は海の神であるオオワタツミノカミの娘で、ホオリノミコト(火遠理命)と結婚し、ウガヤフキアエズノミコトを産んだ女神です。そのウガヤフキアエズノミコトの子が初代天皇・神武天皇であるため、豊玉姫は神武天皇の祖母にあたります。
この系譜によって、天皇の祖先に海の神の血が流れていることが強調され、日本という国の成立に海の神格が深く関与していることを物語っています。
家系図でみる系譜・神武天皇との関係
物語の系譜をわかりやすくするために、『古事記』系の並びをもとに簡略化して示します。
| 世代 | 神名・人物 | 説明 |
|---|---|---|
| 父 | 邇邇芸命(ににぎのみこと) | 天照大御神の命で高天原から天孫降臨した |
| 母 | 木花開耶姫(このはなさくやびめ) | 山の神である大山祇命(オオヤマツミ)の娘 |
| 三兄弟 | 長男・火照命(ほでりのみこと)=海幸彦 | 海の漁労を象徴する兄 |
| 三兄弟 | 次男・火須勢理命(ほすせりのみこと) | 中つ子(物語ではあまり中心に立たない) |
| 三兄弟 | 三男・火折尊(ほおりのみこと)=山幸彦 | 山・狩猟を象徴する末子、本話の主人公 |
| 山幸彦の妻 | 豊玉毘売命(とよたまびめ) | 海神・大綿津見神の娘。山幸彦の妻となる |
| 山幸彦と豊玉姫の子 | 鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと) | 海の一族と天孫の血が合流した子。 豊玉姫の妹・玉依姫(たまよりひめ)が育てる。 |
| 鵜葺草葺不合尊と玉依姫の子 | 神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと)=神武天皇 | 鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)と玉依姫(たまよりひめ)の間に生まれ、初代天皇となる |
広告
ホオリノミコトとの出会いと結婚
豊玉姫は、釣り針を探して海神の宮殿を訪れたホオリノミコトと出会い、やがてホオリノミコトと結婚します。ホオリは海神の宮に三年間滞在し、豊玉姫と夫婦となって平穏な時を過ごします。神話によれば、豊玉姫はホオリに一目惚れしたとも、父の命により婚姻したとも伝えられており、いずれにせよ海の神族と天孫族の婚姻という大きな意味を持つ結びつきでした。これは、天と海、異なる神格が融合する象徴的な場面とされ、日本神話における秩序の安定と神々の血統の正当性を裏付けるものでもあります。
広告
出産と別れの神話
豊玉姫とホオリノミコトは夫婦となりますが、やがてホオリが地上に戻ることになります。豊玉姫は彼の子を身ごもったまま、地上まで追いかけてきて出産します。出産の際、豊玉姫は自らの本来の姿である和邇(ワニ、つまり海獣または龍神のような姿)となって子を産もうとしますが、それを見てしまったホオリに対して深く恥じ入り、出産後に海へと帰ってしまいます。
このエピソードは、人間と神、日常と神秘の境界を象徴しており、神の本質を暴こうとする行為が神との断絶を招くという神話的教訓を内包しています。
広告
海の神としての神格と役割
豊玉姫は海神の娘として、豊穣と生命力、そして母性を象徴する存在です。豊かな海の恵みを表すだけでなく、出産という神聖な営みを担う神でもあり、後世においては安産や子授けのご利益がある神としても信仰されるようになりました。また、その美しさと神秘性から、美容や女性の魅力を象徴する神格とも結びついています。海という不可視の世界に属しながら、人間の世界と深く関わった女神であることから、神と人をつなぐ存在としても重要な役割を果たしています。
広告
現代における信仰と神社
豊玉姫を祀る神社は、主に九州南部や海にゆかりのある地域に分布しています。特に鹿児島県知覧町の「豊玉姫神社」や宮崎県の青島神社などが有名です。これらの神社では、海の守護神として航海の安全、漁業の繁栄、安産などを願う人々に親しまれています。また、女性の守護神としても信仰を集めており、美しさや家庭円満、子宝などを願う参拝者が訪れています。
広告
神話における象徴的な存在
豊玉姫は、日本神話における女性神の中でも特に象徴性の強い存在です。その美貌、母性、神秘性、そして人間との関係性は、神話の中でも際立った個性を持っています。ホオリとの関係を通じて、異なる世界を結ぶ媒介者としての役割を果たし、その後の神武天皇へと続く血統を形成する重要な神でもあります。豊玉姫の神話を読み解くことは、海と山、神と人、見えるものと見えざるものの境界を理解する手がかりとなります。