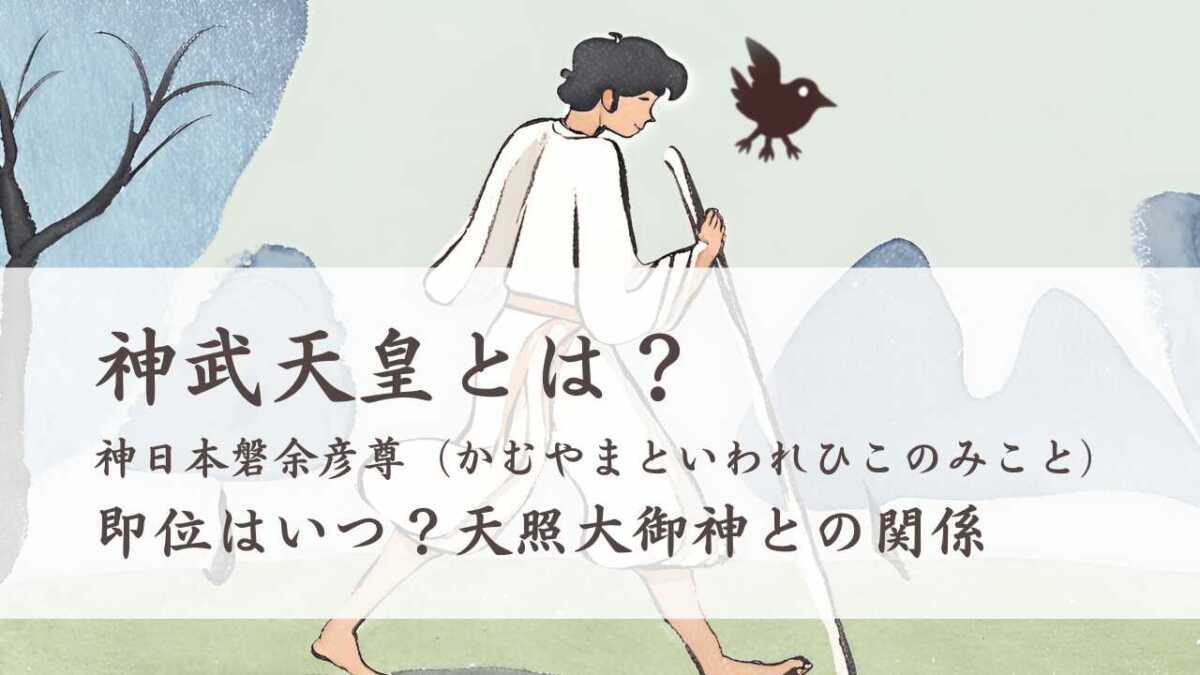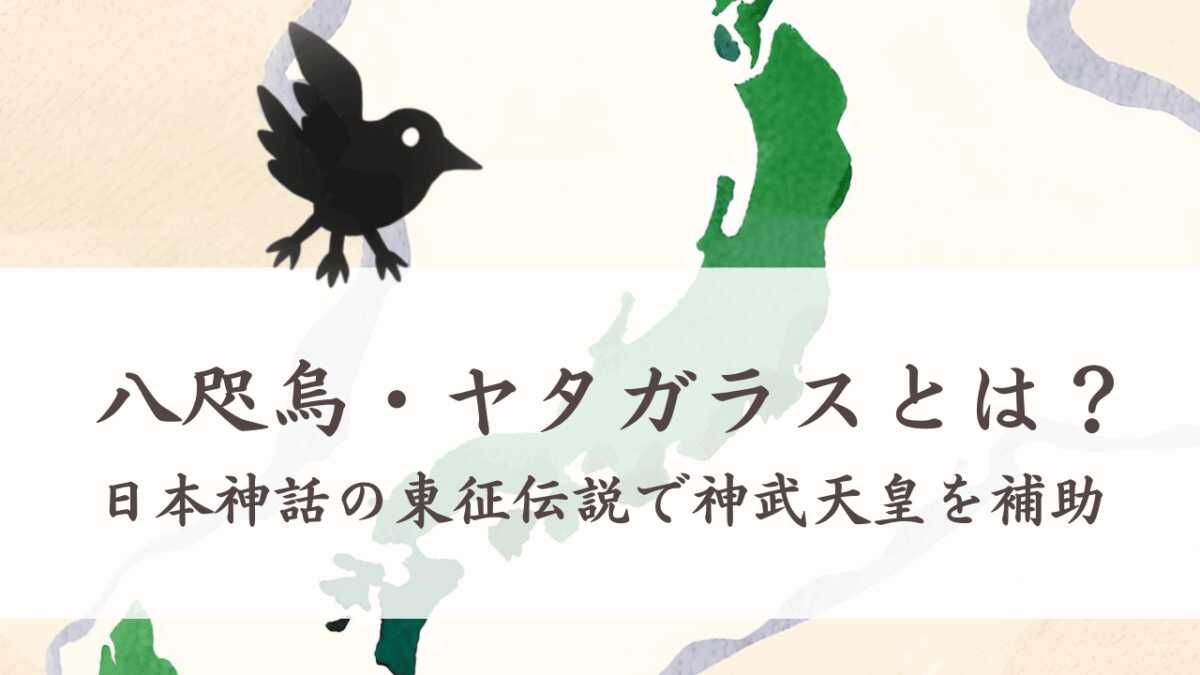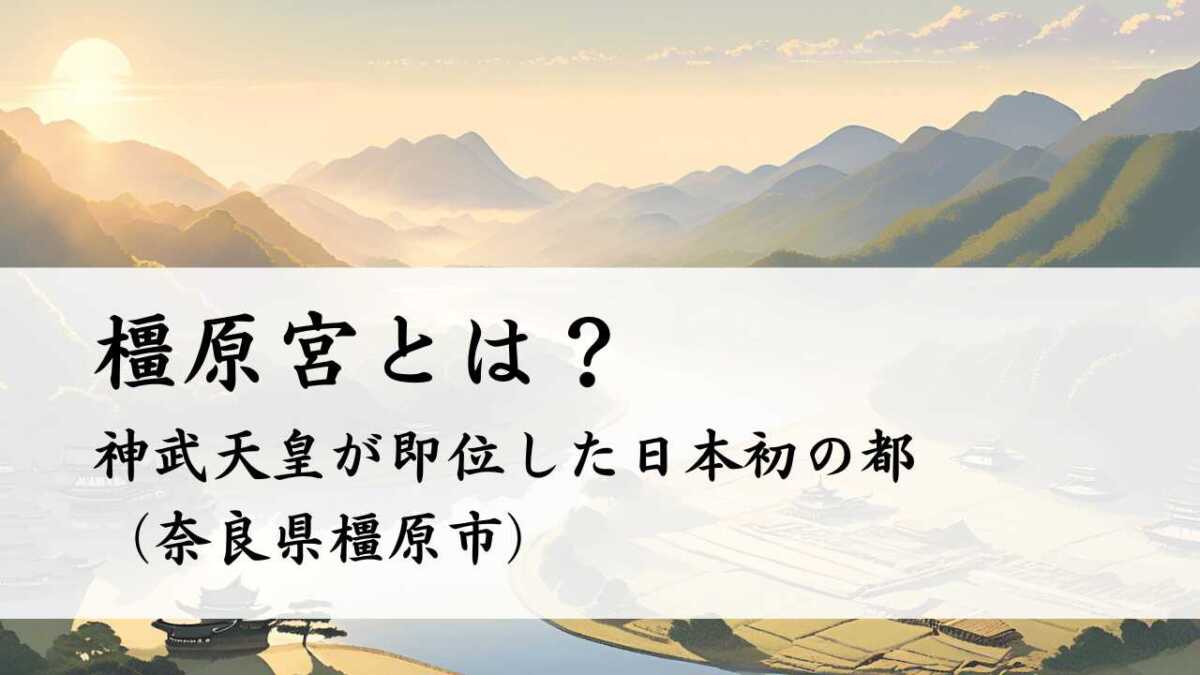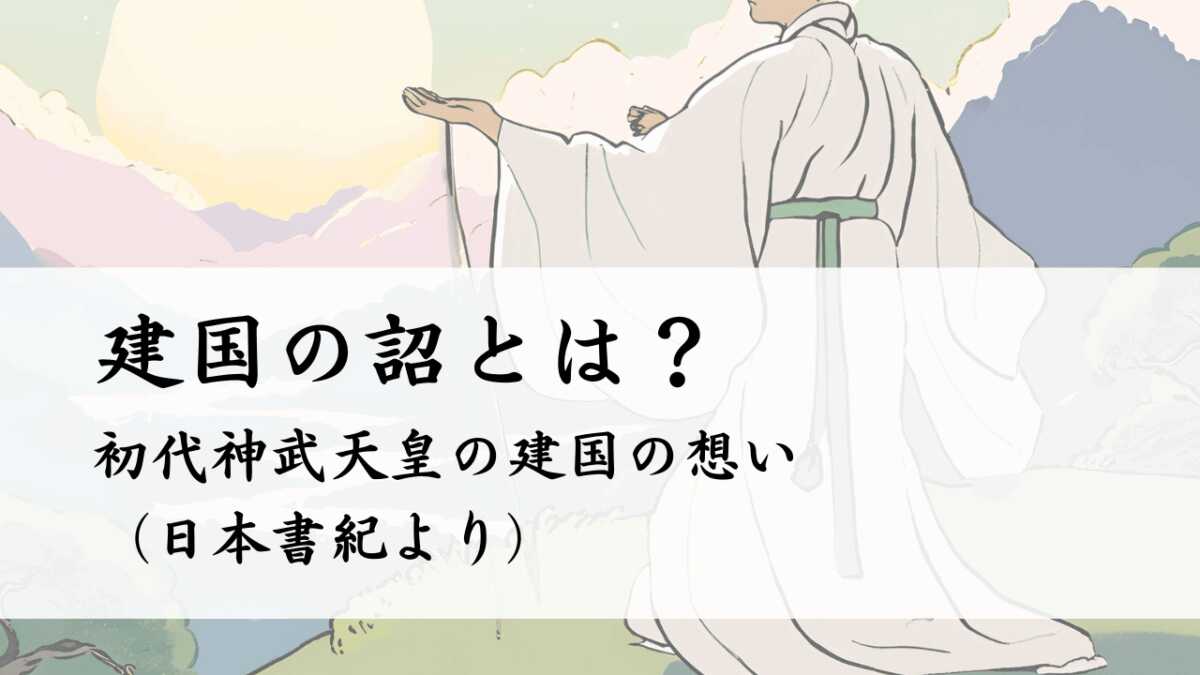毎年2月11日は「建国記念の日」として、日本の建国を祝う祝日とされています。しかし、「建国記念日」ではなく「建国記念の日」と表記されるのはなぜでしょうか?この日は、日本最初の天皇とされる神武天皇(じんむてんのう)が即位した日に由来するとされていますが、実際に何があったのでしょうか?本記事では、日本神話における建国の伝説や「建国記念の日」の歴史を詳しく解説します。
広告
建国記念の日とは?
建国記念の日(けんこくきねんのひ)は、日本の建国を祝う国民の祝日で、毎年2月11日に定められています。この日は、日本が建国されたことを記念し、国を愛し発展を願う日とされています。しかし、「建国記念日」ではなく「建国記念の日」と表記されることには理由があります。
実は、日本がいつ建国されたのか正確な日付は不明です。そこで、古代の歴史書『日本書紀』をもとに、初代天皇である神武天皇(じんむてんのう)が即位した日とされる日を記念日とし、「建国記念の日」と定められました。
広告
2月11日は日本神話で何があった?
2月11日が「建国記念の日」として選ばれたのは、神武天皇が即位した日とされる紀元前660年(日本書紀の記述による)1月1日(旧暦)を、新暦(現在の太陽暦)に換算した結果、この日が選ばれたためです。
神武東征と日本建国の神話
神武天皇は、日本神話における天照大御神(あまてらすおおみかみ)の子孫であり、日向(現在の宮崎県)で生まれました。彼は「豊葦原の瑞穂の国」(とよあしはらのみずほのくに=日本)を治めるために、東へ向かって遠征を行いました。この旅は「神武東征(じんむとうせい)」と呼ばれます。
神武天皇は各地で戦いながら進み、奈良県の橿原(かしはら)に到達します。そして、紀元前660年の1月1日(旧暦)に橿原宮(かしはらのみや)で即位し、日本の初代天皇となりました。この出来事が「日本の建国」とされており、これを祝うために建国記念の日が制定されたのです。
建国の詔(けんこくのみことのり)と建国記念の日
「建国の詔(けんこくのみことのり)」とは、日本の初代天皇とされる神武天皇が即位した際に発したとされる詔(みことのり)で、『日本書紀』に記録されています。この詔には、日本を統治する方針や理想が示されています。
この詔の内容を簡単に要約すると、「日本を広く安定した国にし、民を幸福に導く」というものです。神武天皇は、橿原宮(奈良県橿原市)において即位し、この詔を発したことで、日本の統治が本格的に始まったとされています。
「建国記念の日」は、この神武天皇の即位と「建国の詔」を記念する日として制定されました。具体的には、『日本書紀』の記述によると神武天皇の即位は紀元前660年1月1日(旧暦)とされており、明治政府がこの日を新暦に換算した結果、現在の2月11日が「建国記念の日」として選ばれました。
したがって、「建国記念の日」は単なる歴史的な出来事を記念するものではなく、神武天皇の即位とその理念を象徴する「建国の詔」に基づき、日本の建国精神を讃える日として位置づけられています。
広告
建国記念の日の歴史
建国記念の日は、もともと「紀元節(きげんせつ)」という祝日でした。
紀元節の制定(明治時代)
明治政府は、西洋のように国民の統一意識を高める祝日を設けるため、『日本書紀』をもとに神武天皇即位の日を「日本の建国の日」としました。そして、1873年(明治6年)に紀元前660年1月1日を太陽暦に換算し、2月11日を「紀元節」として制定しました。これは、当時の欧米諸国に対し、日本が長い歴史を持つ国家であることを示す意味もありました。
紀元節の廃止と復活(戦後)
第二次世界大戦後、日本はGHQ(連合国軍総司令部)の占領下に置かれ、戦前の国家主義的な祝日が見直されることになりました。その結果、紀元節は1948年(昭和23年)に廃止されました。しかし、戦後の復興が進む中で、再び日本の建国を祝う日を設けるべきだという意見が高まりました。
その結果、1966年(昭和41年)に「建国記念の日」として復活し、翌年の1967年(昭和42年)から正式に祝日となりました。
広告
現代における建国記念の日の意義
建国記念の日は、日本の誕生を祝う日であると同時に、「日本という国の成り立ちを考え、未来へ発展させることを願う日」とされています。そのため、全国各地で神社の祭典や式典が行われます。特に、神武天皇が即位したとされる奈良県橿原市の橿原神宮では、毎年盛大な「建国記念祭」が開催されます。また、その他の神社でも建国記念の日に合わせて「紀元祭」が行われています。
また、学校では日本の歴史について学ぶ機会となり、政治家や有識者による記念講演が行われることもあります。近年では、建国記念の日の意義を見直し、日本の文化や伝統を次世代に伝える取り組みも増えています。
建国の詔(けんこくのみことのり)を再認識
建国の詔(けんこくのみことのり)の原文は、『日本書紀』神武天皇即位の条に記されています。以下に原文とその現代語訳を示します。
原文(『日本書紀』巻第三 神武天皇即位の詔)
夫れ、葦原千五百秋の瑞穂の国は、是れ我が皇孫の王たる可き地なり。
宜しく、天壌無窮の神勅を承けて、皇基を建てむ。
当に、六合(くにのうち)を兼ねて都を開き、八紘(あめのした)を掩(おお)ひて宇(いえ)と為(せ)むこと、亦可(よ)からずや。
遂に都を橿原の地に建てたまふ。
現代語訳
そもそも、この豊葦原の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂の国(日本)は、我が皇孫(すめみま=天皇家の子孫)が治めるべき国である。
天の神々より受け継いだ「天壌無窮(てんじょうむきゅう)」の神勅(しんちょく=永遠に栄えるべき国を築けという神の命)を守り、皇室の基盤を築くべきである。
国土を統一し、都を開き、天下を覆って一つの家とする(八紘一宇の思想)、これはまことに素晴らしいことであろう。
このようにして、橿原の地に都を定める。
広告
海外の建国記念日と日本の建国記念の日の違い
海外の多くの国では「建国記念日」は独立や革命、憲法制定など具体的な歴史的出来事に基づいて制定されています。例えば、アメリカの独立記念日(7月4日)は、1776年にイギリスからの独立を宣言した日、フランスの革命記念日(7月14日)は1789年のバスティーユ襲撃を記念する日です。また、ドイツの統一記念日(10月3日)は、1990年の東西ドイツ統一を祝うものです。
一方、日本の「建国記念の日」は、実際の建国の日ではなく、『日本書紀』の神話に基づく神武天皇即位の日(紀元前660年)を換算したものです。このため、日本の建国記念の日は歴史的事実ではなく、伝説や神話を元にした日である点が、海外の建国記念日と大きく異なります。また、日本は外国の支配から独立した歴史を持たないため、「独立記念日」ではなく、「建国記念の日」として制定されました。
このように、日本の「建国記念の日」は国家の成立を祝う精神的な記念日であり、具体的な歴史的事件を基にする海外の建国記念日とは性格が異なります。
広告
まとめ
「建国記念の日」は、日本の建国を祝う大切な日です。その由来は、日本神話における神武天皇の即位にあり、これを記念して2月11日が選ばれました。
- 古代の神話に基づく記念日であること
- 明治時代に「紀元節」として制定され、戦後に廃止・復活した歴史
- 現代では日本の発展を願い、歴史を振り返る日として意義がある
これらを理解することで、「建国記念の日」の意味をより深く考えることができます。