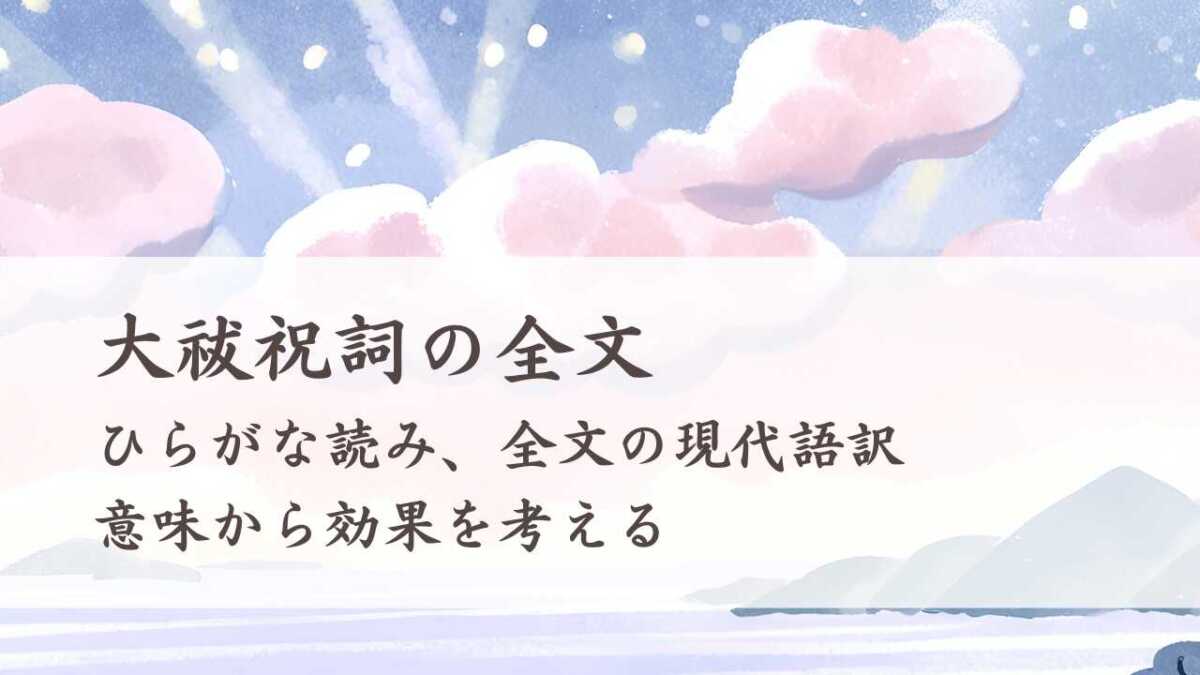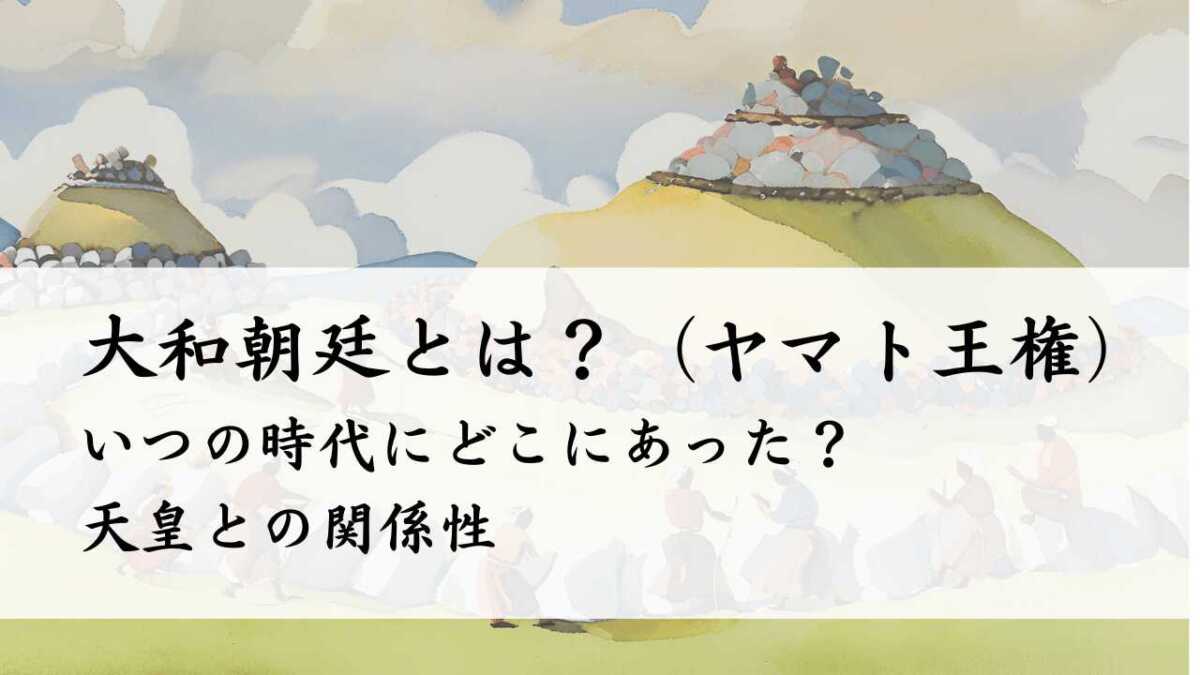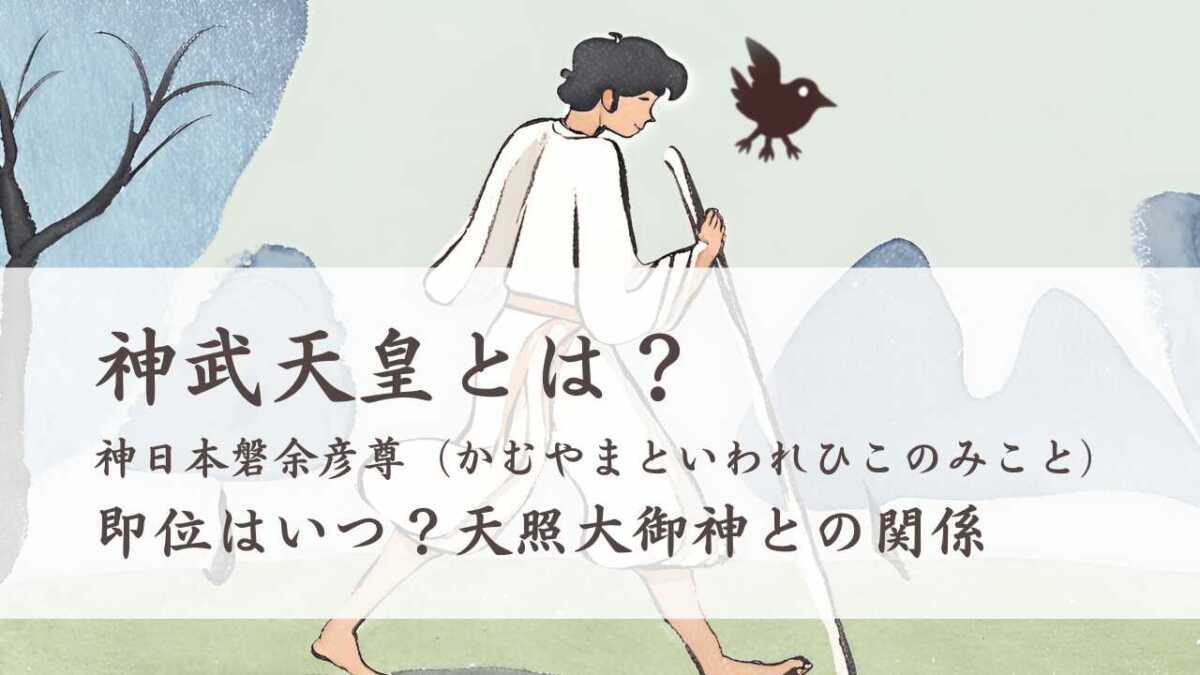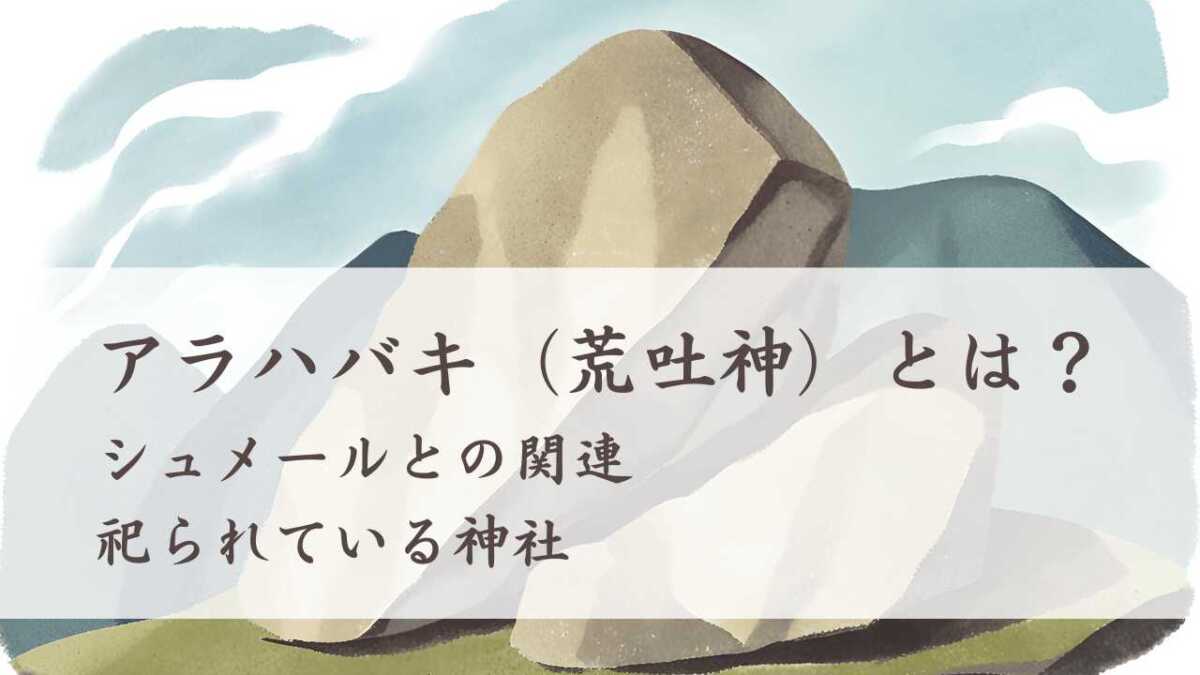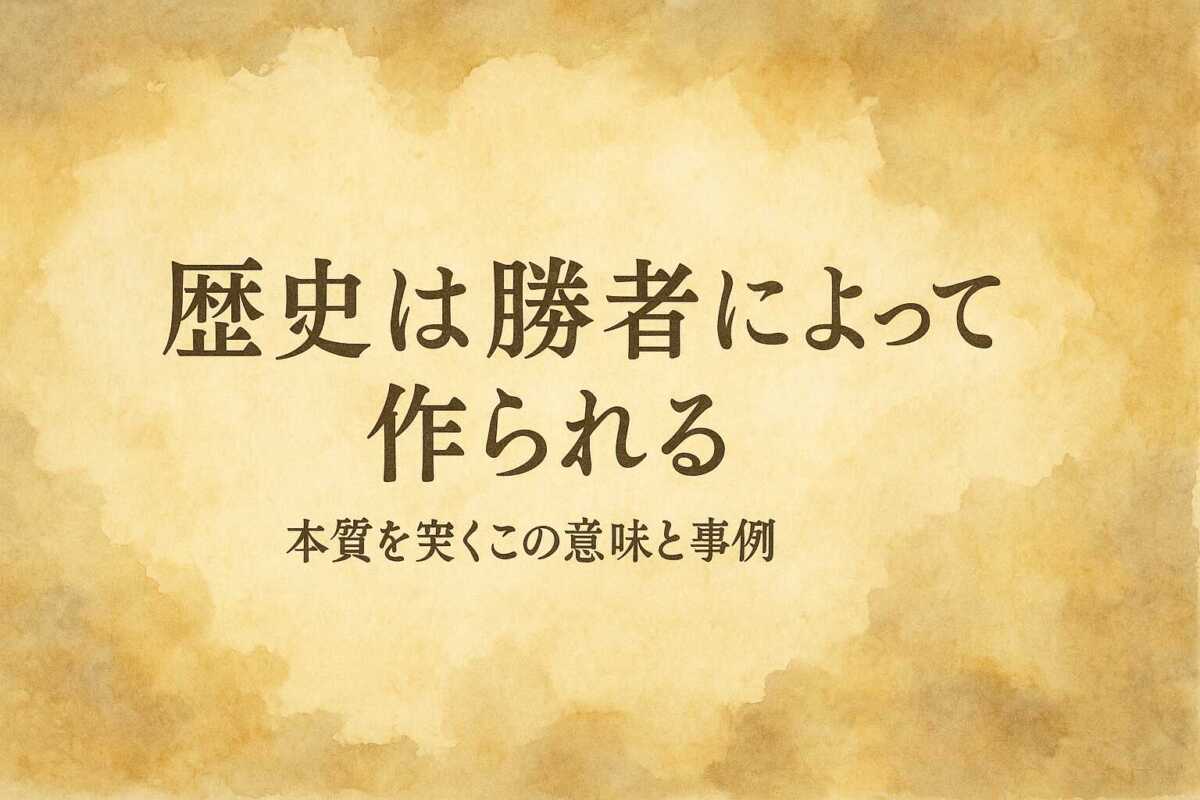日本神話や古代史において、「日高見国(ひたかみのくに)」「日上国(ひのくに)」という言葉は、東北地方にかつて存在したとされる謎多き国を指します。一般的な歴史教育では語られることの少ないこの存在は、大和朝廷とは異なる文化圏を築いていた可能性があり、日本の成り立ちにおいて重要な役割を果たしていたのかもしれません。本記事では、日高見国の概要やその独自性、常陸や高天原との関係、さらにはアラハバキ信仰やユダヤ人渡来説、田中秀光教授の研究、そして「日本国」という国号の成立史までを多角的に掘り下げていきます。
広告
日高見国(日上国)とは?
日高見国(ひたかみのくに)あるいは日上国(ひのくに)とは、古代日本において現在の東北地方に存在したとされる独自の国の名称です。『日本書紀』や『古事記』には直接的な記述は少ないものの、大祓詞(おおはらえのことば)などの神道の文献や、東北地方に伝わる口承や地名の中にその痕跡を見つけることができます。
日高見国という名前には、「日が高く見える国」「日が登る国」という意味合いが込められており、日本列島の東端にあたる地域が太陽の昇る方角として、神聖視されていた可能性が示唆されます。
広告
日高見国は独自の国だった
日高見国は、大和朝廷が成立する以前から存在していたとされる独自の政治体制を持つ国家的存在であったと考えられています。つまり、日高見国は大和政権よりもはるか以前、縄文時代から存在した可能性があるのです。
日本における国家形成が弥生時代以降とされる通説に対して、東北・関東を中心とした縄文文化圏に既に国家的なまとまりがあった可能性があるという視点は、日高見国の歴史をより古層にまでさかのぼらせる新しい仮説です。
近畿地方を中心とした歴史観では日高見国について語られることが少なかったため、長らく歴史の表舞台に登場することがありませんでした。しかし、東北地方にも王が存在し、独自の文化や信仰体系を持っていたことが、近年の研究によって明らかになりつつあります。古代の日本列島は複数の「国」に分かれており、それぞれが独自の王権を有していたという考え方に立てば、日高見国もその一つであったと見るのが自然です。
縄文から弥生への移動と東北の変遷
縄文中期までは東北や関東地方が温暖で人口も多く、定住文化が発達していたが、弥生期に気候の寒冷化や鍛錬化により、人口が西日本(関西・九州)に移動したと指摘されています。この移動の結果、日高見国の中心地は次第に周縁化し、歴史から取り残されていったという仮説は、地政学的な背景として非常に重要です。
広告
日高見国と、茨城県常陸(日立)・鹿島との関係
茨城県の常陸(ひたち)地方、特に日立市周辺にも「ひたかみ」の語源と関係する地名が残っています。これが東北の「日高見国」とどのような関係を持っていたかについては定説があるわけではありませんが、共通する名称や信仰の痕跡から、文化的・宗教的なつながりがあった可能性が考えられます。常陸は古代より東国の要所であり、大和朝廷との交流や戦いの舞台となることも多かった地域です。こうした地理的・歴史的背景の中で、日高見と常陸が連携し、あるいは同一文化圏に属していた可能性は否定できません。
関東や鹿島が「日高見国」とつながる地理的証拠
関東(特に茨城県・鹿島地域)にも日高見国の痕跡があるとされ、「鹿児島」の語源が「鹿島の子」であるという説や、鹿島神宮・香取神宮の存在が日高見の南限を示しているという指摘は、日高見国の範囲が単に東北だけでなく関東南部まで及んでいた可能性を示唆します。鹿島から宮崎を経て南下した神武天皇の話とも符合する構造がここにあります。
正史(『日本書紀』)における神武東征とは?
基本的なストーリーとして、日本神話における「神武東征」は以下のように描かれています。
| 神話の要点 | 内容 |
|---|---|
| 出発地 | 日向国(現在の宮崎県) |
| 経路 | 九州から瀬戸内海沿岸を経由して東へ進軍 |
| 上陸地 | 熊野(和歌山県) |
| 終着地 | 大和国(現在の奈良県)で政権樹立 |
| 結末 | 神武が初代天皇として即位し、日本建国の始まりとなる |
これは、南九州を出発点として「東」へ向かう征服譚です。これが「神武東征(東に向かう)」と呼ばれる所以です。この考え方の主な根拠は以下のようなものです。
「実は神武の勢力(もしくは天孫系の先祖)は関東や東北から南下して九州に至った」という流れを示唆しています。
1. 鹿島神宮の重要性
茨城県鹿嶋市にある鹿島神宮は、武神タケミカヅチを祀る古社であり、記紀神話でも「国譲り」の場面で高天原の意志を地上に伝える重要な役割を果たしています。鹿島の神が天孫降臨以前に動いていることから、天孫族以前に関東・東北に霊的・政治的中枢があった可能性が指摘されます。
2. 神武天皇の母系・祖先神との接点
神武の祖先である天照大御神(あまてらすおおみかみ)や高御産巣日神(たかみむすび)は、高天原の神々とされますが、これを地理的ではなく文化的に「高き処」=東の霊地と解釈する見方もあります。つまり、「高天原=日高見(東北)」という再構成がなされることで、神の血統が東国に由来していたとする説が生まれます。
3. 鹿島から宮崎へという移動の痕跡
「鹿児島」の地名は、古くは「鹿島の子(=分霊、分社)」という意味で解釈されることがあり、鹿島神宮の分霊が南に伝播していったとする言い伝えがあります。この伝承が、神武の南下=東国から日向(宮崎)への移動を示す文化的・宗教的裏付けになっているという説です。
広告
日高見国と高天原の関係
日本神話において、神々の住む世界として語られる「高天原(たかまがはら)」と、日高見国の関係性にも注目が集まっています。高天原は天上界とされていますが、地理的な象徴とも解釈されることがあり、一部の学説では東の果てに存在する「日の出る場所」がそのイメージと重なると考えられています。日高見国が「日が登る国」「日を仰ぐ国」として神聖視されていたとすれば、高天原の原型や比喩的表現として、日高見が神話の舞台に組み込まれた可能性もあります。
広告
日高見国とアラハバキの関係
日高見国と深い関わりがあるとされる信仰のひとつが「アラハバキ神」です。アラハバキ神は、東北地方を中心に祀られていた土着の神であり、その由来や正体については謎が多く残されています。もともとは外敵を防ぐ神、境界を守る神として信仰されていたとされ、古代の戦いや国境の管理と関わりがあったと見られています。大和政権の拡大とともに、アラハバキ信仰は抑圧された形跡もあり、日高見国の独自性や抵抗精神を象徴する存在とも考えられます。
広告
日高見国とユダヤ人の関係
一部の古代史・オカルト史観では、日高見国と古代ユダヤ人との関連を指摘する説も存在します。これは、日高見国の祭祀や風習が、古代イスラエルの文化と類似している点が複数見られることから主張されている仮説です。特に、神道に見られる神宝の構造や神社建築、祝詞などが、旧約聖書に記された祭礼と似ているとの指摘があり、日高見国が何らかの形でユダヤ的要素を受け入れていたのではないかという見解もあります。ただし、これについては学術的な裏付けが十分とはいえず、あくまで民間伝承や仮説の域を出ないものとして扱う必要があります。
広告
日高見国の中心とされる候補地
岩手県北上川流域(特に奥州市水沢・北上市周辺)
北上川流域は、「日が昇る国(=日高見)」の語源とされる「日高見」または「日上」という名称の元になったともいわれています。特に奥州市水沢の「黒石寺」や、北上市の「成島毘沙門堂」周辺には、古代からの祭祀遺跡や律令以前の集落跡が確認されています。
胆沢城(いさわじょう)跡も近くにあり、これは後の蝦夷支配のために大和政権が設置した拠点ですが、それ以前にも先住勢力の中心地だった可能性があると考えられています。
宮城県栗原市~登米市一帯
宮城北部の栗原市・登米市周辺は、「日高見国」の地勢的な中心とする説もあり、かつてこの地域は「日高見郡(ひたかみぐん)」と呼ばれていたことも注目されています。この地にある「金成延年神社(くねりえんねんじんじゃ)」や「花山神社」などの神社は、アラハバキ信仰と結びつけられることがあります。
また、栗原市にはアラハバキ神の巨石信仰に関わると思われる「荒覇吐神社」も存在します。
青森県南部~秋田県北部
青森の南部地方には、アイヌ語由来とも言われる古地名が点在し、蝦夷文化との関連性が強く指摘されています。
秋田県大館市や能代市にも、アラハバキや土着神に関連した神社や古墳が残されており、広域的な信仰圏があったことをうかがわせます。
現存する神社・史跡(関連が深いとされるもの)
| 地名 | 神社・遺跡名 | 関連性・特徴 |
|---|---|---|
| 岩手県奥州市 | 黒石寺 | 古代祭祀跡の可能性、鬼剣舞との関連も |
| 岩手県北上市 | 成島毘沙門堂 | 東北の仏教伝来初期の遺構とされる |
| 岩手県奥州市 | 胆沢城跡 | 後の大和政権の城柵だが、前身的な集落があった可能性 |
| 宮城県栗原市 | 荒覇吐神社 | アラハバキ信仰の中心神社の一つとされる |
| 宮城県登米市 | 金成延年神社 | 地元の古伝承や地名と深く結びつく |
| 青森県三戸郡 | 多賀神社 | 古代祭祀との関連やアラハバキ信仰の影響があるという説 |
日高見国の「都」と断定できる考古学的な証拠はまだ限定的ですが、北上川流域(岩手県)から宮城県北部にかけてが政治的・文化的な中核だったと見るのが有力です。こうした地域には、アラハバキ信仰や日高見の名を残す神社・史跡が今も存在しており、それらが日高見国の実在性を示す重要な鍵となっています。
広告
「日高見国」や、東北・北海道は否定的描写が多い、その意図
祝詞や古史で日高見国や東北・北海道の出来事や人々は登場するものの、その描かれ方は野蛮で従わない民=エミシ(蝦夷)という否定的なものが多くなっています。しかし、これは編纂された時代の政権が近畿にあったこと、そして自分たちの正統性を強調するために別系統の文化圏であった日高見国を意図的に軽視・敵視した可能性があるという視点もあります。
「歴史は勝者によってつくられる」という言葉ありますが、編纂者がどのような立場であるかにより、記述の仕方は異なるのが歴史を紐解く時の難しいところです。
田中秀光教授が「日上国」と東北地域を整理・解説し再注目
東北大学名誉教授であった田中秀光氏は、古代日本における東北の歴史的意義を再評価し、「日上国」という概念を体系的に整理したことで注目を集めました。田中秀光教授は、地名・古文書・神話の分析を通じて、日高見国が単なる地方ではなく、明確な国としての構造を持っていたことを論じました。その業績は『日本の起源は日高見国にあった』といった著書にまとめられており、現代においても地域アイデンティティの再構築に貢献しています。田中教授の研究は、これまで中心から外されていた東北の歴史に光を当てる大きな契機となりました。
新井白石による関東・東北起源説
江戸時代の儒学者・新井白石も、神は人間だったという視点から、「関東・東北の祖先が神とされ、大和朝廷を作った」という説を展開しています。これは、古代神話の神々の実在性や、関東・東北地域の先住民が日本国家の起源に関わったという可能性を示す思想的背景となっています。
日本国という言葉の成立の歴史
「日本国」という国号が国際的に承認されたのは奈良時代に入ってからのことです。それ以前、中国や朝鮮の歴史書では「倭国(わこく)」あるいは「和の国」と呼ばれていました。663年の白村江の戦いで敗北した後、日本は30年近く外交的に孤立する時期を迎えますが、遣唐使が再び派遣された際、中国側に提出した国書の中に「日本国」という言葉が用いられ、これが事実上の国号として認識されることになります。
この「日本(ひのもと)」という名称は、日の昇る国という意味を持ち、日高見国が持っていた地理的・象徴的価値と響き合うものです。東北という「日が昇る場所」の概念が、日本全体を指す名称に昇華されたという点でも、日高見国の存在は日本の国号の由来に深く関わっていると見ることができます。